沖縄の米軍普天間基地の辺野古移設反対で、翁長雄志知事を中心に「オール沖縄」(沖縄県の政党や県民の中で保守派と革新派が協調)となって、日本政府と対立している現状について、その解決の方向性を、『戦後沖縄と米軍基地――「受容」と「拒絶」のはざまで 1945~1972年』の著者で、沖縄政治や日本政治を研究する平良氏に聞いた。(聞き手/「ダイヤモンドQ」編集委員 大坪 亮)
──平良さんの著者や論文では、「1950年代は沖縄では超党派でまとまれる基盤が強かった」ということですが、今回の「オール沖縄」は、どのように考えたらいいのでしょうか。
まず押さえなければならないのは、保革対立の政治枠組みは1960年前後に、本土から沖縄に流入したということです。それ以前の50年代は、超党派でまとまれる基盤がありました。米国の軍用地政策に反対した「島ぐるみ闘争」などはそのよい例です。
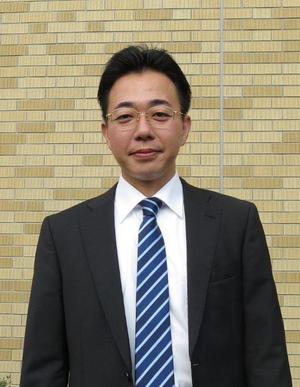 たいら・よしとし
たいら・よしとし1972年沖縄県那覇市に生まれる。95年沖縄国際大学法学部卒業。2001年東京国際大学大学院国際関係学研究科修士課程修了。08年法政大学大学院社会科学研究科博士後期課程修了。博士(政治学)。現在、獨協大学地域総合研究所特任助手。東京財団政治外交検証研究会メンバー。主著に『戦後沖縄と米軍基地―「受容」と「拒絶」のはざまで 1945‐1972年』(法政大学出版局)。
60年代以降、沖縄でも保革対立の政治構造が徐々に固まっていきます。その中身を詳しく見ると、国家レベルの問題では保革のスタンスは全く違いますが、地域レベルの問題では、両者は同じ方向性をもっていたということがわかります。
つまり、日米安保や米軍基地、そして自衛隊の存在については保革が真っ向から対立しましたが、基地の整理縮小や経済振興といった地域レベルの問題では、両者の間にそれほど大きな差はなかったのです。
この点の理解が重要で、保守は「経済振興」、革新は「基地問題」に注力したというような単純な捉え方をすると、沖縄政治は捉えそこなってしまう。ただ、そうはいっても、保守は「経済振興」をより重視し、革新は「基地問題」をより重視したことは間違いありません。
──状況が変化し、保革対立が変わったのですか。
両者を結びつける基盤のようなものが元々あり、沖縄を取り巻く「現実」そのものが変わっていけば、つまり「基地もなく、豊かな沖縄県」という「理想」に近づいていけばいくほど、両者の距離が接近してくるのは、ある意味、自然だということです。
米ソ冷戦の終結した1990年代から、基地返還の可能性が見え始めました。そして、経済振興によって基地への依存度も徐々に減っていったことから、保革がともに基地経済からの脱却と基地の整理縮小というものを、現実の課題として射程内に入れ始めたのです。よって、両者の距離は事実上接近してくるのです。
その縮まった範囲内において両者が対立したのが、普天間基地の辺野古移設問題だったわけです。革新陣営が辺野古移設に絶対反対を主張し、保守陣営が嫌々ながらも条件付きで容認するという政治構図が、98年以降、続いてきました。
そうした状況で、保守陣営が「辺野古移設反対」へと大きく舵を切るきっかけとなったのが、2009年の鳩山民主党政権誕生による普天間基地の「県外移設」の模索でした。




