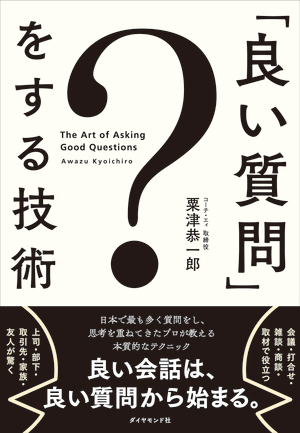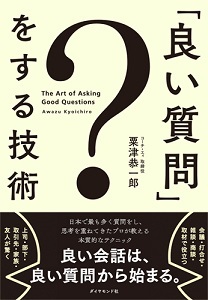日本で最も多く質問をし、思考を重ねてきたトップレベルのエグゼクティブコーチが10年来の探求と実践の成果をまとめた書籍、『良い質問をする技術』が発売されました。雑談・商談・会議・打合せ・取材で役立ち、上司・部下・取引先・家族・友人に感謝される「良い質問」とはどのようなものなのか?そのエッセンスを紹介する連載の第6回です。
質問が会社の文化と風土をつくる
質問の力は、周囲の「個人」にだけ及ぶものではありません。ときに何百人、何千人もが集まる組織にも、善かれ悪しかれ多大な影響を与えます。
会社でよく交わされる質問は、その組織の「企業文化」や「風土」とも密接な関係があるのです。
私が以前お会いした、あるベンチャー企業の社長に、Yさんという方がいました。そのベンチャー企業では、社員から新規事業のアイデアを集めて、良いアイデアは次々に事業化していくという方法をとっていました。しかし、Yさんが社長になって以来、社員たちからはたくさんのアイデアが出てくるものの、なかなか実現にはいたらず、Yさんは私にエグゼクティブ・コーチングの依頼をしてこられました。
社長のYさんに話を伺うと、「イノベーションを起こすようなアイデアが、次々と出てくる会社にしたい」とおっしゃいます。
ところが、アイデアを検討する会議に同席させてもらったところ、Yさんは、「それは儲かるのか?」「実現するまでにどれぐらいコストがかかる?」「本当にできるのか?」「他社ではやっているのか?」といった、聞かれた社員のアイデアが広がりにくい質問ばかりされていたのです。
「新規事業を成功させるために、そういう質問をするように心がけているんだよ。でも実際に聞いてみると、まだまだ細部まで考えられていないアイデアがほとんどでね。これまでビジネスとして実現したアイデアは1つもないんだ」
そう残念そうに語るYさんに、私は次のように質問しました。
「なるほど、そうですか。ちょっと思ったんですが、たとえば、同じIT業界ということで、もし創業時のグーグルの社長が今日の会議に出ていて、社員のアイデアを聞いたとしたら、どんな質問をすると思いますか?」
するとYさんはハッとした顔をしました。そして、しばらく目をつぶって考え込んだあとで、こう言いました。
「他社ではやっているか?とは、たぶん聞かないだろうな」
Yさんは、自分の質問が、新しいアイデアの芽を摘んでしまっている可能性があることに気づいたのでした。
もちろんビジネスですから、Yさんのように「儲かるか、儲からないか」をシビアに問いかける質問も必要です。しかしその問いは、「自由にアイデアを求める」場面では有効な質問ではありませんでした。
Yさんは自分が、儲かるのか、役立つのか、実現可能か、と質問することで、自分の想いとは裏腹に、会社を将来大きく発展させるかもしれないアイデアの芽を潰していたかもしれない、と気づかれました。
Yさんはその後、ミーティングでの質問を変えました。可能性を摘み取る質問から、次のような質問をするように心がけたのです。
「君はどうしてそのアイデアを実現させたいの?」
「市場はこれからの10年でどのくらい変化すると思う?」
「他にはどのようなアイデアがあるの?」
「その事業は5年後にはどうなっていると思う?」
「そのアイデアで世界をどう変えたいの?」
「他社と組むとしたらどんな会社?」
数年後、Yさんの会社では、いまや誰もが知るネットサービスを展開するようになりました。社内のアイデア会議では、次々に新しいサービスのタネが話し合われているそうです。
何気ない質問が、会社の未来を大きく成長させることもあれば、逆に、発展を阻害してしまうこともある。質問が組織に与える影響を示した、わかりやすい例と言えるでしょう。

“ほぼ日”の篠田真貴子さんのエピソード
また、こんな面白いエピソードを聞いたこともあります。超人気サイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営する東京糸井重里事務所のCFO、篠田真貴子さんのお話です。職場でよく聞かれる質問が、篠田さんがこれまで働いてきたそれぞれの会社で見事に違っていたそうです。
まず大学を出てからすぐに就職した銀行では、「他の銀行はどういう判断をしている?」というのが上司の口癖だったそうです。横並び意識が強いために、他行が気になって仕方がないということなのでしょうか。
その次に勤めた外資系コンサルティング会社では、ことあるごとに「So what?(だからなに?)」と聞かれたそうです。
クライアントに対して「あなたの会社はこれこれ、こういう課題を抱えている。だから我々は、こうすべきだと考える」とアイデアを提供するのがコンサルタントの仕事ですから、社内でも常に「なぜ?」「どうして?」「なんのために?」とお互いに聞き合っているということなのでしょう。
そしていま働いている糸井重里事務所では、「それ、本当に面白いと思ってる?」という質問が、社員の間で合言葉のようになっているとのこと。糸井重里事務所にとって一番大切なのは、コンテンツが「本当に面白いかどうか」、ということなのですね。
会社が大切にしている「価値観」が、どの企業でも質問に表れていると知って、驚いたものでした。
組織の中でよく使われている質問は、その集団の「本質」を表します。
トップが「売上はどうなっている?」と社員に質問していれば、なによりも売上を重視する企業風土が育まれていきます。「顧客は満足しているか?」という質問をし続けていれば、顧客志向の会社となるでしょう。
たとえ業種・業態・規模が同じであっても、会社によってぜんぜん企業風土が違うのは、そこで交わされている質問が違うからなのです。
つまり、組織の風土を変えたいと思うなら、「質問を変える」ことが非常に有効だということです。とくに会社の場合、もっとも強く社員に影響を与えるのは社長です。社長が口癖のように言っている質問を変えれば、自然と役員や社員の質問も変わっていきます。
手に入れたい風土に向かうための質問を作り、お互いにその質問を繰り返す。そうすれば、組織全体が無理なくそちらの方向に進んでいくのです。