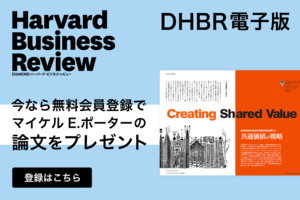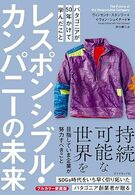──第26回の記事:現代の経営学で不可欠な「組織の経済学」(連載第26回)
──前々回の記事:なぜ「アドバース・セレクション」を理解することがビジネスにおいて重要なのか(連載第27回)
──前回の記事:普段何気なく取っているビジネス行動を、理論の視点から見直そう(連載第28回)
情報の非対称性はチャンスになりうる
経営学で主張される重要なポイントを紹介しよう。ここまで筆者は、情報の非対称性を「問題」として、ネガティブに扱ってきた。しかし情報の非対称性が常に望ましくないかというと、必ずしもそうとも限らないのだ。
先に紹介したカプロン=シェンのSMJ論文に戻ろう。同論文は、企業買収において、非上場企業と上場企業のどちらが買収されやすいかを分析したものだった。実はこれに加えて、カプロンたちは(買収企業の株価変化で計算した)買収パフォーマンスも統計分析している。その結果、「上場企業よりも非上場企業を対象に買収した方が、買収パフォーマンスが高まる」という結果を得ているのだ。
これは興味深い結果ではないだろうか。いままでの議論から言えば、非上場企業は情報の非対称性が高いのだから、それを買収したらパフォーマンスは悪くなると考えるのが自然だからだ。なぜこのような結果が得られるのだろうか。
上場企業から考えよう。上場企業は一般に(非上場企業よりも)情報が公開されている。ポイントは、これが他企業・投資家・メディア・顧客など、すべての外部ステークホルダーに公開されていることだ。逆に言えば、「この情報は外部の誰でも知っているのだから、稀少価値がない」ともいえる。仮にある企業がこの上場企業を買収しても、そこには誰もが知らないような稀少で価値がある情報はほとんど残っていないことになる。
他方で非上場企業の情報は、外部の誰もがよくわからない。しかし逆に言えば、もし何らかの理由で、ある企業だけがその非上場企業内部の私的情報を評価できるなら、その企業は非上場企業の私的情報を独占していることになる。稀少で価値ある情報だ。結果、他企業に先駆けて、その非上場企業を「買い」と判断できる可能性がある。
この考えより、カプロン=シェンは以下のように論理立てた。まず他の条件を一定とすれば、非上場企業は情報の非対称性が高いから、上場企業と比べて買収ターゲットとして望ましくない。しかし、ある企業Aがそれでも非上場企業を買収したということは、企業Aはその非上場企業や関連業界への「目利き力」が他社より高く、その本当の価値を見抜いたことになる。したがって企業Aは、価値を見抜けなかった他社を出し抜いて、非上場企業の経営資源を独占できる。
他方、上場企業の情報の多くは誰にでも公開されているため、そのような企業を買収しても、ライバルを出し抜く「上澄み効果」は薄い。したがって、目利きによって非上場企業を買収できれば、上場企業の買収に比べてパフォーマンスが高まるという結果になるのだ(※1)。
すなわち、情報の非対称性は実はチャンスでもあるのだ。ある企業の情報の非対称性が高いということは、「その企業の私的情報は外部の誰にもわからない」ということだ。しかし逆にその理由で、自社だけがその企業の私的情報を見抜く「目利き」ができれば、その情報はむしろ価値があって稀少なものとなり、ライバルを出し抜くチャンスになる。