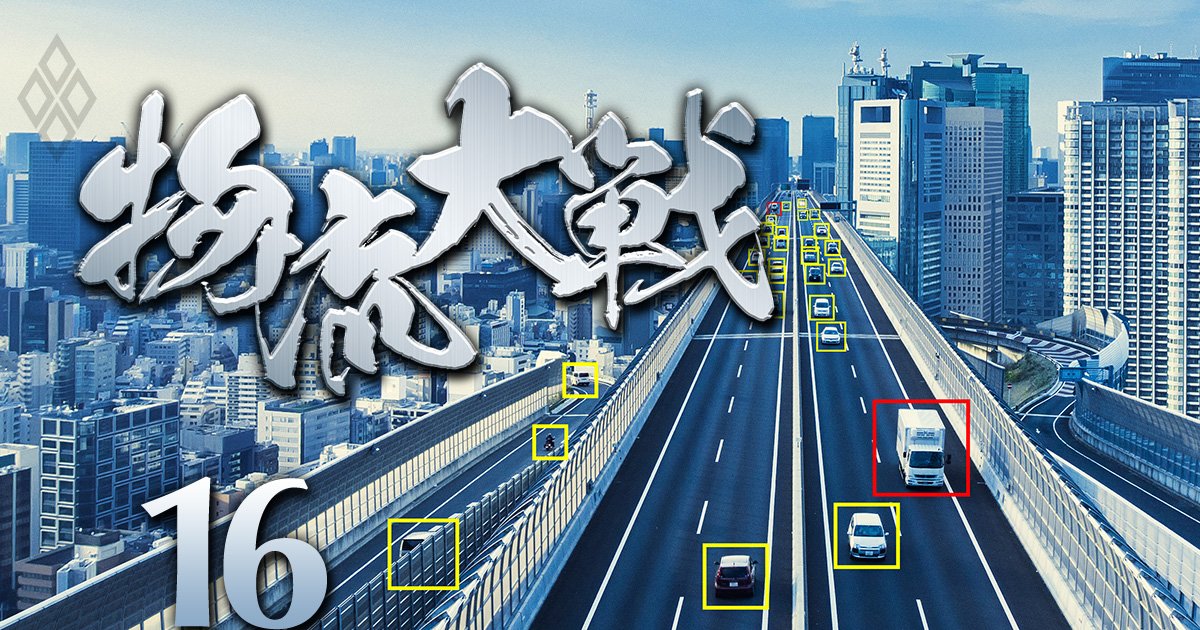孤独の中で不安におびえる若手裁判官たち
「震え上がった。宮本さんはどうなるのか、そして自分は大阪地裁でやりすぎたと思った。左遷されるのか不安で、仕方がなかった」(井垣康宏氏)
東京高裁や大阪高裁などの大規模庁と異なり、裁判所支部は一人での勤務だ。ドラマの寅子たちのように議論できる仲間がいるならいいが、今と違って通信手段も整っておらず、孤独の中で不安はつのるばかり。最高裁の切り崩しはこのような状況で効いていったのだ。若き井垣判事補は、日曜日ごとに延岡から3時間以上かけて九州山地を横断する長距離バスに乗り、熊本の宮本判事補に会いに行った。
「バスの窓かまちにカップ酒をずらりと並べて、それを飲みながら熊本に向かった。飲まずにはいられなかった」(井垣氏)。妻の一子(かずこ)さんも「家でも、よくぼやきながら飲んでいました」と回想する。
ドラマでは、家庭裁判所に異動した朋一が、裁判官を辞めると寅子と航一に告げる。朋一の妻から「自分は(悩む朋一の)何の支えにもなれない」と離婚を切り出されたと告白する(124回)が、似たエピソードがあったのだと一子さんは話す。「青法協を辞めてほしいあまりに、病気になった奥さんがいるんです」。一子さんは、夫に「お前は病気にならへんのか」と尋ねられてそのことを知った。
 退官後、自宅で鍋を囲む井垣康弘さん(右)と妻の一子さん
退官後、自宅で鍋を囲む井垣康弘さん(右)と妻の一子さん
宮本判事補は1971(昭和46)年、再任されなかった。