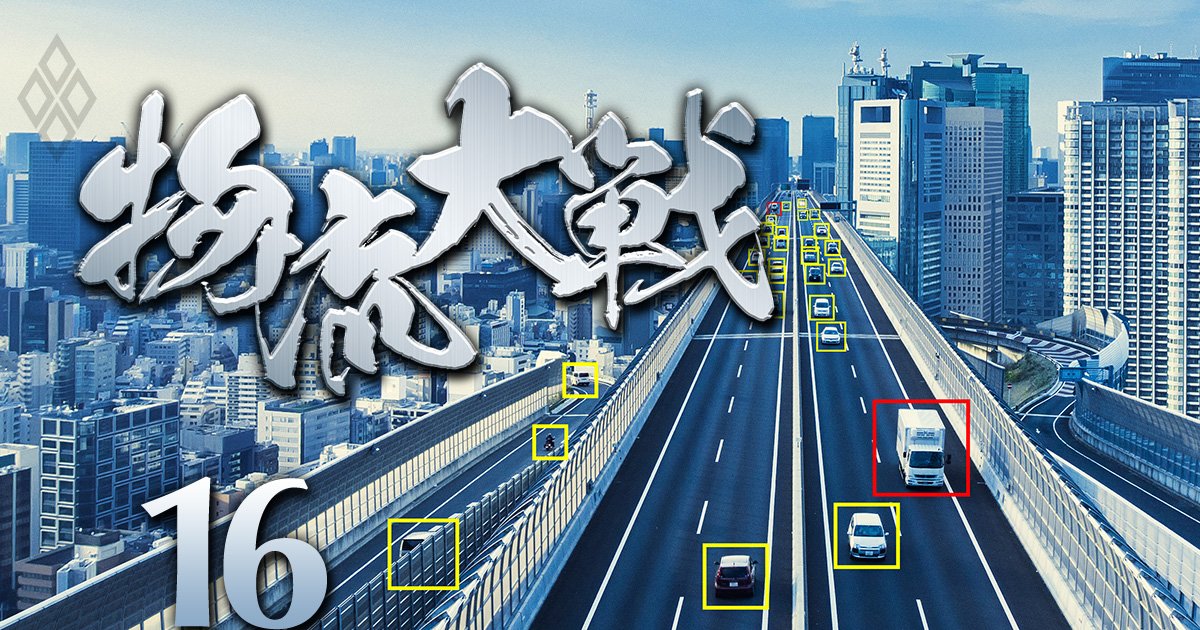では、井垣氏の場合はどうだったのか。
1967年~大阪地裁判事補、70年~宮崎家地裁延岡支部判事補、73年~前橋地家裁判事補、76年~大阪地裁判事補、77年大阪地裁判事(再任されて判事補から判事に)、79年松山地家裁大洲支部判事、83年岡山地家裁津山支部判事、88年福岡家地裁判事(家裁担当)、93年大阪家地裁岸和田支部判事(家裁担当)、97年神戸家裁判事、2005年定年。
見事なまでの左遷に次ぐ左遷人事である。井垣氏は刑事裁判官を志していたが、前橋地裁以外は徹底的に避けられて、その希望がかなえられることはなかった。
裁判官統制は、同僚による差別で完成した
苛烈なのは最高裁事務総局だけではなかった。「同僚裁判官による差別」である。如月会、裁判官懇話会参加者は、他の裁判官から後ろ指を指され続けてきた。「彼らは能力が低い」。
裁判官は日本で最も難しい国家試験である司法試験を突破するだけでなく、その成績優秀者でなければ選抜されない。総じて彼らはプライドが高い。最高裁はそこを利用した。1999(平成11)年、如月会・裁判官懇話会参加者が、裁判官制度を中心にした司法改革を目指し、司法改革の必要性を広く社会に訴えるために初めて社会に顔と名前を明らかにして「日本裁判官ネットワーク」を発足させた時も、同じような話が何度も出てきた。「ブルー・パージ」において、この同僚差別が効いた――これこそが、石田和外が始め、最高裁事務総局が長く続けた、お互いを疑心暗鬼にさせる裁判官統制のやり口だった。
「暴力は、思考を停止させる」という山田よね(土居志央梨)の言葉(122回)は、ブルー・パージにもあてはまるのだ。これは暴力である。
しかし、実際にそうやって「くさされている」裁判官たちに会ってみれば、彼らは実直に裁判に向かい合う、優秀な裁判官だった。例えば安原浩氏(故人)のように論文を何本も書く刑事裁判の理論的リーダーや、浅見宣義氏(現在は退官し、滋賀県・長浜市長)のように、最高裁事務総局からも実力に一目置かれているのが明らかな若き裁判官もいた。
だが、「裁判官ネットワーク」にも入っていた井垣氏は、よく言えばそこでもひときわ異彩を放つ存在であり、悪く言えば、そこでも浮いていた。