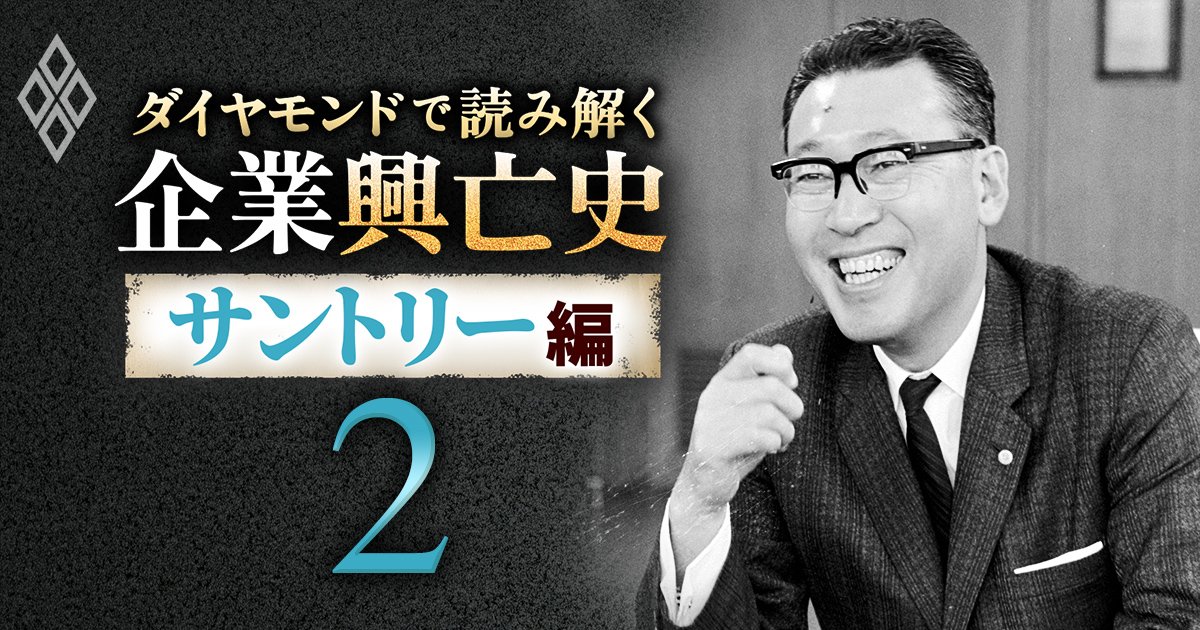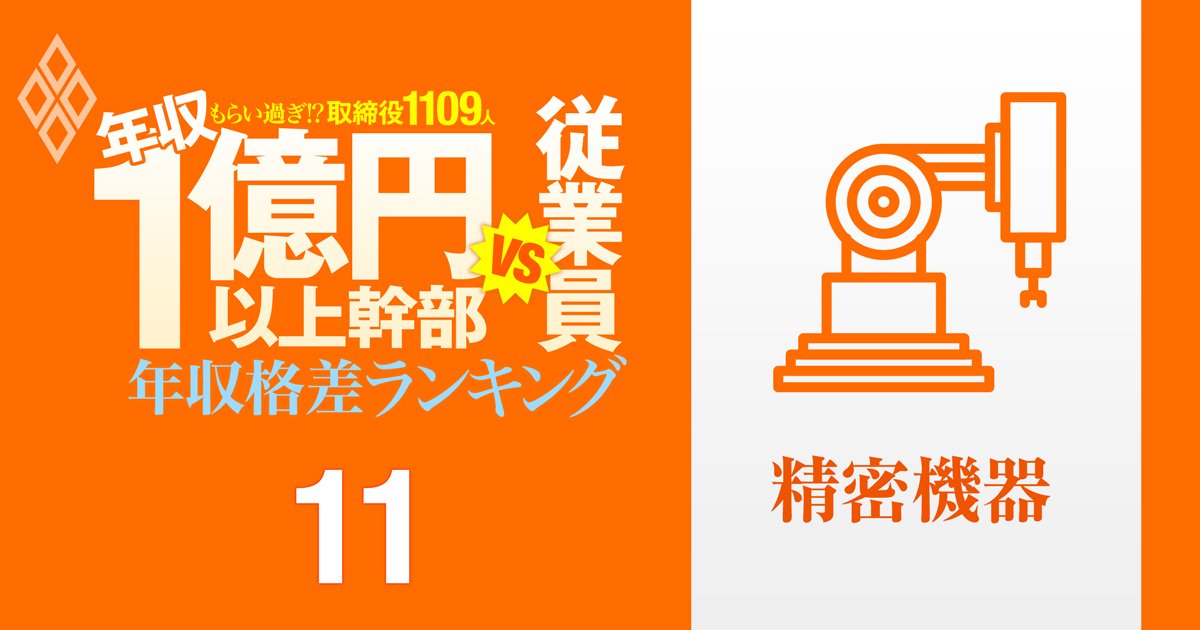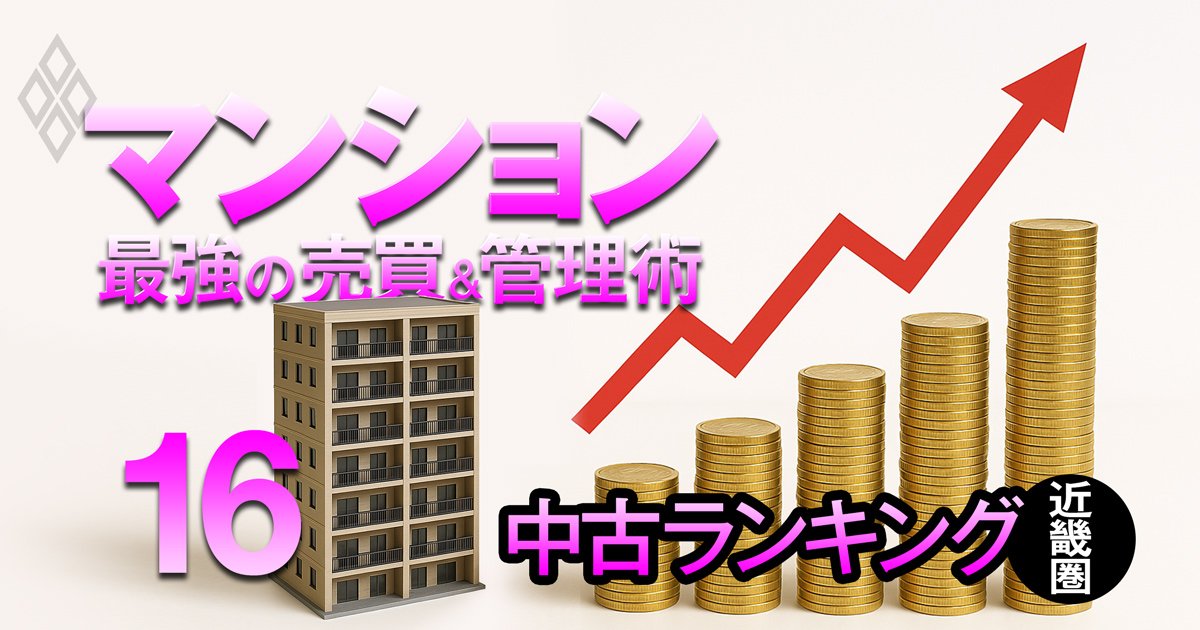この「チャンピオン制」という出来レースによって、本来の適正価格よりも高い金額で工事契約が結ばれることになる。その水増しされた費用の一部が、管理組合には知らされないまま、受注を差配した設計コンサルタントや関係者に「バックマージン」として支払われている、という構図だ。
バックマージンの額は、総工事費の10%から、悪質な場合には20%にも達するとも言われる。つまり、管理組合が支払った工事費の一部が、本来の工事目的以外に充当されている可能性も考えられるのだ。相場が1億円の工事が、15%割高な1億1500万円で契約された場合、差額の1500万円が、キックバックの原資となっている…といった例である。
さらに、この癒着構造を隠蔽(いんぺい)する巧妙な手口の一つに、設計コンサルタントが管理組合に対し、相場では考えられないほど安いコンサルティング費用(設計監理料)を提示するというものがある。
一見すると、管理組合にとっては費用を大幅に節約できる魅力的な提案に映るだろう。しかしその裏には、工事費を割高に設定することで得られる多額のバックマージンで、コンサルタントは十分に利益を確保できるという計算が隠れている場合も少なくない。表面的な費用だけを見ると、むしろ良心的にさえ見えるケースもあるため、その裏にある癒着や不当な費用の流れは見過ごされやすくなってしまう。これが問題の発覚を困難にしているとも言えるのだ。
加えて、近年における資材価格や人件費の上昇は、大規模修繕工事の費用そのものを大きく押し上げているのが実情である。管理組合が計画的に積み立ててきた修繕積立金だけでは必要な費用を賄いきれず、住宅金融支援機構をはじめとする外部機関からの借り入れに踏み切るケースも増加している。こうした厳しい財政状況が、癒着による不当な費用上乗せのリスクをより一層深刻なものとしているのである。
不正の兆候?
チェックすべき業者選定の「シグナル」
建築や業界慣行に関する専門的な知見がなければ、管理組合がこの巧妙に仕組まれた癒着構造を見抜くことは簡単ではない。見抜くことが難しいからこそ、選定プロセスの中に現れる具体的な「シグナル」に目を向けることが大切になってくる。
例えば、設計コンサルティングの費用が相場と比較して異常に安いにもかかわらず、提示される工事見積総額が不自然に高額であったり、修繕積立金の残高に合わせたかのようにピッタリだったりする場合は警戒が必要だ。
また、コンサルタントが紹介した特定の業者以外に応募がなかったり、他の参加業者が明らかに受注に消極的な態度を示したりする場合も、水面下での調整が疑われる。
見積もり合わせの結果、特定の1社だけが突出して安い(もしくは予定価格に近い)場合や、他の業者が横並びで高額な見積もりを提示している状況は、もしかすると出来レースの兆候かもしれない。
これらのシグナルに気づくことが、不正を見抜くきっかけともなり得る。