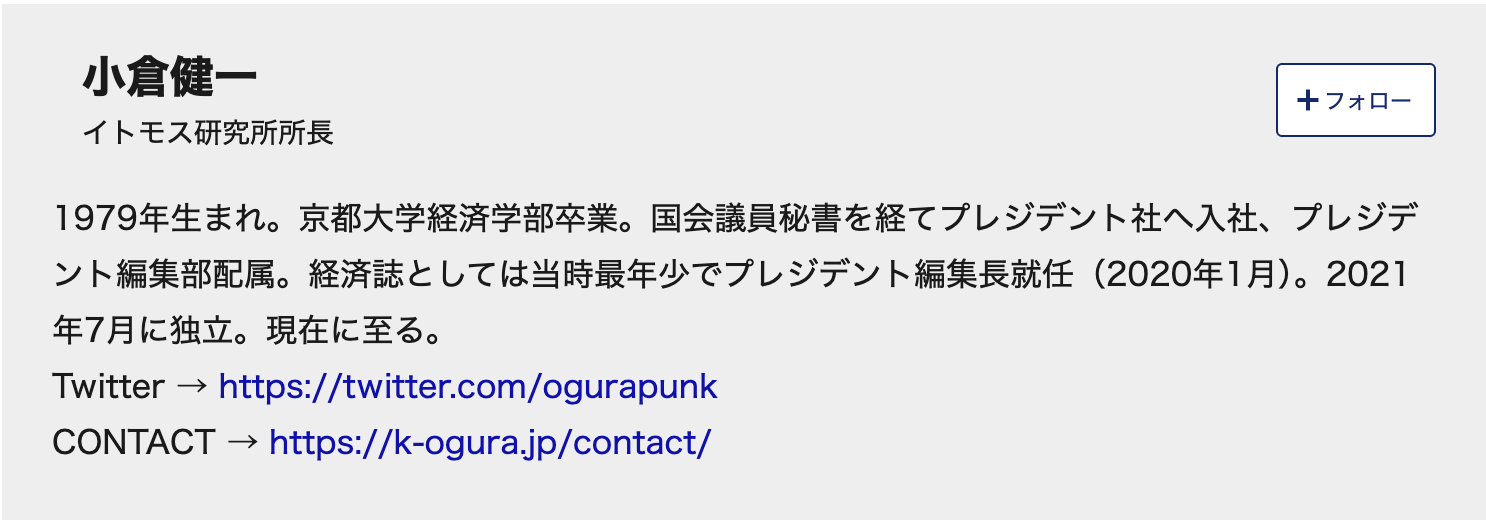店の名前がすべてを決める!なぜ「名代」と名付けたか
店名が果たす機能は多岐にわたる。
第1に、他店と自店を区別するための識別機能がある。第2に、業態やコンセプト、品質、価格帯といった情報を顧客に伝達する機能を持つ。第3に、ブランドの個性や世界観を形成し、顧客に特定のイメージを抱かせる機能がある。第4に、顧客の記憶に残りやすく、口コミを促進する機能も重要だ。
優れた店名は、これら複数の機能を同時に満たしている。ネーミングを決定する際には、事業戦略全体との整合性を考慮することが不可欠である。
ターゲットとする顧客層は誰か。どのような価値を提供したいのか。コンセプトと名前が一貫していなければ、顧客は混乱し、ブランドへの信頼は損なわれる。単に響きがおしゃれであるとか、奇抜で目立つといった理由だけで名前を選ぶべきではない。
事業の核となる哲学を凝縮し、的確な言葉で表現する作業が求められる。現代では、商標登録の可否や、ウェブサイトのドメインが取得できるかといった実務的な側面も無視できない。
店名は、あらゆる顧客接点の出発点となる。看板、メニュー、ウェブサイト、SNSアカウント、従業員のユニフォームに至るまで、すべてのコミュニケーションが店名という一つの中心点から展開されていく。中心点があいまいであれば、ブランドのメッセージは拡散し、力は弱まってしまう。
結論として、店名は単なる呼び名ではない。それは事業の成功を大きく左右する、極めて重要な戦略的要素である。消費者は意識的、あるいは無意識的に、店名から多くの情報を読み解き、期待を形成し、最終的な購買行動を決定している。
事業者は、自らの店が提供する価値をもっとも的確に表現する言葉を、慎重に選び抜く必要がある。その選択が、事業の未来を照らす光とも、その道を閉ざす影ともなり得るからだ。
最後に、冒頭で触れた「名代 富士そば」の「名代」の読み方について種明かしをしたい。この言葉は「なだい」と読む。みょうだい、めいだいではない。
創業者の丹道夫会長が「富士山のように日本一立派で有名な立ち食いそば店にしたい」という強い思いを込めて、1972年頃に屋号を定めた。評判が高い、名高いという意味を持つ「なだい」という言葉に、日本一の象徴である富士山を組み合わせたのだ。
創業者の壮大な志が込められた、本来は非常に格調高い名前である。読み方と由来を知ることで、店名に対する印象は大きく変わるだろう。しかし、多くの人が知らない。
ネーミングが持つポテンシャルを顧客に完全に伝えることの難しさ、そして奥深さを改めて示している。