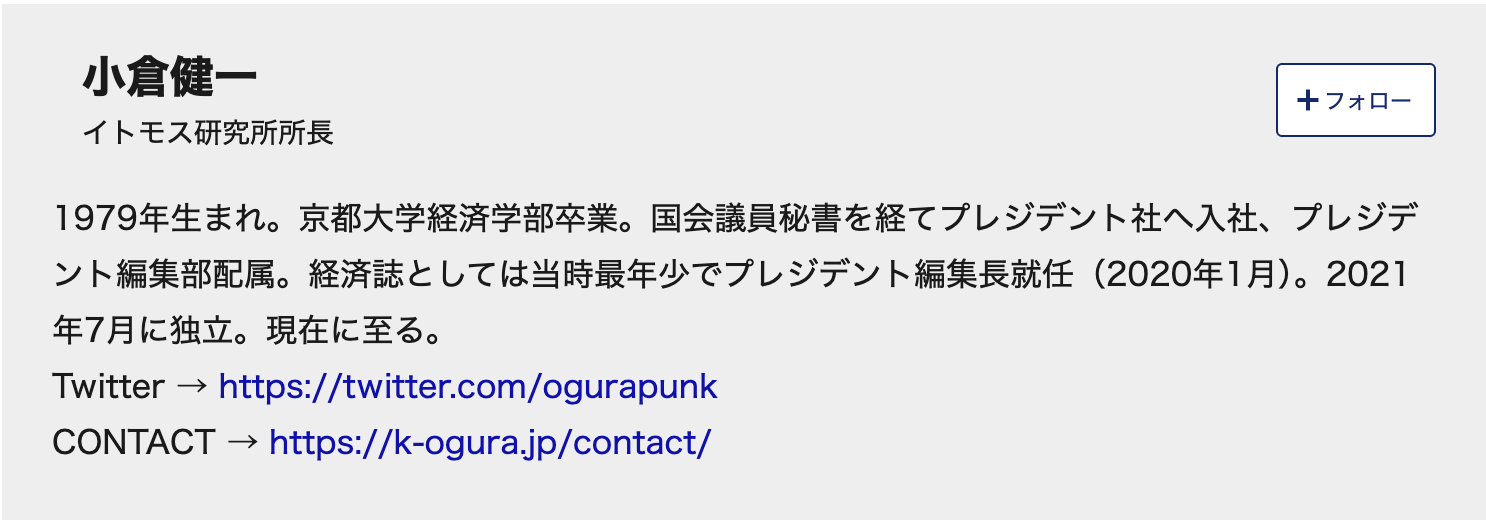「自分の考えを超えてくる人材」が必要
命令が一方向にしか流れない組織では、情報の流れも一方向になる。現場で起きている問題や新しい発想は、上司や経営者には届かない。
その状況をカーンらはこう描写する。
“Authoritarian leadership produces unfavourable attitudes, conflicts, distortions, and interaction with security guards, as well as high turnover, poor performance, absenteeism, and a negative impact on job quality.”
(権威主義的リーダーシップは、好ましくない態度、対立、歪曲、警備員との衝突を生み出すほか、高い離職率、低い業績、欠勤、職務の質に対する負の影響ももたらす)
この論文はかなり専門的で学術的な文献だが、読めば読むほど、柳井氏の実感と重なるように思う。優秀な人材ほど「頭脳」として働きたい。命令を守るだけの手足ではいたくない。もしその機会がなければ、彼らは去っていく。
ユニクロが成長を続ける中で、柳井氏はようやく「自分の思い通りに動く人材」ではなく、「自分の考えを超えてくる人材」を必要としていることに気づいたようだ。
こうしたユニクロの苦悩を研究は理論的に裏付ける。
“Employee and leader collaboration and communication improve project performance significantly because projects are both transitory and complex.”
(従業員とリーダーの協働と対話はプロジェクト成果を大きく高める。プロジェクトは一時的で複雑なものであり、信頼と意見交換が不可欠である)
つまり、組織が成長し、課題が複雑になるほど、リーダーの「一方的な指令」よりも「双方向の対話」が成果を左右するということである。
柳井氏が転機を迎えたのは、まさにその「対話の必要性」を痛感したときだった。かつてのユニクロには時間の余裕がなかった。命令して動かすしかなかった。
しかし、危機を乗り越えたあとの停滞こそが、経営者を鈍らせる。トップダウンの成功体験が、そのまま衰退の種になる。
命令は速い。だが、人はゆっくりしか育たない。現在の柳井氏に対しても「依然としてトップダウンで独裁的だ」という批判もあるだろう。
だが、放任でも独裁でもなく、その間で悩み抜くという意味で、柳井氏は組織が抱える普遍的な課題と真摯に向き合ってきた経営者だと言えるのではないか。