リーマンショック以降、低迷を続けていたリート市場が「怒涛の急回復」を遂げている。
2008年10月、ニューシティレジデンスが経営破綻して以降、東証リート指数は1000ポイント以下で低迷していたが、10年10月以降急上昇。1月18日現在の終値は1118ポイントまで上昇した。これは、08年10月のリーマンショック直前の水準である。
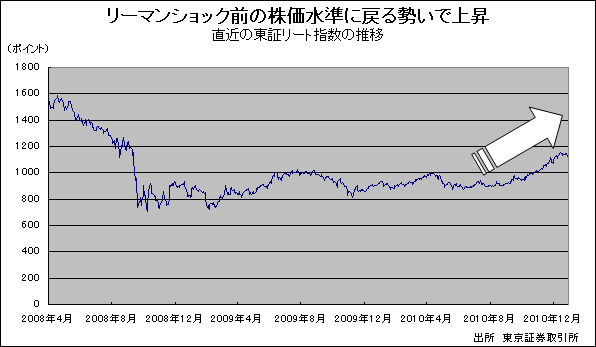
言うまでもなく、そのきっかけは「日銀介入」だ。日銀は10年10月、景気対策として、500億円を上限としリートを買い入れると発表。12月26日には22億円の買い入れを行った。
これを見て動いたのが国内金融機関だ。円高で為替リスクのある金融商品から撤退し、運用先を失っていた国内の投資資金が、現在利回り5%台を確保できる数少ない金融商品であるリートに集中したのだ。
「もともとリート投資の再開を目論んでいたものの、地銀は一度撤退した投資先に復帰しかねていた。それが、日銀の買い入れで信用が担保されたとして一気に動いた」(石澤卓史・みずほ証券チーフ不動産アナリスト)。みずほ投信投資顧問、日興アセットマネジメントなどの投資顧問会社は、年末年始にかけ相次ぎリートの大量保有報告書を提出。さらに、リートを組み入れた投資信託の組成も相次いでいる。9月末時点でJリート投信の残高は4000億円だったが、1月には7000億円にまで増加する見込みだ。3ヵ月で75%増加する勘定だ。
ただし、この回復は「リーマンショック以降、解散価値以下で不当にディスカウントされてきたリートが、ようやく正常化した」(鳥井裕史・日興コーディアル証券アナリスト)だけ、という面が否めない。ネット・アセット・バリュー(リートの不動産ポートフォリオの資産価値から負債を引いたもの)から換算した、市場全体の解散価格は1080ポイント。現在はようやく“解散価値”を超えた計算になる。
市況の回復を見込み、年始早々、三井不動産系の日本ビルファンドや、積水ハウス系のジャパンエクセレントが増資と物件取得を行った。今後、リートが成長するには新たな収益不動産を取得し、ポートフォリオの収益性を高めることが欠かせないからだ。
もっとも、リートの運用資産の大半を占めるオフィスビル市況は、賃料の低下に歯止めがかからず、軟調を脱し切れていない。今後、増資ができるリートとそうでないリートの格差は広がるだろう。「リートが取得を狙うような優良物件の価格がなかなか下がらないため、結果的にスポンサー(親会社)の保有物件を取得するしかない状況」(石澤アナリスト)が続いているからだ。
リートは本来、スポンサーからは切り離されて運用され、「親の実力」とは関係なく評価されるべきものである。だが、市場の成長の波に乗れるかどうかは「親次第」という皮肉な状況は、金融危機時となんら変わっていない。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 鈴木洋子)




