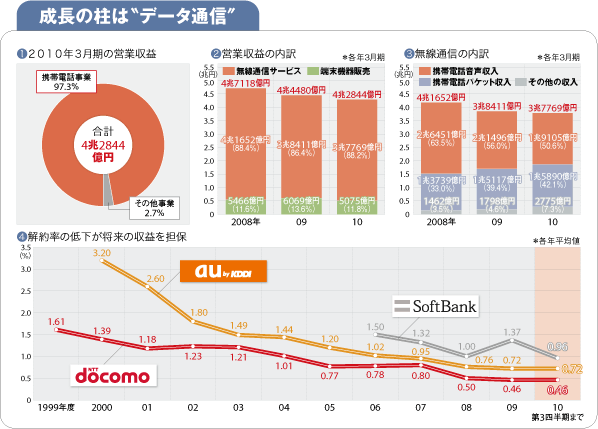契約者のシェアが漸減し、約49%になったとはいえ、約5700万人と国内最大のユーザー数を抱えるNTTドコモ。このところのスマートフォンシフトで、新たな経営課題も浮かび上がってきた。
NTTドコモは、1年間で4回、スマートフォンの国内販売台数の予測を上方修正した。
2010年4月の期末決算発表時は、「年間で100万台」だったが、6ヵ月後にiPhone対抗商品として投入したGalaxy Sの発表時には、130万台になった。
それが、11年1月の第3四半期決算発表時に、通期の販売目標を250万台とほぼ倍増させた。そして、山田隆持社長は「来期(11年度)には600万台前後の販売を見込む」と、さらに2倍以上に増やすと明かした。この比率は、ドコモが1年間に販売する携帯電話の約3分の1がスマートフォンになるという計算である。
現在、NTTグループの連結営業利益の75%を稼ぎ出すドコモは、売上高に相当する営業収益の97.3%を携帯電話事業に依存している(図(1))。そして、収益の88.2%が無線通信サービスとなっている(図(2))。
09年度の業績は、折からの競争の激化による値下げ合戦によって音声収入が下がったこと、07年秋から携帯電話の販売方法を新ビジネスモデルに変更したことの影響で、3年連続の減収となった。
とりわけ、後者では、端末代金と通信料金が混在してわかりにくかった価格を明確に分離したことで、一時的に端末代金が上がった。これでユーザーは、一定期間同じ端末を使い続けるように変わり、端末の売り上げも下がった。その一方で、端末を売るために必要だった販売奨励金の支出を大幅に抑えることができ、ネットワーク関連設備のコスト削減なども進めたことで営業費用を抑え、営業利益の段階で増益を確保した。
減収の最大の原因は、前述したとおり音声収入の減少だ。収益に大きく影響する音声収入の割合が下がり続け、反対にパケット(データ通信)収入の割合が伸びている(図(3))。これは、全体の「1契約当たりの月間平均収入」の下降を食い止めるために、ドコモ側が意図してインターネット系の各種サービスで収益源となるデータ通信の拡大に注力してきたこともあるが、無線通信でネット上の各種サービスを楽しむスマートフォンやタブレット端末の需要が伸びている潮目の変化もある。
ただし、このスマートフォンやタブレット端末などは、ドコモに対して、ビジネスモデルの再編を突きつける存在だ。1999年の登場以来、日本の携帯電話のスタンダードになっているネット端末のiモードは、通信ネットワークから端末、その上で動くアプリケーションまでを、すべてドコモが垂直統合で完全に管理できた。
だが、現在、急速に伸びているスマートフォンなどは、そもそも世界規模でサービスを水平展開(協働)することを目指して開発されているグローバル端末が多く、かつてのように1社単独でコントロールすることはできない。