人類は、常に「新しさ」や「成長」を追求してきた。それが進歩であり、また進化であるといわれてきた。そしてビジネスの世界では、もっぱら「効率」が重視されてきた。たとえば、コストダウン、規模や量の拡大、スピード化、改善やイノベーションであり、また21世紀を前後して、デジタル化、可視化、自動化などが台頭してきた。
もちろん悪ではない。ただし、その代償として、地球環境の破壊、人間性や社会関係資本(ソーシャルキャピタル)の希薄化、全体性(ホリスティック)やコミュニティシップなどの喪失が招かれた。幸いなことに、こうした失われたものを取り戻そう、回復させようという動きが、遅ればせながら世界各地で起こっている。
そしてもう一つ、知らずしらずのうちに失われつつあり、デジタル時代だからこそ立ち止まって取り戻すべきものがある。そう、「深く考える」という思考のスタミナである。その必要性は、昔から言われ続けてきたことでもある。名経営者といわれた企業人たちの言葉を温(たず)ねてみよう。
「考えよ」(トーマス・ワトソン・シニア)
「事業成功の神髄は、と問われたならば、何ごとも軽率に着手しないことと答えます。着手するまでに十分考え、いわゆるバカの念押しをやってみることが大切です」(小林一三)
「一方はこれで十分だと考えるが、もう一方はまだ足りないかもしれないと考える。そうしたいわば紙一枚の差が、大きな成果の違いを生む」(松下幸之助)
「四六時中考える習慣をつけなさい」(安藤百福)
「何をやるにしても考えて考え抜く。それが私の一生である」(出光佐三)
「考えて、考えて、考え抜く」(小倉昌男)
デジタル化や自動化が加速している現在、元AI研究者の川上浩司氏も、同じく「深く考える」「思考を深める」ことの重要性を訴える。いわく「こうした便利なツールを当たり前に使うようになったことで、人々の思考がパターン化・効率化され、浅い思考が習い性になってはいまいか、深く考えることはまさしく人間ならではの営みであり、他に代えがたい強みではないのか」。
川上氏は現在、「不便益」という視点から、AIをはじめとするさまざまな人工システム、バリューエンジニアリング、インターフェースやコミュニケーションなどのあるべき姿について研究しており、ウェブベースでの研究者コミュニティ「不便益システム研究所」を主宰したり、一般公開講座「京大変人講座」で不便益をテーマとした講義を担当したりと、この概念の普及・啓蒙に努めている。
川上氏によれば、この不便益を意識的に取り入れる中で、深い思考へと導かれていく可能性があるという。本インタビューでは、思考の効率化やパターン化をいったん保留して深い思考を心がける意義、また不便益の視点の必要性、不便益/不便害と便利益/便利害との相関性について説明を受けながら、デジタル・AI時代における「考えるスタミナ」について問い直す。
効率化や便利さが
「深く考える」力を衰えさせる
――編集部(以下略):デジタル技術、特にAIによってますます楽になり、人間に残されるのは、創造性を活かしたり、社会性が求められたりする仕事であり、むしろそれは人間にとって幸せなことだ、という意見があります。
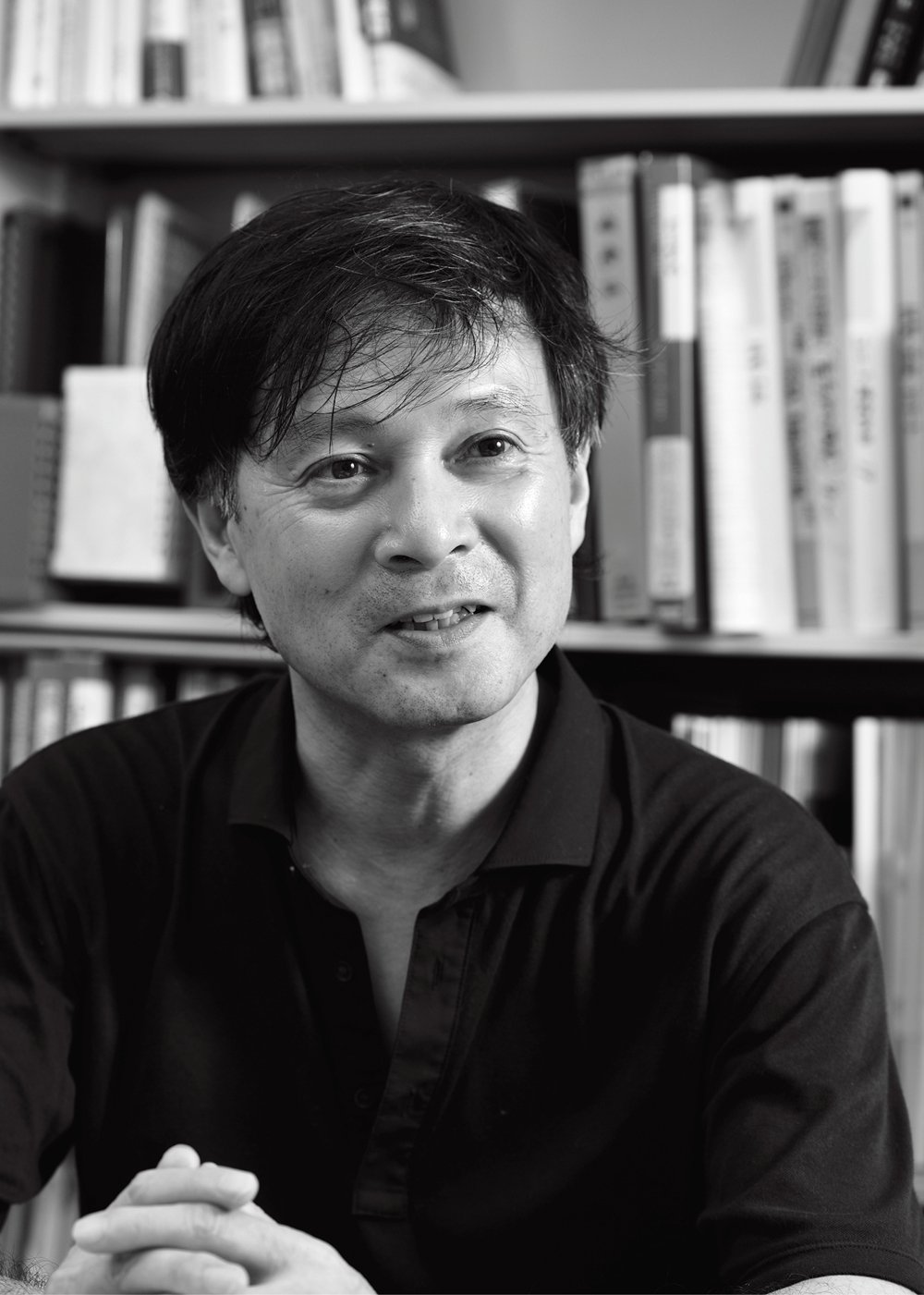
川上 浩司 HIROSHI KAWAKAMI
川上(以下略):それほど単純ではないと思いますよ。むしろ眉に唾しています(笑)。
人類の歴史をひも解くまでもなく、私たちは「もっと早く、もっと便利に」と効率を追求することで発展し、豊かさを得てきました。ですが、こうした早さや便利さを享受することで、なおざりにされつつあることがあります。そう「深く考える」という営みです。
私はそもそも工学畑の出身です。若い頃は、すこぶる素直に「便利なものさえつくっていればいい」という工学の宗教を信じておりまして、しかも究極の便利さをもたらすかもしれないAIの研究者でした。
コンピュータ科学を含めて工学の世界では、「評価関数」を設定しないと研究が進みません。たとえば、新幹線の先端の形状を決める際、空気抵抗の値を評価尺度の一つとして、その最小化を目指すわけですが、その値を出す関数を評価関数といいます。
このケースは比較的簡単ですが、もっと複雑な工作物になると、どの範囲の数値を対象にした関数をつくるか、ということさえ問題になります。こうした一筋縄ではいかない場合でも、多くの工学者や科学者は、変化は直線的である、つまり「線形近似」(単純な一次関数に置き換えること)ができる部分を組み合わせて評価関数を設定しがちです。
たとえばH2Oという物質は、温度によって水(液体)から水蒸気(気体)へ、あるいは氷(固体)へと変化します。いわゆる相転移です。この相転移を正しく理解するには、熱して液体の温度が一直線に上昇する過程だけではなく、固体や気体に変わる瞬間についても観察・測定しなければなりません。
H2Oがこのように相転移を起こすことを知っているから、H2Oは線形で変化しないと納得できるわけですが、えてして私たちは、予想できない世界、知らない世界については、線形で変化していくと期待してしまう傾向があるのです。実際、工学の世界に限らず、皆さんの身近なところにも、こうした線形思考の産物がたくさんあるはずです。









