高齢社会となり、また価値観の多様化が見られるなかで、葬儀のあり方も変化している。家族葬や自然葬、無宗教でのお別れの会や、花で飾られたオリジナル祭壇等々。その人の生きてきた道にふさわしい最後の儀式として、故人や家族のこだわりが反映されるようになっている。死に関して無自覚になったといわれる現代人にとって、葬儀とはどうあるべきか? 今あらためて、現代のとむらいや供養のかたちを考えてみたい。
現代は、死について無自覚な〝死を忘れた文化〟が浸透し、共同体のなかの絆が失われ、葬送儀礼は急速に変化しつつある。
そのなかで、現代人は死とどのように向き合い、どのように生きればよいのか。
新しい学問である「死生学」に取り組む、東京大学の島薗進教授に、日本人の死生観や葬儀のあり方、理想的な〝とむらい〟への思いを聞いた。
「死生学」とは、簡単にいうと、死ぬまでの生き方を考える、新しい学問分野です。具体的には、まず医療との接点で求められています。現代の医療は科学一辺倒で、人の心に接するあり方を軽視してきた。死にゆく人々の残りの命を充実させる視点が欠けていた。そのため、死に直面した患者や家族、ケアにかかわる医療現場からのニーズが高まり、死生学の教育や研究が進められるようになったのです。
死に対して
無自覚になった
現代人
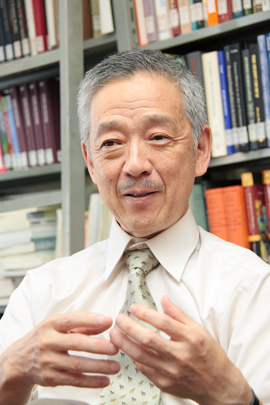 東京大学文学部・同大学院人文社会系研究科・死生学研究拠点 島薗 進教授
東京大学文学部・同大学院人文社会系研究科・死生学研究拠点 島薗 進教授1948年東京都生まれ。専門は宗教学。2002年から日本宗教学会長、グローバルCOEプログラム「死生学の展開と組織化」の初代拠点リーダーなどを務める。著書に『スピリチュアリティの興隆』『現代宗教の可能性』(いずれも岩波書店刊)、『いのちの始まりの生命倫理』(春秋社刊)ほか多数。
かつては死別の悲しみは、仲間のあいだで癒やしていたものでした。通夜にはたくさんの人たちが集まり、故人の話をして別れを惜しんだ。そのなかに家族が入れば、少しは気が紛れたものです。今は葬儀の簡略化が進んで、遺族が自分の心の中に死別の悲しみをため込んでしまうケースが増えてきました。そうした見送る側の心のケアをするグリーフワーク(悲嘆回復)も、また死生学の大切な役割の一つになっています。
なぜ今死生学が求められるのか。それは現代人が死について無自覚になっていることが背景にあると思います。かつてはお盆の行事や法事など、先祖(死者)との共生感を持つ生活習慣が、身の回りに色濃くありました。また無常観溢れる詩歌などを通じて、間接的に死というものを学んできたのです。
ですが、今はそうした間接的な学びがなくなりつつあります。逆に現代の死は、昔と比べて直接的に現れるようになってしまった。漫画とか映画には、あまりにも簡単に死が出てきます。ゆっくりと死を考えたり、死に親しんだりする間もなく、露骨に死が訪れてしまうのです。そのため、現実の死に直面すると、どうしていいかわからなくなってしまう。死と向き合うすべを見失っているので、途方に暮れてしまうのです。
かつて共同体の
〝絆〟が根底にあった葬儀
そもそも、家族や親族が集まって懇ろに死者を弔うという葬儀のあり方は、今から400年ほど前、江戸時代の初期に定着したものです。仏教が小さな村にまで入り込み、民衆の生活に近づいて、家の中にも仏壇ができた。
