記事一覧
米株式相場は昨年9~10月、今年2~3月に続く、半年に1度起きる程度の調整に見舞われた。過去の事例から全治2カ月とざっくり初期診断しつつ、まずは「売りが売りを呼ぶ」事態悪化のリスクに細心の注意を持って観察している。景気減速、インフレ、金利上昇、中国問題、資源高騰、ワクチンなどファンダメンタルズ(経済の基礎的諸条件)の外的要因以上に、実は、不安定な損益状況にある既存投資ポジションからの行動、つまり、相場自体の内的力学を重要視すべき場面である。

米国のシェール業者は来年、石油生産へ向けた投資を若干増やす見通しだが、生産量の大幅な増加にはつながりそうにない。

中国共産党はメディアに投資する民間資本を追い払う一方で、誤情報とみなすものへの取り締まりを実施している。

乳がん検診、マンモ+超音波の有効性は?
ピンクリボン月間だ。日本では40歳以上の女性に2年ごとの乳がん検診が推奨されている。コロナ禍で、検診機会を逃さないよう気をつけたい。乳がん検診ではマンモグラフィー(マンモ:乳房エックス線撮影)が使われるが、乳房を挟む「痛い」イメージが先行して敬遠されがち。最近は、マンモと痛みがない超音波検査を組み合わせる自治体が増えてきた。

情報共有ツール「Notion」を開発する米国のスタートアップ、Notion Labs。同社は10月13日に日本語化したNotionを公開した。創業者でCEOのIvan Zhao(アイバン・ザオ)氏とNotionの日本第1号社員である西勝清氏はDIAMOND SIGNALの独占取材に応じた。

#3
10月に緊急事態宣言が解除されたものの、ビールメーカーに楽観ムードはない。背景にあるのは、二つの「時限爆弾」の存在だ。コロナ禍は流通構造が抱えるリスクを一挙に顕在化させた。ビールメーカーが直面するのは売り上げ消滅と値下げドミノの悪夢だ。

コロナ禍からの企業業績の回復は、勝ち組と負け組の格差が拡大して「K字型」に引き裂かれていくという二極化の議論が強まっている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はサイバーエージェント、電通グループ、博報堂DYホールディングスの「広告」業界3社について解説する。

新型コロナウイルスの感染拡大は、不動産市場に短期から中長期のさまざまな影響を及ぼした。リモートワークの拡大一つ取っても、その波及の仕方はプラス、マイナスの両面があって画一的ではない。オフィス、物流、住宅、ホテルと資産タイプ別の今後の見通しを分析した。

コロナ禍からの企業業績の回復は、勝ち組と負け組の格差が拡大して「K字型」に引き裂かれていくという二極化の議論が強まっている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回は第一生命ホールディングス、かんぽ生命保険、T&Dホールディングスの「生命保険」業界3社について解説する。
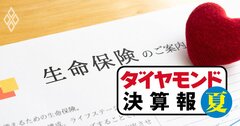
戦後最長となる8年9カ月にわたって財務省に君臨した麻生太郎前財務大臣。5年弱にわたって彼を追い続けた日本テレビ報道局の経済部デスクが、独特の「麻生節」に失言、官僚からの人気、そして実行した政策までを振り返り、戦後最長財務大臣が遺したものとはなんだったのかを考える。

今回は、日本を代表する名門電機メーカーである、パナソニックとソニーグループの決算書を見ていこう。昨今の報道では業績の明暗が語られることの多い2社だが、決算書にはどんな実態が表れているのか。それぞれの特徴を解説する。

第5回
今の時代、日本で自宅にいながらでも英語は話せるようになる。しかし、そうなるには、中学・高校時代の学習法からの転換が必要だ。今回は英語界の権威で東進ハイスクールのカリスマ英語教師として有名な安河内哲也先生に話を聞いた。

岸田新政権の「分配重視」の政策が効果を上げるためには、成功へのインセンティブを阻害しないことや雇用機会や投資成果の享受での公平さに配慮することが重要だ。

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が9月末で解除となり、飲食店などの営業時間は延長され、イベントなどの参加人数の制限も緩和されている。こうした制限措置の緩和により、経済活動の持ち直しへの期待も高まっている。宣言解除後の人出・人流の増加による成長率を押し上げ効果を試算し、しばらくは日本景気の高成長が続くことを示唆する一方で、2022年初め以降の景気弱含みリスクを指摘する。

いよいよ岸田内閣が本格始動しました。支持率の低さから低調な船出とする報道もありましたが、所信表明演説は今までの岸田氏のイメージよりもはるかに力強いもので、個人的には最後の「早く行きたければ、一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め」のフレーズはグッとくるものがありました。これぞ、日本人的であり、岸田的な良さなのだろうと感じました。

米主要企業の7-9月期(第3四半期)決算発表シーズンが幕を開ける。投資家はコスト上昇が今四半期以降の利益圧迫要因になるかどうかを見極めようとしている。

大統領には、巨額財政支出・コロナ・移民といった議論を呼ぶ問題で主導権を取り戻す機会がある。

最も生存率が低いがんといわれる、膵臓(すいぞう)がん。早期発見が困難であることも知られている。そうした中、大阪大学大学院医学系研究科の石井秀始特任教授とベンチャー企業、HIROTSUバイオサイエンスは共同研究を行い、世界初の線虫嗅覚によるがん検査を応用した早期膵がんの診断法で、従来の腫瘍マーカーによる検査よりも高い精度でがんの有無を診断できることが明らかになった。線虫検査には現在のがん検査、そして治療のあり方を大きく変える可能性がある。

近年、劇的に変わりつつある「食」の世界。今後、地球規模の人口爆発による食料の供給不足や、外食業界での人手不足の深刻化、さらに新型コロナウイルスの流行で、ますます先行き不透明な時代になっていくでしょう。こうした深刻な問題を解決すべく、日本をはじめ世界各国が臨んでいるのが、「フードテック」です。たとえば、培養肉や代替肉、スマート調理機器など、すでに実現しているものもあるのです。そこで今回は、大豆ミートをはじめとする“もどき食材”の事例について抜粋紹介します。

「健康経営」の落とし穴は?企業が忘れてはいけない3つのポイント
コロナ禍では、多くの企業が、事業所での感染対策はじめ、リモート勤務やワクチン接種などさまざまな取り組みを通して従業員の健康確保の重要性を再認識している。今後も「従業員の健康」をどのように守るかが各方面から問われることは間違いない。しかし、企業による「従業員の健康確保」は、法律や規制への対応に終始し、医師や保健師といった専門家に任せるだけといったケースも少なくない。産業医・労働衛生コンサルタントとして就労者の現場の声に精通し、ITを活用した健康管理クラウドサービスを提供する株式会社iCAREの山田洋太氏(代表取締役CEO)に、人事戦略としての「健康経営」の課題について話を聞いた。

