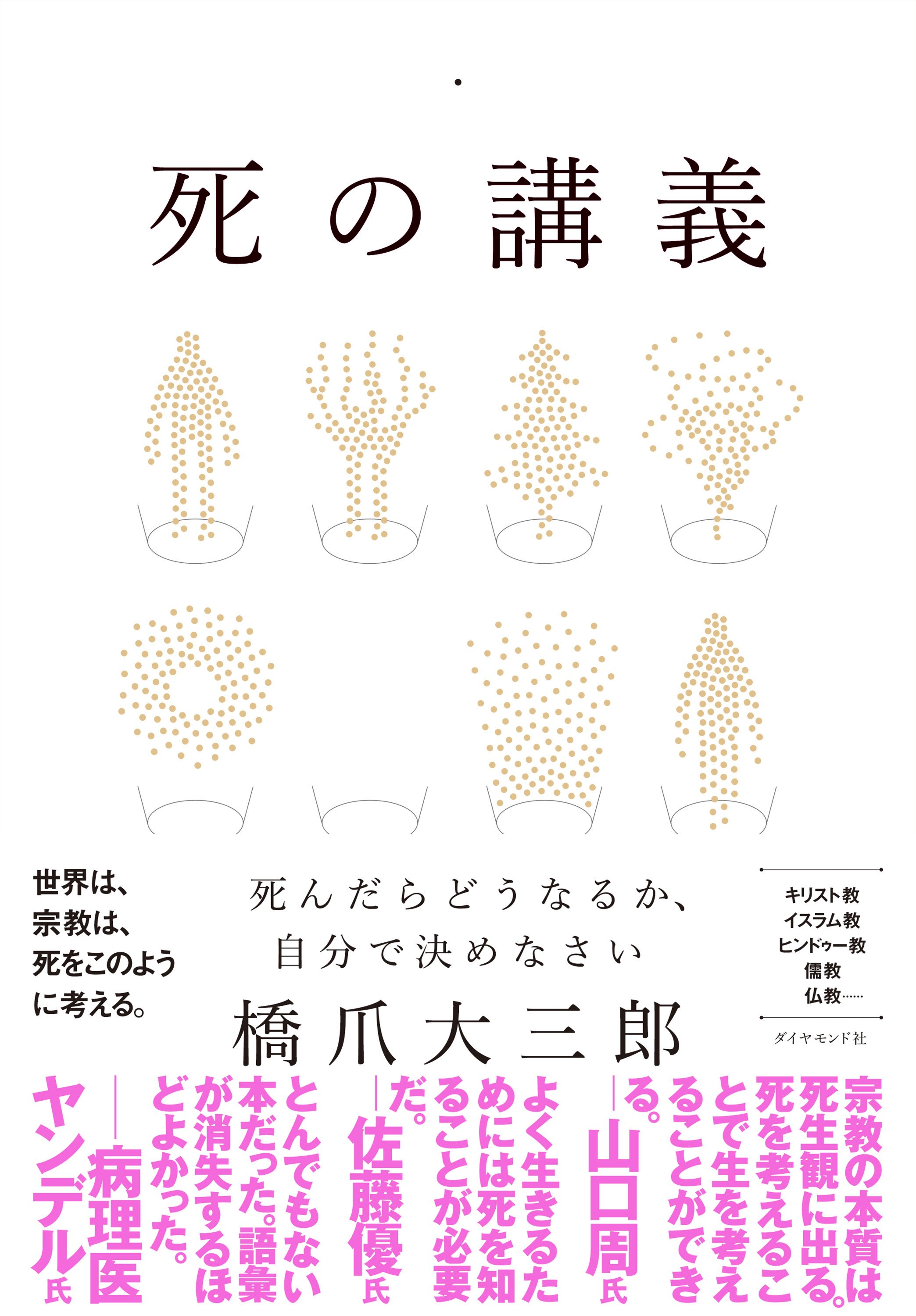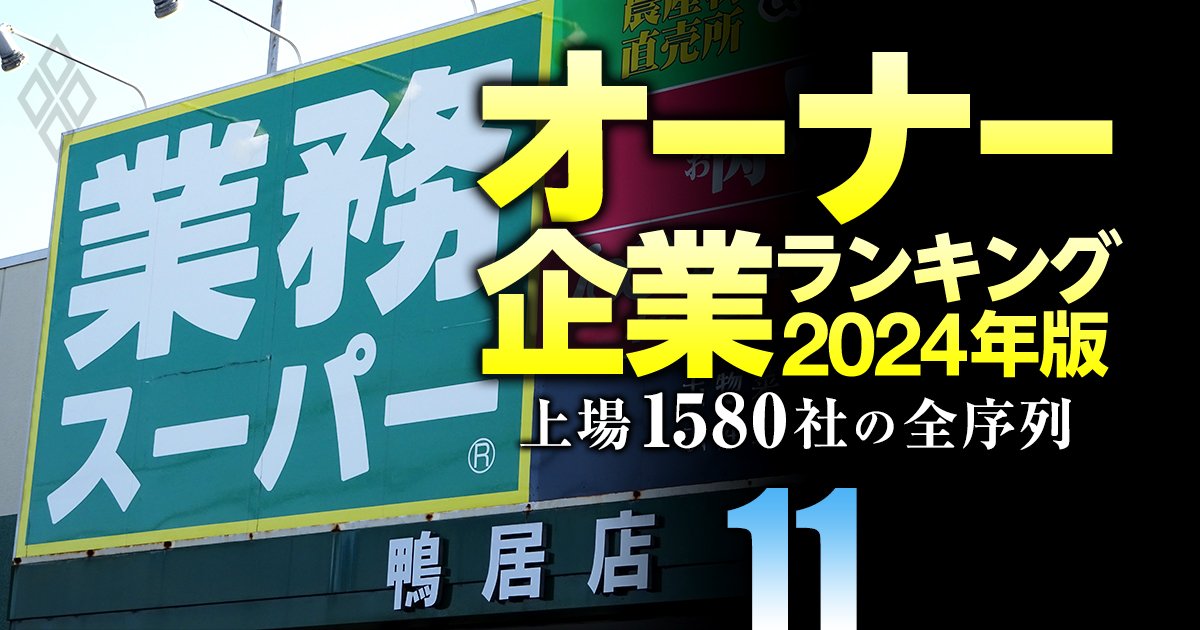「死」とは何か。死はかならず、生きている途中にやって来る。それなのに、死について考えることは「やり残した夏休みの宿題」みたいになっている。死が、自分のなかではっきりかたちになっていない。死に対して、態度をとれない。あやふやな生き方しかできない。私たちの多くは、そんなふうにして生きている。しかし、世界の大宗教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教などの一神教はもちろん、ヒンドゥー教、仏教、儒教、神道など、それぞれの宗教は、人間は死んだらどうなるか、についてしっかりした考え方をもっている。
現代の知の達人であり、宗教社会学の第一人者である著者が、各宗教の「死」についての考え方を、鮮やかに説明する『死の講義』が9月29日に発刊される。コロナの時代の必読書であり、佐藤優氏「よく生きるためには死を知ることが必要だ。」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。連載のバックナンバーはこちらから。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
科学は死についてなにが言えるか
科学は死について、なにが言えるだろうか。科学は死について、なにも大したことが言えない。とくに、「科学は、『このわたし』の死について、なにも言えない」のである。なぜだろうか。
人間はこの世界のなかで、さまざまな経験をする。世界は、まったく無秩序なわけではなく、一定の法則に従っている。さまざまな出来事の起こり方には、決まったパターンがある。科学は、そうしたさまざまな出来事がどう起こるかを、合理的に秩序立てて説明する。科学は、人間の経験を整理する学問である。
いっぽう死とは、世界を経験する「このわたし」が、存在しなくなることである。このことは、経験できない。経験をはみ出している。経験をはみ出しているのだから、経験できる出来事についての知識である科学が、扱える範囲を超えている。
だから、科学によって、死を考えることはできない。どんなに科学が進歩しようと。死はあべこべに、科学の土台を覆してしまう。
科学は、この世界の経験的な出来事を、合理的に説明するものだった。その科学を担うのは、生きている人間である。
ところが「このわたし」が死ねば、世界がなくなる。わたしはもう存在しないし、なにも経験できない。経験できる出来事がない。つまりもう、世界がない。科学は、経験的な世界についての知識なのだから、科学の成り立ちようがない。死によって科学は、世界もろとも、あらぬ彼方に投げ出されてしまうのだ。
哲学&宗教
死が不可知なものだと知りながら、それでも死と向き合い、死について考える。そのとき、科学は役に立たない。
では、なにが役に立つのか。哲学は、役に立つかもしれない。哲学は、自分がものを考えるとはどういうことか、を考えるようにできている。科学のように「世界の経験的な出来事を、合理的に説明する」ことだけに、縛られていない。人間が死ぬということも織り込んで、その覚悟で、ものを考えるのが哲学だ。
宗教も、役に立つかもしれない。宗教は、この世界がここにこうあるとはどういうことか、を考えるようにできている。その際、議論を、経験できることに限定しない。経験できないこと(超越的なこと)も、必要ならば遠慮なく取り込んで行く。死についてもっとも突っ込んで、考えてきたのは宗教である。
(本原稿は『死の講義』からの抜粋です)