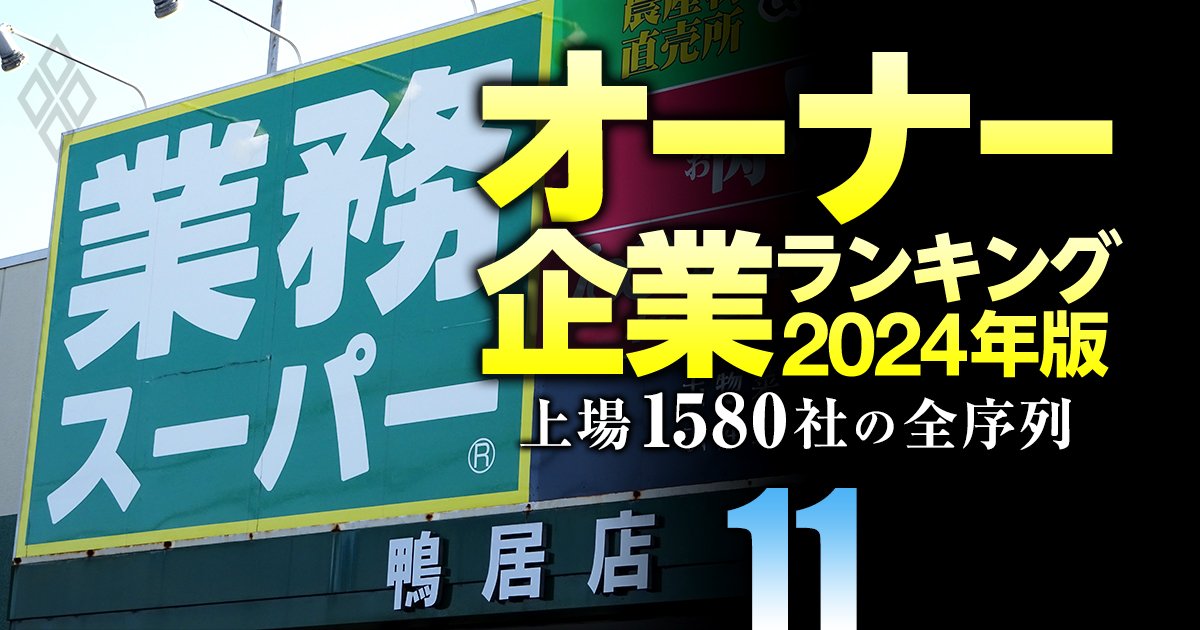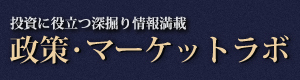Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
企業のガバナンス改革において
社外取の役割は過大評価されている
コーポレートガバナンスは、その国の歴史、文化、伝統などの社会基盤の上に成り立つものである。それらを軽視して、部分的かつ表面的に欧米の制度を移入しても、実効的なガバナンス改革は実現できない。筆者は、東芝と三菱電機の事例が示すように、ガバナンス改革において社外取締役の役割が過大評価されていると感じる。
歴史的に、東芝は何度も大きな経営上の混乱を経験してきた。1939年に、東京電気(1890年創業)と芝浦製作所(1875年創業)が経営統合して、東京芝浦電気(1984年に東芝に改称)が誕生した。その後、今に至るまで、重電部門とエレクトロニクス部門の不協和音が、社内抗争の原因の一つであるといわれる。
戦後、東芝は労働争議が頻発し、経営危機に陥ったため、1949年に石坂泰三氏(第一生命社長、第2代経団連会長)が社長に就任した。1965年、再度、東芝は経営危機に陥り、土光敏夫氏(石川島播磨重工業社長、第4代経団連会長)が社長に就任した。
こうした歴史的経緯があり、東芝は先進的とされるガバナンスを採用してきた。2003年に、米国型ガバナンスといわれる指名委員会等設置会社に移行した。当時の取締役構成は社内12名、社外4名であったが、その後、事件の度に、社外取締役構成比は高まった。
2013年以降、会計不祥事や米国原子力発電事業買収失敗などによって経営が混乱し、過去8年間に社長は6名を数える。2020年に、綱川智社長(当時)が会長、車谷暢昭会長が社長に就任した。
ところが、わずか1年後、綱川氏が社長に復帰した(車谷氏は辞任)。これらの人事は、社外取締役が多数を占める指名委員会が決定した(当時の取締役構成は社内2名、社外10名)。
次に、三菱電機の例を見てみよう。