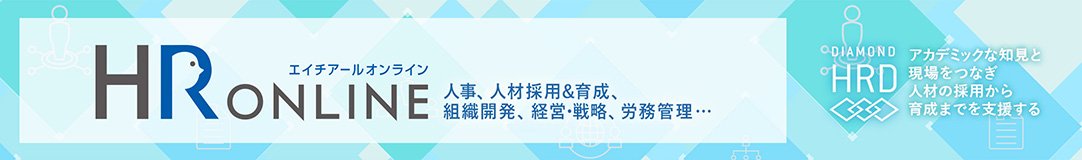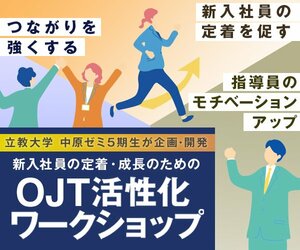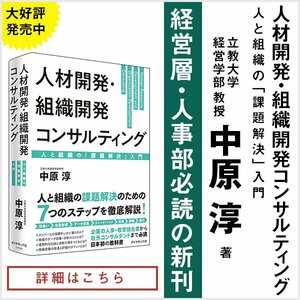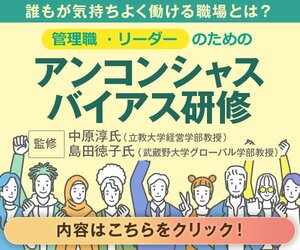“パラレルキャリア”の効果と効果最大化のために個人と組織に必要な姿勢
個人にとってのパラレルキャリアの実践効果
パラレルキャリア実践が個人にもたらす効果を、冒頭で示した内容を含めて5点あげます。
1つ目は、エンプロイアビリティの向上です。専門性・コミュニケーション力・リーダーシップ力・タイムマネジメント力の向上があげられます。「水曜日の定時後はNPOでの仕事が入っているので、その分、効率的に仕事をこなし、本業に迷惑がかからないように取り組んだ。それがタイムマネジメント力の向上につながった」。私のインタビューでこのように語ってくれた人がいました。
2つ目は、人的ネットワークの深化・拡大です。価値観の異なる人たちとの協業を通じて、自身のキャリア形成のヒントを得られる可能性があります。パラレルキャリアを通じて形成されたネットワークが本業の商談成立につながった例もあります。
3つ目は、メンタルヘルスへの好影響です。本業と家庭以外に第三の居場所があることの安心感やリフレッシュ効果があげられます。
4つ目は、リスク管理や将来への準備ができることです。まさかの事態にいつ遭遇するかわからない現代において、リスク管理の重要性は高まっています。加えて、シニア世代にとっては、定年以降の準備をパラレルキャリアの実践を通じて、戦略的に行うことも可能です。
5つ目は、人生の豊かさや充実を感じられる点です。収入目当ての副業とは異なり、基本的に、やりたいこと、将来のキャリアを念頭においての活動なので、こうした効果が生じます。
組織にとってのパラレルキャリアの推進効果
パラレルキャリアは、個人だけにとどまらず、組織にも次の5点の効果をもたらします。
1つ目は、研修代替効果です。社員が自発的にパラレルキャリアを実践することは、企業にとってコストをかけることなく、社員のスキルアップをもたらします。
2つ目は、社外視点を本業に取り込むことによるイノベーション効果です。社員と組織双方が、パラレルキャリア実践効果を本業に還元しようという思いと工夫を行うことで組織変革につながり得ます。
3つ目は、若手社員の離職抑制効果です。若手社員は自由な働き方を認めてくれる企業に魅力を感じます。囲いこもうとすることは、逆に有望な社員の社外流出を招きかねません。社員のパラレルキャリア実践に理解を示し、社外で磨いたスキルを活かせる場を設定できれば、若手社員のモチベーションや愛社精神は高まります。つまり、離職率が上がるどころか、下げる効果が期待できます。
4つ目は、シニア世代対応効果です。約8割の企業は定年後再雇用制度を採用しており、定年退職者も約8割が再雇用制度を選択するというデータもあります。再雇用制度に対しては、給与・やりがい面で個人からの批判が多い一方で、企業側も再雇用を選ぶ社員の処遇に苦慮している側面もあります。シニア世代がパラレルキャリアを通じて、社外でも通用するスキルを身につけ、社外転出が増加する(再雇用選択率が減少する)ことは本音の部分で企業はありがたく感じるでしょう。転出しないまでも、向上したスキルを本業で活かしてもらう、あるいはイキイキ働いてもらえれば、組織にとって、大きなメリットとなります。
5つ目は、副業に比べて、労務管理上の手間がかからない点です。社外での学びや社会貢献を目的とするパラレルキャリアは、収入が発生しないケースがほとんどであるため、労働時間の通算管理も必要ありません。副業解禁に二の足を踏む企業が、理由を聞かれたときに出てくる「労務管理上の煩雑さ、難しさ」という問題が原則発生しません。