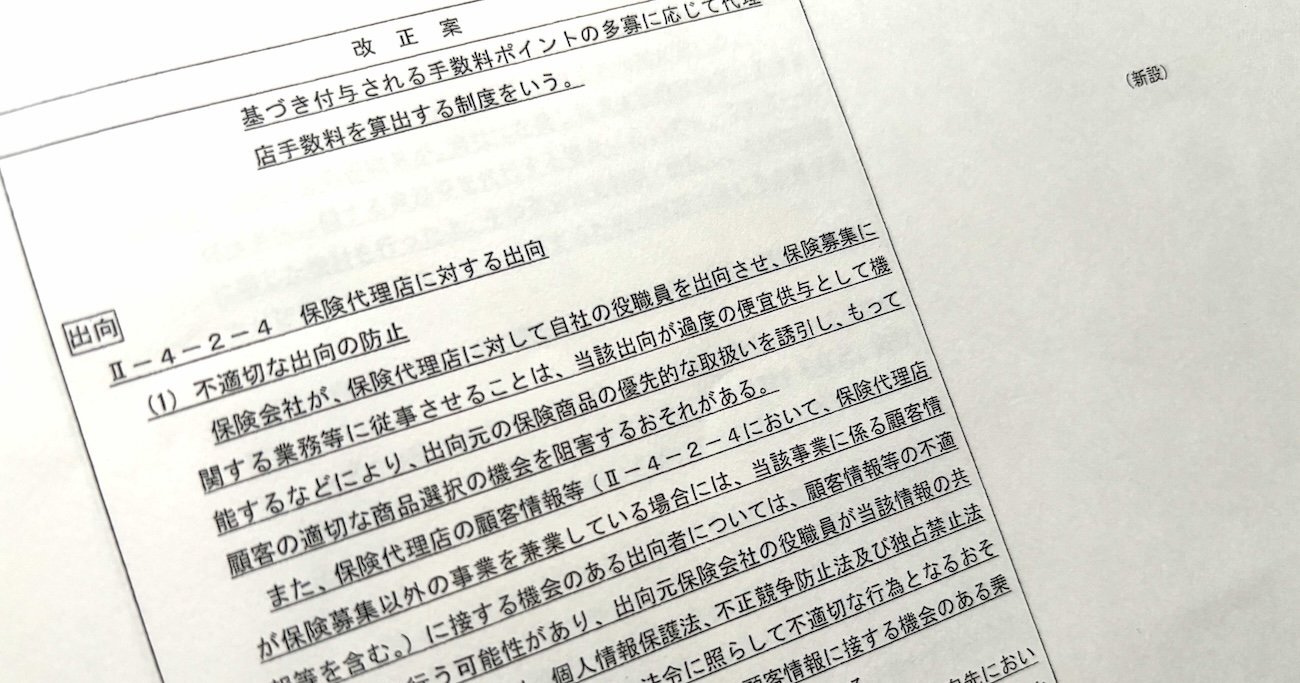ハーバード・ビジネス・スクールが正規の授業の一環として日本の東北を訪れる超人気授業「ジャパンIXP」がどのような経緯で始まったのか、また実際に学生たちや東北の受入先がどのような学びや気づきを得てきたのかレポートしていく本連載。本論に入るまえに、今回はジャパンIXPが始まる背景ともいえる、金融危機を契機とするHBSの深い自省と、その後の改革によって始まったフィールド・メソッドの全体像をお伝えします。
2008年はHBSにとって、2つの意味で転換点となった。
ひとつは、100周年を迎えたこと。100周年のイベントは、約1年かけてさまざまなテーマについて世界各地で断続的に行われた。テーマのひとつは、未来のMBA教育のあり方を考える、というものであった。そのためにHBSの教授陣がチームを組み、世界のビジネススクールの過去10年の応募数、実際の入学率、学費などのデータを集めて分析し、欧米のトップのビジネススクールの学長と企業経営者それぞれ30人にMBA教育の価値と欠点についてインタビューを行った。また、11のビジネススクールのカリキュラムを分析し、評価が高い科目については担当教官のインタビューを実施するなどより深い考察を行い、6つのビジネススクールのケースを作成した。
結果、世界的にビジネススクールへの応募数は伸び悩み、また実業界からもMBA教育の価値への疑問符が打たれ、どの学校もこのままの教育ではいけないという認識を共有していることが分かった。多数のビジネススクールの学長、教官、経営者をHBSのキャンパスに招き、その時点での発見をもとに議論を行い、さらにHBSの教授陣だけで議論を深めた。
1年にわたって続いた100周年記念の最大のイベントは、4月8日に行われたHBSキャンパスでのセレモニーであった。教授、学生、スタッフの誰もが登録すれば参加できる1000人を超えるランチのほか、グリーンをテーマに美しく装飾された巨大なテント会場でのカクテルパーティー、キャンパスのそこかしこで開かれるさまざまなセッションやワークショップなど、まさに盛大かつ豪華絢爛だ。
しかし皮肉なことにそんな100周年のお祝いと同時進行で、世界金融危機が始まっていた。これが、HBSに転換を促したもうひとつのきっかけとなる。
世界金融危機はHBSにいくつかの変化をもたらした。まず、売上の減少を見越した徹底的なコストカットである。一部のスタッフがレイオフされる、キャンパス内でサンドイッチやコーヒーを売るスタンドが一部閉鎖される、学校として購読している新聞の種類が激減する、ミーティングの際に出ていたブラウニーやクッキーが廃止される、全スタッフのボーナスがカットされるなど……100周年のきらびやかさから倹約志向に一転した。派手なときは思いっきり派手だけど、カットするとなったら、「別にクッキーをなくしても大した額じゃないのでは…」というところまでカットする、というHBSの「やると決めたらとことんやる」文化を再確認することになる。
また、さらに重要だったのは、これまでの自分たちの教育は本当に正しかったのだろうか、という深い自省である。
HBSは世界金融危機の震源地となったアメリカの金融業界に数多くの卒業生を輩出していた。「世界を変えるリーダーを育成する」という理念を掲げてきたが、本当に世界をよい方向に変えるリーダーを育成できていたのか?もしできていたらそもそもあの危機は起こらなかったのではないか?自分たちの教育がむしろ原因を作ってしまったのではないか?
Knowing,Doing,Beingという新たなフレームワーク
この自省をもとに、金融危機前から考えていた未来のMBA教育のあり方について、さらに追加の分析や考察を行ったうえで、結論を出した。未来のMBA教育を考える一連の議論をリードしたHBSの教授らは、結論の核をknowing(知識)、doing(実践)、being(価値観、信念)という3つの言葉を用いてこう説明している。
ビジネススクールがリーダーやアントレプレナーを育成したいと考えるのであれば、どのような事実、フレームワーク、理論を教えるか(“knowing”)について再検討する必要がある。また同時に、カリキュラムのバランスを見直して、経営の実践の肝となるスキル、能力、技術の開発(“doing”)、そして経営者の世界観やプロフェッショナルのアイデンティティを形成する価値観、態度、信念(“being”)により焦点を当てるべきである。
実践(doing)のスキルがなければ、いくら知識(knowing)があっても役立たない。また自己の存在(being)からくる価値観や信念を反映した自己認識がなければ、doingのスキルも方針が定まらない中で有効に使えることはできない。
これまでの教育は、事実、フレームワーク、理論を教えて「知識を増やす(knowing)」ことに重点を置きすぎていた。よりスキルや能力の開発につながるような「実践(doing)の場」を増やし、またすべての行動のベースとなる自身の価値観・信念の認識を深める「自分が何者であるかを知る(being)教育」を行っていかなければいけない、という結論である。つまり、これまでは頭ばかり動かしていたが、これからは実際に体も動かし、そして心を豊かにしていく。頭と体と心のバランスをとる教育をしていかなければいけない、という決意表明だ。日本の武道の世界で唱えられてきた「心・技・体」の概念に非常に近いのではないだろうか。
教育大改革を背景にした「フィールド」の導入
この「knowing,doing,beingのバランスを取り戻す」という方針は、実際にHBSの教育現場にも導入され、大規模な教育カリキュラムの変革が行われた。
変革をリードしたのが、2010年にHBS10代目の学長に就任したニティン・ノーリアだ。インド出身のノーリアは、100年のHBSの歴史で初めての非北米出身、つまり白人でないHBSの学長で、リーダーシップ、組織変革を研究していた。まさに自身が研究者として研究していた内容を、リーダーとして実践する立場になったのである。
ノーリアは、多数の教授やスタッフとのミーティングを重ね意見を聞きながら、就任後わずか100日でHBSが今後も世界のリーダー育成機関であり続けるために必要な5つの優先事項を掲げた。
その最初の優先事項が、教育カリキュラムのイノベーションであった。HBSは約100年にわたってケース・メソッドを唯一の教授法としてやってきたが、それによってknowing偏重の教育になってしまった。doingとbeingのバランスをとった教育にしていくために、カリキュラムにイノベーションを起こす、という意味である。
前回述べたとおり、HBSは教室というインフラからスタッフの体制まですべてがケース・メソッドの効果の最大化という目的に向かって設計されている。教授もケース・メソッドを唯一の教授法としてやってきた人たちだ。そこに新しい教授法を開発し導入するというのは、本当に大変だったと思う。遠く離れた東京にいても、時折議論の不協和音が聞こえてきたほどだ。
しかし結果として、2011年9月入学の学年から新しい教授法に基づく必修科目が導入された。ノーリアが学長に就任してからたった1年で、教授会での意思決定とカリキュラム開発、必要な体制構築まで行ってしまったわけだ。
世界金融危機の前から課題と方針を議論していて、かつ危機によって教育を変革しなければ未来はないという思いが強まったところに、ノーリアのリーダーシップが加わったことによって、これだけのスピードで変革が起こせたのではないかと思う。危機が起こった後に組織がどのように動けるかは、危機前にすでに徴候を捉えて準備を始めていたか、そして危機後のリーダーのあり方にかかっているということを、自分が働く組織の経験からも改めて学ぶことができた。