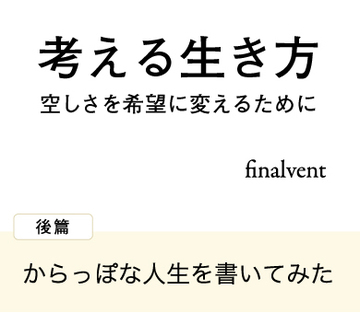『考える生き方』は、ネット界で尊敬を集めるブロガー・finalvent氏の第1作。自身の人生を「からっぽだった」「失敗だった」と吐露する稀有なスタンスが多くの人の共感を呼び、人生の「むなしさ」と苦難を受け止めるヒントになる内容として話題となっている。この連載ではその「はじめに」と、「おわりに」の代わりとして小冊子「Kei」書かれたエッセイを紹介する。
昨年の夏、55歳になった。
私が子どものころ、1970年代の大企業の定年は55歳だった。子どものころの私は、自分が55歳まで生きていたら定年になってもう仕事をすることはないだろうと思っていた。そのあとの人生は余生だろうとも。
現在の企業の定年は65歳くらいだから、55歳で余生とか人生とか考えるのは早すぎる。それでも自分の人生の大半は終わった感じはする。55歳まで生きられなかった人もいろいろ見てきたから、ここで人生が終わってもしかたない。
自分の人生はなんだったんだろうかと思うようになった。
なんだったか?
からっぽだった。
特に人生の意味といったものはなかった気がする。55歳以降でも一念発起して事業を成し遂げる人もいるから、年を取ったからといって結論を急ぐこともないが、私の場合はこれから人生の一発逆転みたいなことはないだろう。
こうなることはずいぶん前からわかっていた。
自分の人生はからっぽになるだろうというのは、20代のころうすうす気がついていた。30代になって、たぶんそうなるんだろうという確信のようなものが芽生えた。40代になって、ああ、からっぽだという実感があった。これは、あれだな、と若いころ覚えた論語の章句が浮かんだ。
論語に「後生畏るべし」という言葉がある(子罕第九の二十三)。
「後生」というのは「先生」の反対で、自分より年が若い人のことだ。自分より若い人の未来に自分より優れたものがあるというのだ。若者の未来を思って若者をせよと。これに「いずくんぞ来者の今にしかざるを知らんや」と続く。どうして若者が現在の大人に劣るといえようか、と。
若者には可能性がある。自分にも、たぶん、あった。そしてそれがなくなった。いつなくなったかというと、「後生」が見えたときである。自分より若年の人のなかに自分より優れた可能性を見たときだ。この若者たちは優秀だなと思うときだ。
具体的にいつごろの年代かというと、40歳から50歳である。続けて論語で孔子先生がこう言っている。
「四十五十にして聞こゆること無くんば、これまた畏るるに足らざるのみ」。
40歳、50歳になって世にその名が知られるようでもなければ、そんな人は尊敬に値しない、と。
それが私だと、40歳のときに思った。