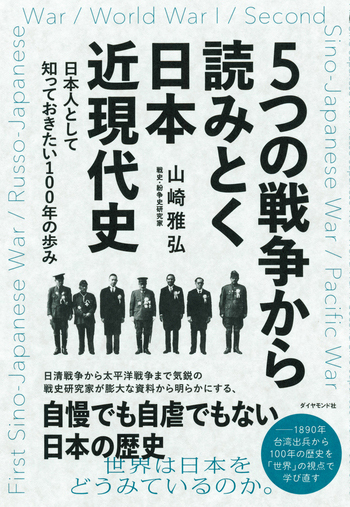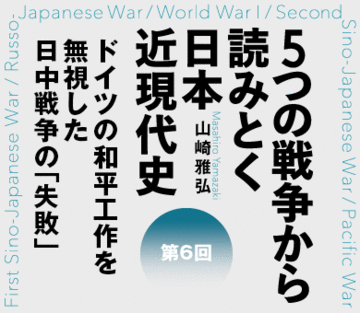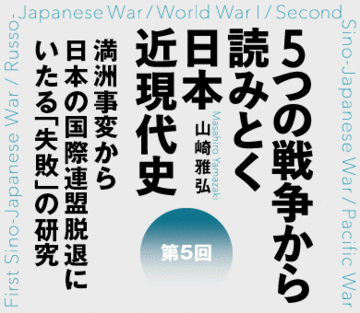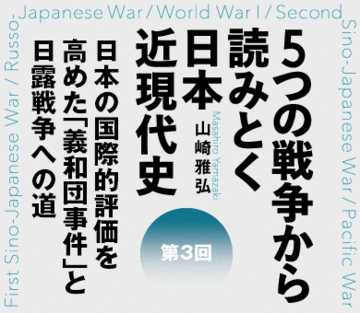近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売4日でたちまち重版・4万5000部突破の気鋭の戦史・紛争史研究の山崎雅弘による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第7回は経済的には相互依存をしていた日米が開戦に至るまでの道程を解説します。

対日宥和か、対日強硬か?
揺れ続けたアメリカ
日本が国際連盟からの脱退を宣言したのと同じ年、1933年3月4日に第32代のアメリカ合衆国大統領へと就任したルーズベルトは、就任から1937年頃までは、日本との友好関係を重視し、1930年代を通じて頻発した日中間の紛糾に対しても、双方から一定の距離を置く姿勢を貫き続けていました。満洲事変に始まる日本の大陸進出は、1922年2月の「九カ国条約」で国際的に保障されたはずの、中国における門戸開放と商業上の機会均等を脅かすものでしたが、ルーズベルトは将来における「日米両国による中国経済の共同支配」という可能性も視野に入れながら、日本との協調関係を模索し続けました。
しかし、1938年11月3日に、近衛首相が「日本と満洲、中国を政治的・経済的・文化的に結合させて大東亜新秩序を建設する」との国策上の方針(第2次近衛声明)を、全世界に向けて発表すると、米政府は中国市場が日本によって独占される可能性の高まりに強い危機感を覚え、日中戦争で中国側に味方する方策へと路線を転換します。約1ヵ月後の12月15日、ルーズベルトは中国(蒋介石の国民党)政府に2500万ドルの借款を供与すると発表し、米国民の大多数による支持を待つことなく、大統領権限の範囲内で、日本との対決に向けた第一歩を踏み出したのです。
アメリカ政府が、日本軍の北部仏印への進駐に対する最初の「経済制裁」を行ってから約半年後の1941年3月8日、中国とアジアにおける政治と軍事の問題解決に向けた日米交渉が、本格的にスタートしました。駐米大使野村吉三郎と米国務長官ハルによる日米交渉が進められていた時、ハルは「日本に対する政治的・軍事的圧力を強めすぎると、逆に日本政府内の対米穏健派の立場を弱めることになり、最終的にはアメリカにとっての不利益を生む」との認識から、理性的な交渉の継続をルーズベルト大統領に進言していました。
1932年の着任以来、日本国内の政情をつぶさに観察してきた「知日派」の駐日大使ジョセフ・グルーも、ハルとほぼ同意見でした。しかし、7月23日に日本軍が南部仏印への進駐を決定(実際の進駐開始は7月28日)すると、状況は一変します。先に挙げた北部仏印進駐の場合、日中戦争に関連する「ハイフォンルートの遮断」という大義名分がありましたが、南部仏印進駐については、米領フィリピンや英領マラヤおよびシンガポール、蘭領東インドの安全を直接的に脅かす「出撃拠点の確保」という、アメリカにとっては見過ごすことのできない意図が込められていたからです。
この事実を知ったルーズベルトは、従来のような宥和的な対応では日本の政策に対処できないと考え、「対日強硬派」の意見を採り入れた新手を立て続けに打ちました。まず7月24日に「日本軍が仏印から即時撤兵すれば、米政府は英中蘭各国に働きかけて、仏印を完全な中立状態に置く努力を行う」との提案を日本政府に送る一方、翌7月25日には在米日本資産の即時凍結を発表、8月1日にはモーゲンソーらが主張し続けた「対日石油輸出の全面禁止」という、最も強い切り札を繰り出しました。アメリカ政府内における「対日宥和派」の発言力は、日本軍の南部仏印進駐が行われた1941年の夏以降は急激に低下し、スティムソンやモーゲンソーら「対日強硬派」の発言力を相対的に強めることになりました。
また、アメリカの実質的な同盟国であるイギリスとオランダも、日本資産凍結や日本との通商協定破棄を行い、日本に対する経済制裁に加わりました。これに対し、日本側は9月6日の御前会議で「対米戦争を覚悟する決意の下に、10月下旬を目途として戦争準備を完了させる」との方針を決定します。米政府との外交交渉は、引き続き継続するものの、10月上旬になっても相手が日本側の言い分に耳を傾けないなら「ただちに対米開戦を決意する」という、交渉破棄の期限を定めた内容でした。
実は最後通牒ではなかった
「ハル・ノート」
1941年11月の時点で、米政府は「全面協定案」(「ハル・ノート」の原型)と「暫定協定案」という2つの提案のいずれかを日本に提示する検討を進めており、後者は日米双方の譲歩を前提とする事態打開の方策を列記した内容でした。しかし、11月26日の朝、陸軍長官スティムソンから、日本軍の輸送船団が上海を出発し、台湾南方を航行中であるとの誤った情報を知らされたルーズベルトは、「(中国での)休戦と撤兵の交渉をしている最中に、新たな軍事侵攻の準備に着手するとは、明らかな背信行為だ」と激怒して、日本に対する態度を一挙に硬化させました。
その結果、同日午後5時にハルが日本側代表へと手渡した文書は、相互譲歩を前提とする「暫定協定案」ではなく、日本に対する一方的な撤兵要求を書き連ねた「日米間総括的基礎提案」(いわゆる「ハル・ノート」)でした。ハルが日本側に提示した「ハル・ノート」の内容は、日本軍の中国からの撤兵、汪兆銘政権(南京政府)の否認、日独伊三国同盟の空文化に加えて、全ての国家の領土および主権の尊重、内政不干渉、通商上の機会均等、紛争の平和的解決などで、その多くは日本側がそれまで進めてきた対外政策をことごとく否定するものでした。
そのため、日本軍上層部は「わが国が決して受け入れられない条件ばかり突きつけてきた」と激しく反発し、対米開戦はもはや不可避だとの意見が大勢を占めました。しかし実際には、「ハル・ノート」はアメリカ政府から日本政府への正式な要求文書ではなく、単にハル国務長官の覚書に過ぎず、書類の冒頭には「一時的かつ拘束力なし」との文言が記されており、戦争を前提とした「最後通牒」ではありませんでした。
それゆえ、例えば「中国からの撤退」という項目には満洲国が含まれないとの解釈も可能であり、日本軍上層部の意向を無視して考えれば、この「ノート」を土台にして、さらに日米交渉を続けるという選択肢もあり得たはずでした。また、もし日本軍上層部に「今までの日中戦争の進め方は誤りだった」と反省する合理的な思考力があったなら、この「ハル・ノート」を逆に利用して、中国からの撤退の口実にするのと同時に、「我々も言うことを聞いたのだからアメリカ側も他の分野(石油禁輸の撤回など)で譲歩せよ」との要求を突きつけ、日中戦争終結と対米戦回避の両方を実現できたかもしれません。
けれども、日本政府と軍の上層部は、この期に及んでもなお、自国民に対する自分たちの面子の維持に固執し、過去数年間にわたって積み重ねてきた「対外政策の失敗」を認めることができませんでした。今までのやり方は失敗だったと認めてしまったなら、政府と軍指導部の威信は失墜し、主要幹部の責任問題へと発展してしまうからです。
日本はこの時までに、日中戦争で約20万人の兵士を失い(負傷者を含めると約50万人)、国家予算の7割を軍備につぎ込んでいました。こうした過去の人的損失とコストの大きさも、政府と軍の指導部が自らの失敗を認めることを邪魔していました。日本の一部では、太平洋戦争の勃発は「ハル・ノート」という理不尽な要求を日本がアメリカに突きつけられたことで「やむを得ず」始まったもので、日本はいわば「罠にはめられた被害者なのだ」という自国中心の主観的な主張が、今も盛んに語られています。しかし、ここまで述べてきた歴史的事実の経過を踏まえて、客観的視点から見ればわかる通り、日米戦争はハル国務長官が提示した「ハル・ノート」によって、唐突に引き起こされた戦争ではありませんでした。