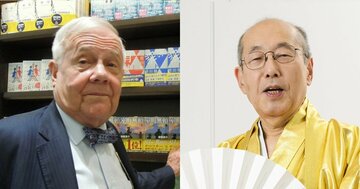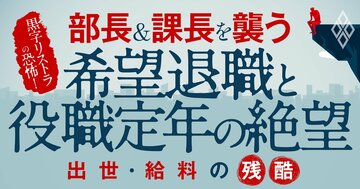5月6日、菅直人首相は中部電力に対して、東海地震の想定震源地の上に立つ浜岡原子力発電所の停止を求めました。「再び地震によって原発事故が起きれば、日本全体に甚大な影響が及ぶ」というのがその理由でした。
そして中部電力もそれに応じ、運転中の2基と定期検査中の1基を止める決断をしました。運転中の原発を、政府が止めさせるというのは前代未聞のことです。この事実だけ見れば、日本が「脱・原発」に大きく舵を切ったと受け止められなくもありません。
しかし、実際はそうではありません。菅首相は、「あくまで浜岡だけ」と協調しましたし、枝野幸男官房長官は「原発政策の基本は変わっていない」と語り、海外への原発輸出の旗振り役だった仙谷由人官房副長官も「政策としては原発を堅持する」と述べています。
東京電力・福島第1原子力発電所のあの大惨事を受けても、日本の原発政策は止まることはありません。それが現実です。その理由は、原子力発電所という産業そのものが巨大な“システム”になっているところにあります。
日本には商業炉として54基の原発があり、現在約20基が運転を続けていますが、その裾野は実に広大です。何しろ、用地選定から運転までに20年、そして運転は最長で60年間続きます。役目を終え廃炉にするのも、放射能の除染や核廃棄物の処理などで20年を要します。すべての過程で100年に及ぶ、恐ろしく息の長い産業なのです。
当然、その間には膨大な人と企業、カネが絡みます。関わる企業や団体は500をくだらないでしょう。福島第1原発の事故では、東電の責任が大きく取り沙汰されていますが、東電とてこの大きなシステムの中の一事業者にすぎません。
また、原発を誘致した自治体も、交付金や電気料金の割引措置、各種の助成金も付いて潤います。さらに、原発産業の推進に際してはもちろん政治家が介在し、行政と産業界を結ぶパイプ役として天下り官僚も跋扈しています。大学をはじめとする研究機関も、安全性を保証する国の代弁者として一役買います。
国民が払う電気料金という非常に安定した収入を、100年の長きにわたり関係各所で分け合う“共存共栄”のシステム。それが原発産業なのです。この、強固につくり上げられた原発を巡る利権の構造は、易々と崩れるものではありません。
世界最大の原発事故を受けても、日本の原発は止まらないし、止められない──。今週号では、そんな日本の原発の現実を、様々な角度から読み解きます。
(『週刊ダイヤモンド』副編集長 深澤 献)