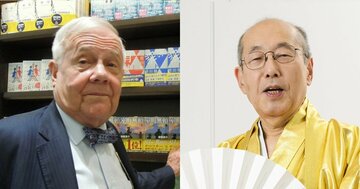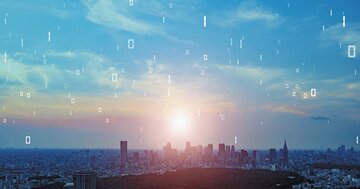介護給付の拡大が止まらない。今や10兆円に達し、2025年度には21兆円まで拡大する見通しだ。このままでは制度の維持が困難とみた国は、スタートから16年目の来年、介護保険制度の大改革に乗り出す。中でも高齢者の負担が増えるという意味でインパクトは大きい。その中身を詳細に見ていくことにする。そのため、制度の維持を目的に制度改革が行われようとしている。
来年から介護サービスの
自己負担が1割から2割に
都内のマンションで一人暮らしをしている末吉倫太郎さん(仮名)は今年88歳。一昨年、重い荷物を持とうとして腰を痛めてからというもの急に体調が悪化、最近になって介護認定を受け、訪問介護サービスを利用している。
そんな末吉さんは、先日、ケアマネジャーの言葉にあぜんとした。
「来年から介護サービスの自己負担が1割から2割になるらしいですよ」
月々の収入は年金などで26万円。そこから食費や光熱費などを支払った上で、ホームヘルパーの費用など介護サービスを利用する際の自己負担分を支払うと余裕はない。
「2割というかもしれないが、負担は2倍になる。受けているサービスを減らすしかないかなぁ」
末吉さんの表情は、それ以降曇ったままだ。
介護が必要な末吉さんにさらなる心痛を与えた原因は、6月18日に成立した「地域医療・介護総合確保推進法」だ。
この法律は、2000年に創設された介護保険制度を見直すもの。高齢化が一段と進み、介護保険の利用者が増える中でも制度を維持できるような仕組みを整えようという狙いがある。
少々、理屈っぽくなって恐縮だが、概要を説明しよう。ポイントは大きく2つある。
まず1つ目は、介護サービスを受ける際の「自己負担割合」だ。
これまで自己負担割合は、原則として1割だった。それを、15年8月から一定以上の所得のある人は2割に引き上げる。