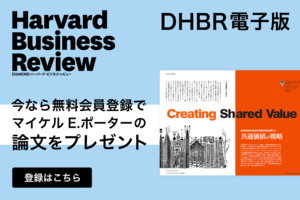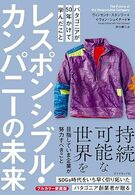同じ会社で働き続けたり、同じ仕事を数十年も続けたりしていると、「このままでいいのだろうか」という疑問や不安が頭をよぎることがある。ただ、思い切った変化を起こそうにも、自分中心でキャリアを選べた20代の頃とは異なり、そこにはさまざまな制約が課せられてもいる。本記事では、こうしたキャリア中期に抱きやすい倦怠感への対処法を、事例とともに紹介する。
誰もが次のような疑問を抱くときがある。「この会社は、自分にふさわしいのだろうか。この仕事は、自分にふさわしいのだろうか。そして、これが自分の仕事のすべてなのだろうか」と。
このような疑問は、キャリア中期の働き手にとって特に悩ましい。この層は、家庭でやるべきことを抱え、収入の必要性が大きく、かつ達成感も求めていると思われるからだ。
キャリア中期の危機に、どのように対処すべきなのだろうか。仕事の満足度を高めるために、どのような手立てを講じられるだろうか。毎日の仕事の単調さや退屈さを、どうすれば撃退できるだろうか。そして、大々的な変化を起こすべきタイミングを、どのように判断したらよいだろうか。
●専門家の意見
キャリア中期の倦怠感は根深い。それは、単なる「一時的な」不満や、人を消耗させる「とてもきついプロジェクト」のようなものではないと、INSEADの組織行動論准教授であるジャンピエロ・ペトリグリエリは言う。「『自分は何かを逃しているのではないだろうか』という気持ちが、いつまでも拭えないのです」
キャリア上のこの種の不満は、中年期に比較的よく生じる、と彼は言う。「中年期は、自分は不滅であるという幻想が失われるときです。自分のチャンスは永遠に続くものではないと知り、時間には限りがあるのだと認識します」
キャリア上で大きな成功を収めた人でも、このような気持ちと無縁なわけではない――そう述べるのは、Build an A-Team(未訳)などの著者であり、企業幹部のコーチも務めるホイットニー・ジョンソンだ。「彼らは自問するのです。『これは本当に自分がやりたいことなのだろうか』と」。
「キャリア上の不安を経験するのは、自然で普通のこと」ではあるものの、「それにどう対処すべきか」を心に留めなければならない。「それに対して何をすべきか、あらかじめ考えておく」必要があるのだ。その方法を以下に示そう。
●内省し、見方を変えてみる
手始めに、キャリア上の不満の原因を特定してみよう。ペトリグリエリは言う。「倦怠感が生まれると、何もかも疑問に思い始めるものです。ですが、問題を分解して、不満の核心をまず明らかにする必要があります。それは仕事なのか、それとも所属する組織なのか」。その答え次第で、対処法は異なる。
もちろん、中年になってからキャリアパスを再考するのは容易ではない。避けて通れないいくつもの責務も考えなくてはならない。それは、住宅ローンだったり、別途キャリアを歩む配偶者やパートナーだったり、学校に通う子どもだったりするかもしれない。
自分の前進を阻んでいる物事について、あれこれ悩んでいることに気づいたら、「それらの制約について見方を変えてみること」をジョンソンは勧める。
若くて、世界中のどこにでも住んで働くことができる時分には、みずからのキャリアパスを計画するのは、非常に大変な、「気が遠くなるような」作業だ。「でも中年になると、その範囲が限定的になります。生活するためにどの地域で働き、いくら稼ぐ必要があるかがわかってきます。こうした制約が、(キャリアパスを描くうえで)実際には役に立つのです」
●小さな変化を起こす
組織にはおおむね満足しているが、仕事には不満がある、というのは珍しいことではない。可能な方策の1つは、「仕事にもっと深く打ち込むために、何かを少しだけ変えてみることはできるか」を検討することだと、ペトリグリエリは言う。たとえ状況そのものは変えられないとしても、「身の回りの小さな環境を変えることはできるかもしれません」
たとえば、刺激的で夢中になれるプロジェクトを探し求める、背景の異なる従業員を雇う、自分をこれまでと違う新たな方法で成長させてくれる社内の委員会やチームに参加する、などだ。勤務の形態やスケジュールの変更を交渉してみたり、異動願いを出したりしてもよいかもしれない。
これまでのルーティンを一新し、「自分の仕事を新鮮なものにする」ことで、仕事への態度や見方が大きく変わりうる。「何を、誰と、どこでやるか」を慎重に検討することがカギである。
●学習に焦点を当てる
中年期のキャリアにおける倦怠感の最大の原因の1つは、退屈である。
ジョンソンは言う。「人は長い人生とキャリアを通して学んでいきます」。だが、40代になる頃には、「自分がやっていることと、その中で何が得意かがわかってしまい、退屈になります」。そして「学習と達成にともなうドーパミンの放出」を再び望むようになる。上司に昇進を求めたり、新たな任務や責任を引き受けたりするのは、明らかにその方策の1つだ。
しかし、ジョンソンは、横への動き(昇進ではない他の職務への移行)を検討してみるよう勧める。「上に行くことが唯一の道なのか、自問してみてください。自分が学習し、成長できる何か面白いことをできるのなら、昇進の階段を昇る必要はないかもしれません」
そのような魅力的な仕事の空きがないのなら、自分自身でそれをつくり出すようジョンソンは提案する。そのためには、「組織内の問題を探し、自分こそがそれを解決するのに適していると証明する」ことだ。
次の問いを、みずからに投げかけてみよう。
「同僚はどんな課題に直面しているだろうか。何がクライアントを苛立たせているだろうか」「自分が他者から繰り返し称賛される部分はどこだろうか。他の人が難しいと感じるのに、自分が易しいと感じることは何だろうか」
会社の儲けや節約に、自分の強みでどう貢献できるかを、創造的に考えるとよい。そのうえで、「ここに、私たちが組織として試してみるべき案があります」と宣言しよう。
結局、「自分が次に成すべきことは何か、他人に教えられるのを待っていてはなりません。自分で仕事をつくり出すのです」(ジョンソン)
●仕事の意義を意識的に探す
ペトリグリエリによれば、キャリア上の倦怠感と不満の源としてもう1つありがちなのが、「自分の仕事は何にも影響を及ぼさない」という欲求不満である。長時間働きながら、「何のためにこの仕事をやっているんだろう」と疑問を抱く人もいるかもしれない。
だが、「やりがいは向こうからはやって来ない」ことを心に留めるべきだ、と彼は言う。「それは愛のようなものです。探し求め、力を注ぎ続ける必要がある。存在して当たり前のものではないのです」
自分の仕事から直接恩恵を得る人たち(顧客、クライアント、同僚など誰であれ)を満足させるために、一貫した努力を注ごう。「自分の仕事がどのように他の人の役に立っているかがわかれば、必然的にやりがいが見えてきます」。さもなければ、仕事の意義を簡単に見失い、「頭でっかち」になってしまうのだ。
●キャリアチェンジを検討する
ここまで述べてきた方策が望ましい効果をもたらさない場合には、思い切った動きを起こすべきサインかもしれないと、ジョンソンは言う。「自分自身に破壊的変化を起こす必要がある、という気持ちが心の奥底にあるならば」、それを無視してはならない。「仕事に打ち込めないまま続けていると、自分で自分をダメにすることになります」
うんざりするような仕事を続けているのは「金のため」だという人は多い。だが、実は往々にして、周囲に知られているキャリアの道を捨てることによって「名声と地位が失われる」ことを恐れて辞めないのだ、と彼女は言う。
自分に正直になり、考えてみよう。みずからを現状にとどめている要因は何か。ある程度のリスクテイクや実験を、してみるべきではないか。
たしかに、人生半ばでキャリアを転換するのは怖いだろう。だが、ここでも自分の窮地のプラス面を考えてみよう。「おそらく、すでに何らかの専門知識があり、自分のことを昔よりもよくわかっているでしょう。20代の頃のように、誰かの承認を得る必要はないのです」(ジョンソン)
自分が追い求めたいものは何か。それが現在のキャリアでないのなら、みずからの知識を活かして、深く慎重に考えることだ。この場合、キャリアコーチとともに取り組むのが効果的だとペトリグリエリは言う。
●自分の前提を疑ってみる
キャリア上の倦怠感は、自分の中で仕事の存在が大きすぎる証である可能性もある。おそらく、「キャリアを常に重視するよう強いられる文化に、息が詰まっているのでしょう」と、ペトリグリエリは言う。「仕事にすべてを注いでいるという事実に、嫌気がさしているのかもしれません」
その場合は、自分の価値と生きる喜びを、仕事の外で探す必要があるのかもしれない。家族、信仰、慈善事業への支援、あるいは情熱を注げる活動や趣味やスポーツでもよい。
たしかにこれは、非常に野心的で「成功を収めた人々」にとっては、慣れ親しんだ思考法ではない。「プロフェッショナルは仕事を通じて人生の意義を見出すもの、と考えられています。そうでなければ、白い目で見られるでしょう」と、ペトリグリエリは言う。
このような非難がましい視線をやりすごすためには、「自分自身を許す必要があります」。また、成功に囚われていたこれまでの状態から抜け出したいという自分の欲求を、「非難せず支持してくれる人たちで周囲を固める必要もあります」。結局、「残された時間は、もはや永遠ではありません。先延ばしにすれば代償も大きくなります。いまでないなら、いつやるのか、ということです」
●覚えておくべき原則
【やるべきこと】
・問題を分析し、次の問いを自問する。「これは自分の仕事だろうか。それとも所属する組織の仕事だろうか」
・自分の仕事から恩恵を得る人たちに応える努力をしながら、意義を探す。
・昇進ではなく横への動きを検討する。新たな課題を担って学習するのは良い方法である。
【やってはならないこと】
・仕事のルーティンや環境を少しだけ変えてみることの効果を、軽視してはならない。
・チャンスをただ待っていてはならない。解決したい問題を見つけ、新たな仕事を自分でつくり出そう。
・仕事がすべてになってはならない。家族、信仰、活動、趣味などを通じて充足感を得る方法を考えよう。