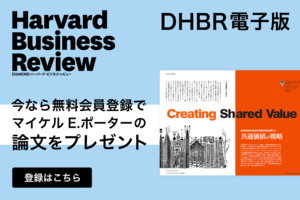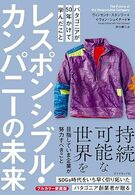組織の経済学とは
今回から「組織の経済学」(organizational economics)に入る。
組織の経済学を学ぶことは、現代の経営学で不可欠である。米国の経営学のPh.D.(博士)プログラムで、組織の経済学に触れないことはありえない。同時に、これらはビジネスパーソンが自社のあり方を考える上でも、重要な「思考の軸」になる。例えば、スタンフォード大学ビジネススクールの教授陣には組織の経済学を専門とする学者が何人もいて、彼らの書いたテキストがMBA授業で使用されている(※1)。
経済学ディシプリンの前章までは、主に「市場」に焦点を当て、そこから導かれるSCP理論やリソース・ベースト・ビュー(RBV)を解説した。完全競争市場では企業は儲からず、独占市場に近づくほど企業は超過利潤を得られる。したがって「完全競争市場が成立するための『4条件』をいかに崩していくか」が、SCP・RBVの根底にあった(※2)。
他方で前章までは、「組織」「組織・市場を構成する個人」への深い洞察は行われなかった。組織が抱える構造問題の本質は何か、組織・個人がビジネス取引で直面する課題は何か、そもそも企業組織はなぜ存在するのか…このようなSCP・RBVでは説明できない深い疑問に答えるのが、組織の経済学である。
この分野は1980年代頃から経済学者がゲーム理論という数理ツールを応用し始めたことで飛躍的に発展し始めた(ゲーム理論は、本書第8章・9章で解説する。ただし、本書での組織の経済学やゲーム理論は、数学を使わずに日本語で解説する)。経済学ディシプリンの仮定する「人はおおむね合理的に意思決定をする」という前提を崩さないまま、組織の複雑なメカニズムを次々に解き明かすようになったのだ。本書はその知見をわかりやすく説明し、読者の皆さんが腹落ちすることを目指す(※3)。
本書『世界標準の経営理論』では、なかでも経営理論として昇華しつつある「情報の経済学」(本章)、「エージェンシー理論」(第6章)、「取引費用理論」(第7章)を、順に紹介する(※4)。これらの理論は、前章まで依拠してきた古典的な経済学が仮定する人間の意思決定の条件を、より現実に近づけるために2つの面で修正することが出発点になる。
第1に、組織・人のビジネス取引・やりとりにおける「情報の非対称性」(詳しくは後述)を出発点にするのが、前者2つの理論である。特に、取引・やりとりの前に起きる問題を扱うのが情報の経済学で、実際に取引・やりとりが始まった後の問題を扱うのがエージェンシー理論だ。第2の修正点は、人の意思決定に「限定された合理性」(詳しくは第7章で紹介)を持ち込むことである。これによって「組織とは何か」の本質に迫るのが、取引費用理論である。
出発点は、やはり完全競争を崩すことから
先にも述べたように、前章までのSCP・RBVは、経済学のベンチマークである「完全競争の4条件」からの乖離が根底にあった。そして今回紹介する「情報の経済学」も完全競争の条件が出発点である。しかしここでは、これまでの4条件ではなく、「第5の条件」に着目する。第1章でも軽く触れたその条件は、以下のようなものだ。
条件5-ある企業の製品・サービスの完全な情報を、顧客・同業他社が持っている。
この条件は「完備情報」(complete information)と呼ばれる。本書ではここまで注目してこなかったが、完全競争が成立する上では重要な条件(※5)だ。
例えば、皆さんがテレビを買おうと家電量販店へ行くとしよう。そこでは高級品メーカーA社の新品のテレビが20万円で売られており、同じサイズのB社のテレビは10万円で売られている。さらに、皆さんは「一般にA社製品の方がB社製品よりも質が高い」という情報を持っている。また、画質・音質・録画機能などのスペックも提示されているので、それらを比較しながらA社のテレビはB社のテレビよりも10万円高い価値があるか検討できる。さらに、その量販店の提示価格が妥当かどうかも、近所の別の店と比較すればよい。すなわち、その製品の特性・店の情報を消費者がほぼ完全に手に入れられる、完備情報に近い状態だ。
しかしこのような状況は、現実のビジネス取引の多くに当てはまるとは限らない。実際のビジネスでは、提供される製品・サービスの質や取引相手の情報が完全にわからないことも多いからだ。するとどのような事態が起きるのか、これを有名な「アカロフのレモン市場」の例を使って説明しよう。