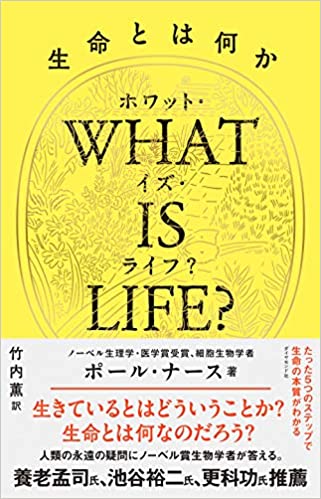本書の「凄み」とは?
ポール・ナースは、1970年代に酵母を用いた研究を始め、不断の努力と偶然の幸運が衝突した先で、あまねく生物に共通する「細胞周期のしくみ」の一端を解き明かし、21世紀最初のノーベル生理学・医学賞を受賞する。時代に輝く遺伝子「cdc2」の命名秘話――「もっとエレガントな、もっと覚えやすい名前をつけておけばよかった、テヘペロ」。
おやおや、ずいぶん謙虚だなあ、と肩の力が抜けてしまう。いち科学者の「物語」が、竹内薫さんのカドのない訳出によって、やさしくも豊潤に描かれる。ほっこりしたのもつかの間、本書の「凄み」が加速し始める。私はここでふと気づいた。
――まだ半分も読んでいないのに、もうポール・ナースのノーベル賞研究が出てきてしまったぞ? じゃあ、この本の残りには、いったい何が書いてあるんだ?――
ポール・ナースは、自らがたどり着いた「ひとつの解」が、生命という巨大かつ複雑な方程式の単独解ではないことを、順を追って、慎重に、かつ楽しげに語る。ひとたび分解した因数を再びかけ合わせる。広大な系を俯瞰し、高難度の詰め将棋を解くように、じっくりと論を組み立てていく様は圧巻の一言だ。彼は本気で「WHAT IS LIFE? 生命とは何か」というバカデカクエスチョンに答えるつもりなのである。
「生命とは、物理的な法則に従うもので、化学的な反応によって支えられており、情報としての複雑さを有し……。」
わあっ、情報だ!「ステップ5 情報としての生命」で、心のドアが全開になる。脳内タイムラインがバズる。うれしくてしょうがない。記憶の中の科学少年が前のめりになって拍手をする。
トラッドなウェット(生物研究)系研究者が、ドライ(情報解析研究)の視点を盛り込んで、「生命とは何か」を総ざらいする姿勢に興奮する。そうだ、その通りだ、生命がcdc2だけで定義できてたまるか! ポール・ナースは取りこぼさない。自然淘汰と進化の理論を忘れず、「境界」を見逃さず、観念論的生命観と唯物論的生命観の二択に安易に嵌まることなく、巨人の肩の上に立って、「WHAT IS LIFE?」をスキマ無く包囲する。
彼が酵母への愛をも忘れていないのがいい。しみじみする。自らの出自にかんする、あっと驚くエッセイ的エピソードのキレ味の鋭さにも舌を巻く。ウェット系研究者じゃなくてウィット系研究者じゃないか(※この書評の中で一番うまいことを言いました)。ロックフェラー大学の学長まで務める知性とはこういうものなのか。鳥の視点と虫の複眼を併せ持つような視座だ。つまりは、蝶の目線。そうか、そうなんだ、ポール・ナースは蝶の目線でこの本を書いている。 生命の定義について、現時点での最適解がついに示された。記録を塗り替えられたエルヴィン・シュレーディンガーも満足だろう。巻末の訳者あとがき末尾に感じ取れる静かな自信。わかる。シッダールタ・ムカジーに匹敵する科学読本。予想は裏切り、期待は裏切らない。ダイヤモンド社は死ぬほど売ってください。
☆好評連載、関連記事
地球上の生命の始まりは「たった1回」だけという驚くべき結論
20億年前、ほとんどの生物が絶滅…「酸素の大惨事」の真相