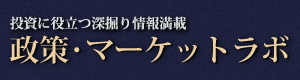広島の主要7カ国首脳会議が採択した首脳宣言にも盛り込まれたこの“デリスキング”は、対中経済関係で「重要なサプライチェーンにおける過度な依存を低減する」ことを意味する Photo:picture alliance/gettyimages
広島の主要7カ国首脳会議が採択した首脳宣言にも盛り込まれたこの“デリスキング”は、対中経済関係で「重要なサプライチェーンにおける過度な依存を低減する」ことを意味する Photo:picture alliance/gettyimages
イエレン米財務長官も訪中
対中国経済政策に変化あるのか
欧米を中心に対中国経済政策で、これまでの「デカップリング(切り離し)」に代わって「デリスキング(リスク回避)」が多用され始めた。
広島の主要7カ国首脳会議(G7サミット)が採択した首脳宣言にも盛り込まれたこの“新語”は、対中経済関係で「重要なサプライチェーンにおける過度な依存を低減する」ことを意味する。
米中間では、ブリンケン国務長官が対話チャンネルの維持を目指して6月に中国を訪れたのに続き、イエレン財務長官も訪中。7月7日の李強首相との会談では、「自国の安全保障のために的を絞った措置を取る必要がある」と述べる一方で、「誤解から二国間の経済関係を不必要に悪化させることになってはならない」と語った。
長官は現地の米ビジネス界との会合では、「2大経済大国のデカップリング(分離)は世界経済に不安定化をもたらす。(米国政府は)全面的な分離は求めていない」と述べた。
だがその一方で米中間では半導体などを巡り輸出規制の応酬が激しくなっており、中国側は「(デリスキングは)偽装されたデカップリングにすぎない」と反発する。
デリスキングは、本当に対中経済で実体を伴う関係を表す用語になるのかどうか。そのカギを握るのは、グローバルサウスだ。