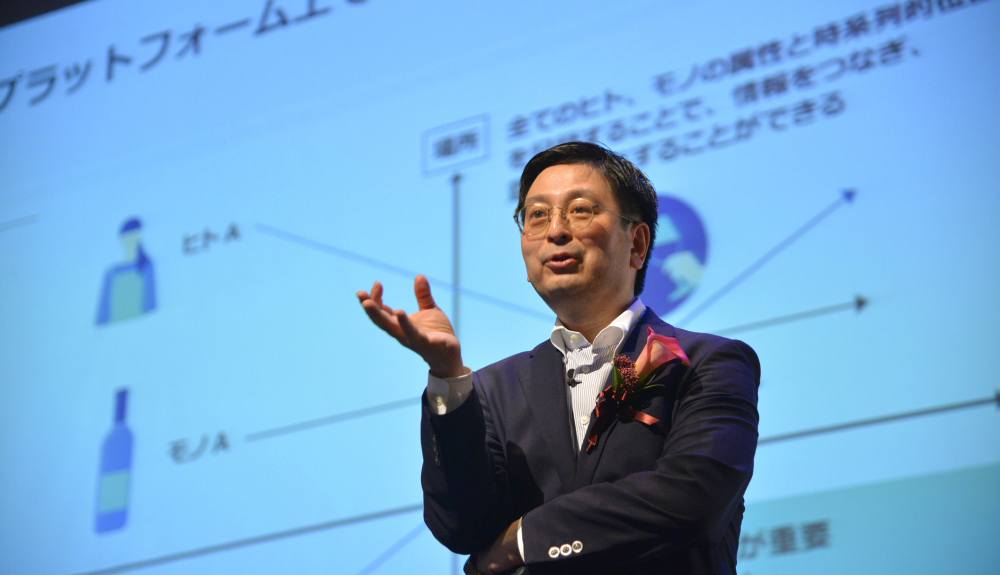 「QON DAY 2016」に登壇した慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎氏
「QON DAY 2016」に登壇した慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎氏
さまざまな消費者コミュニティについての実践報告が発表され、754名もの参加者が集まったクオン株式会社主催セミナー「QON DAY 2016」。そのなかで、慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎氏による基調講演がおこなわれた。著書に『ソーシャルな資本主義』『創発経営のプラットフォーム』などがあり、オープンネットワーク時代の新しい経済について考察・実証してきた國領氏。彼の考える、すべてのヒトとモノがつながる時代のビジネスモデル、そして社会の姿とは。
20世紀は「顔の見えない」
ビジネスモデルが主流だった
今日は「創発する企業と消費者の新たな関係」というテーマでお話しさせていただきます。まず、現代の経済は、情報化によってどうなったのか。それは、「データの集積がサービス価値を生み出す経済」です。いまや、クラウドのコンピュータを通じて、さまざまなデバイスがつながるようになってきています。ヒトがスマホやパソコンからアクセスするだけでなく、近年では家電などのモノがIoT技術によってつながり始めています。それにより、モノからも情報が集まってきます。それらの情報の集積が価値を生み出すということです。ヒトが発信するデータとモノから上がってくるデータが結合すると、ビジネスモデル、マーケティングのかたちも大きく変化するでしょう。
一体どのように変化するのでしょうか。それを考えるにあたり、20世紀のビジネスモデルについての前提を共有しておきましょう。19世紀半ばから急速に発達してきたマーケティングは、人間は「見えない」ということを前提としたモデルでした。つまり、大量生産したプロダクトを店頭に並べ、匿名のお客さんがそれを買っていく、ということです。アルフレッド・チャンドラーという経営史の学者が、「これは鉄道と電信が商圏を広げたことによって成立したモデルである」という説明をしています。生産地だけで消費するには量に限りがありますから、遠くに運んでたくさん売らないと、大量生産した製品はさばけない。そのため、鉄道の路線が全国に延びたことで大量生産・大量販売が可能になったのです。
それより以前は、その地域でつくったものを地域内で流通・消費していました。そこでは、フェイス・トゥ・フェイスの信頼関係が成立していたんです。でも、生産地から遠い土地で知らない人に売るとなると、その商品が安全なものか、価格に見合ったものなのかという信頼を、別のところで担保しなければ売れなくなります。それが「ブランド」です。どの会社がつくっているかということがわかるロゴを明示して、重さを正確に測ってパッケージし、定価を決めて、誰でも安心して買える状態をつくりました。
また、知らない人に売るならば、物々交換や「お金は後でいいよ」というわけにはいかなくなる。商品を手にとった人とは、二度と会わないかもしれないですからね。そうして、店頭で現金決済を完結する、という一連のモデルができてきました。
さらに、先ほどの「電信が商圏を広げた」という話は、広告の発展につながっています。20世紀初頭に出てきた電波メディアが、ブランドを強烈にお客さんに刷り込み、それをもとに商品を買うという行動が生まれた。これらの前提がもとになって、いま我々が当たり前だと思っているマーケティングが成立しています。







