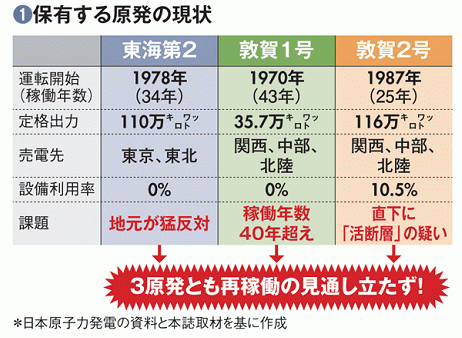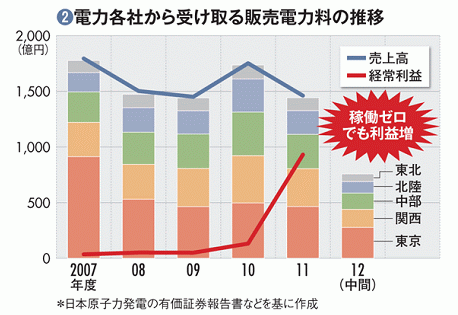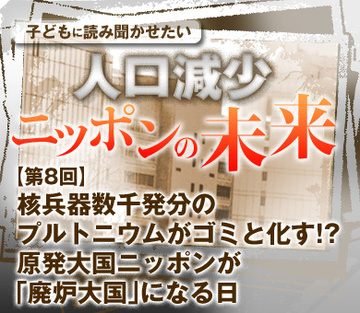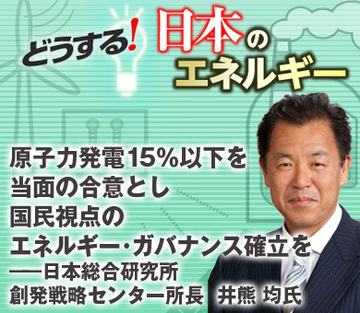保有する原発に活断層の疑いが指摘され、資金繰りの悪化が取り沙汰される日本原子力発電。同社の財務を読み解けば、電力業界全体がもたれ合ってきた原発の構図が浮き彫りとなる。
「電力各社の原子力事業の発展に重要な日本原電を支えたい」
3月16日、電力会社9社で組織する電気事業連合会の八木誠会長(関西電力社長)は、資金繰りに苦しむ日本原子力発電を支援していく姿勢を明確に打ち出した。
日本原電とは1957年に東京電力、関西電力をはじめとする電力9社と、電源開発(J‐POWER)の出資で設立された原発専門の卸売事業者である。もっぱら原発で発電した電気を電力会社に売り、収益を上げている。
だが、現在はその収益源である全3基の原発がいずれも停止しており、再稼働の見通しが立っていない(図(1))。東海第2原発は地元が再稼働に反対しているほか、敦賀原発1号機は稼働年数が40年を過ぎ、民主党政権下で決まった制限年数に抵触している。
さらに2012年12月に、原子力規制委員会が敦賀2号機の真下を走る断層を「活断層の可能性が高い」と指摘し、2号機の廃炉の可能性が取り沙汰されている。
通常、唯一の収益源がなくなれば、売り上げが立たなくなると想像するだろう。だが、原電の場合はそうではない。
東日本大震災直前の11年1月に敦賀1号機、5月に敦賀2号機、東海第2がそれぞれ定期検査入りし、そのまま運転停止となった。このため、12年度中間期の「販売電力量」はゼロにまで落ちた。だが、収入となる「販売電力料」の項目を見ると、11年度通期でも1443億円の安定収入が得られているのだ(図(2))。
発電がゼロ、にもかかわらず収入は安定している──。奇妙な現象だが、携帯電話の月々の支払いに例えると、毎月定額で徴収する「基本料金」と、月々利用した程度に応じて変わる「通話料」の2階建ての仕組みだという。こうして原電は東電をはじめとする電力5社から、設備維持名目などで震災以後もほとんど変わらない収入を得られている。