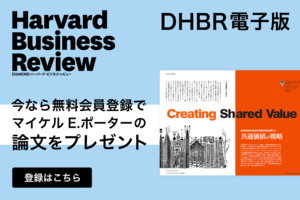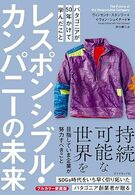──前回の記事:「ポーターの戦略」の根底にあるものは何か(連載第14回)
寡占はなぜ儲かるのか
SCP理論の前提を踏まえて、さらなる解説に入ろう。ここで覚えていただきたい名前が、カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)教授のジョー・ベイン、ハーバード大学教授のリチャード・ケイブス、そしてマイケル・ポーターである。
余談だが、この3人は言わば師弟のような関係にある。ケイブスはハーバード大学でPh.D.(博士)を取得した後、学者としてのキャリアをUCバークレーでスタートさせ、そこで当時「経済学のSCP」を発展させていたベインと共同研究を行っている。その後ハーバードに戻ったケイブスの薫陶を受けたのが、ポーターだった。
まず、ベインによる「経済学のSCP」から始めよう。これまで述べたように、「ある産業が完全競争から離れるほど(=独占に近づくほど)企業の収益率は高まる」というのがSCPの根本だ。「独占に近い」とは、少数の企業に売上げが集中しているということである。これは「寡占」と呼ばれる状況だ。
「寡占は独占と違い、少数でもライバル企業が同じ産業にいるのだから、複数社で競争すれば各企業の収益性は低下するのではないか」と考える方もいるだろう。たしかにその可能性はあるのだが、それに対してベインは、「寡占産業では企業数が少ないので、1社の行動が他社の行動に影響を及ぼしやすい」という点に注目する。
例えば、A、B、Cの3社だけが市場を占有している産業で、A社が製品価格を大幅に引き下げたら、B社とC社も対抗するために価格を引き下げるのが一つの「合理的な判断」になる。するとA社はB社・C社に対抗するため追加で価格を下げるだろう。そして、それはB社・C社のさらなる値下げにつながる。この状況が進みすぎると、業界は「極度の価格競争」に陥ってしまう。
しかし逆に言えば、この状況を見通したA社が十分に合理的なら、「価格を引き下げない方が賢明」と判断するはずだ。B社とC社も同様だ。結果として、合理的なA社、B社、C社とも価格を引き下げないので、業界は価格競争に陥らず安定した収益を保つことができる(小さい企業が無数に存在する完全競争では、1社の行動が他社に影響を及ぼさないので、この状況は実現しない)(※1)。
もちろんこの行動は、競争法の範囲内で行われなければならない。しかし、この「暗黙の共謀」(tacit collusion)で特徴づけられる業界は現実に多くある。食品関係業界はその特徴が顕著かもしれない。例えば大手4社の寡占状況にある日本のビール業界では長年大幅な値下げ競争が起きず、結果的に各社の収益性は比較的安定していた。米国のシリアル業界も同様だ。コーラ業界はペプシとコカ・コーラの2強が、互いに価格競争を仕掛けないことで高い収益性を保っている。
この仮説を実証して「経済学のSCP」を切り開いたのが、ベインが51年に経済学の学術誌『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』(QJE)に発表した論文だ(※2)。この研究では36年から40年の米国42産業のデータを使い、寡占度が高い市場ほど、企業の平均利益率が高くなる傾向が示されている。