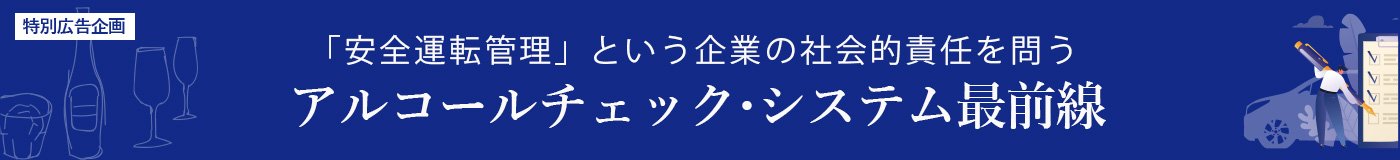一般社団法人
一般社団法人計測健康啓発協会(AHAM)
望月 計代表理事(博士・工学)
飲酒運転による悲惨な事故をなくすため、改正道路交通法施行規則が施行されたのは、2023年12月。従来、アルコール検知器による酒気帯びの確認は「緑ナンバー」(運送)事業者だけに義務付けられていたが、それが一定台数以上の「白ナンバー」車を使用する事業者にまで広がったのだ。
具体的には、乗用車5台以上または乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所ごとに1人の「安全運転管理者」を選任し、運転者の状態を目視で確認するほか、国家公安委員会が定めるアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器)を用いて確認することが義務化された。
交通安全教育などの指導や、運転者に対して飲酒・過労・病気などにより、正常な運転ができない恐れの有無を確認し、安全な運転の確保のために必要な指示などを行わせることにしたのである。
法改正の契機は、21年6月、千葉県八街市で児童5人が死傷した「白ナンバー」車による飲酒運転事故だ。「再発防止のため、警察庁は翌22年4月から『白ナンバー』事業者にもアルコールチェックを義務付けることを発表しましたが、2度先送りされ、23年12月にようやく改正法が施行されました」。
そう説明するのは、アルコール問題啓発活動や子どもたちへの熱中症啓発活動などに取り組む一般社団法人計測健康啓発協会の望月計代表理事である。
世界的な半導体不足でアルコール検知器の製造が追い付かず、事業者側の準備が整わないことなどが延期の要因だった。国内メーカーが増産体制を整え、輸入品も増えた結果、改正法が、ようやく施行された。「ただし、現在、市場に出回っているアルコール検知器の中には、精度や信頼性に欠けるものも含まれています。きちんと計測できるかどうかを確かめて選んだ方がいいでしょう」(望月代表理事)