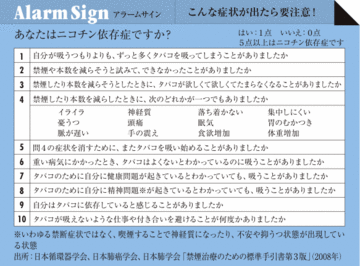「病院は生活の場」か?

病院は暮らしの場だろうか。病院に長く滞在したいだろうか。入院期間はできるだけ短く、と言うのが普通の人の普通の思いではないのか。ところが、病院の運営者はどうも違うらしい。そんな疑問が湧いてくるような「事件」があった。
10月31日に厚労省が開いた公開ヒアリングの場である。テーマは受動喫煙防止対策。その「検討チームワーキンググループ」が関係業界を呼んで実態や要望を聞いた。受動喫煙とは、他人のたばこの煙にさらされること。肺がんの原因とかねてから言われていた。だが、実はほかの病気のリスクも高い。
厚労省は8月31日に改定した「喫煙と健康(たばこ白書)」で病気と受動喫煙の関係を4段階で表わした。最も因果関係の高い「レベル1」に多くの病気が並ぶ。肺がんの他に心筋梗塞などの虚血性心疾患をはじめ脳卒中、乳幼児突然死症候群、鼻への刺激症状である。
「レベル1」というのは「因果関係を推定するのに十分な科学的根拠がある」ものだ。厚労省の調査では、受動喫煙による年間死亡者のうち、肺がんは2484人なのに対して脳卒中は8014人、虚血性心疾患は4459人に及んでおり、他の病気の方が多い。受動喫煙が原因の全死亡者は1万5030人に達している。
「レベル2」の段階での病気は、乳がん、気管支ぜんそく、鼻腔・副鼻腔がん、慢性閉塞性肺疾患、胎児の発育遅延、低出生体重児、小児の中耳炎や虫歯と多岐にわたっている。レベル2は、「因果関係が科学的に疑われる」もので、レベル1ほど科学的証拠が十分ではないが関係がありそうだ、というグループである。
こうした実情を受け、その防止対策を強化する法案作りに入るため、厚労省が病院や飲食業、大学、ホテル、麻雀など10団体を集めた。そこで、話された病院団体の代表の考え方に驚いてしまった。
日本の療養病棟や精神科病棟は平均入院日数が欧米よりかなり長いことを強調し「こうした病院は生活に近い環境になっている」と指摘、従って生活しているのだから「病院の敷地内を全面禁煙にするのは現実的ではない」と述べたと言う。要望として、例外や経過措置を設けて弾力的な規制を求めた。
いったい、「病院が生活の場」であるとはどういうことなのか。長く入院しているから「生活の場」になっている、と当然のように話す。おかしな話だ。誰一人として病院が日常の暮らしの場であってほしいとは望んでいないはずなのに。厚労省が高齢者ケアの理念として掲げた「地域包括ケア」は、高齢者だけでなく、将来的には国民全体が目指すべき方向でもある。
住み慣れた地域でできるだけずっと長く暮らし続けましょう、遠くの病院には頼らない生活が一番です――そのために地域包括ケアに取り組む、ということだ。厚労省が当初示した地域包括ケアの説明は「病院等に依存しない住み慣れた地域で在宅ケアの限界を高める」ということだった。海外では、同じ内容を「Aging in Place」と呼んでいる。
もともと病院は、緊急の避難先であったはずだ。健康を害した人たちが一時的に訪れたり、滞在するところ。「避難所」であり「仮設住宅」に近い。自然災害に襲われた地域住民が自宅で過ごすことが出ないのでやむなく一時的に移るのが「避難所」であり、長期に避難せざるを得ないから「仮設住宅」で日々送る。いずれ自宅に戻るのが大前提だろう。本来の暮らしの場ではない。
つまり、病院に長期に滞在しているという現象が本来のあり方ではないはずである。長期入院をいかにしてやめるかと言う議論があり、取り組んでいる最中なのに、長期入院を固定させるかのような発想に疑問を抱かざるを得ない。