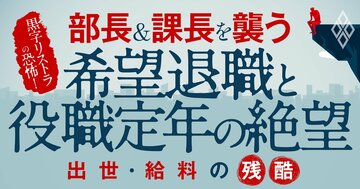英語メディアが伝える「JAPAN」なニュースをご紹介するこのコラム、今週も引き続き原発事故と日本の復興についてです。原発事故当初、日本政府の報告は事態を過小評価しているのではないかとアメリカ政府が懸念していたという話は、先週ご紹介しました。今週は、イギリス政府もかなりの最悪事態を想定していたという話です。そのほか、米軍が「トモダチ作戦」を未来の放射能テロ対応の参考になると考えているという話や、日本復興のカギは地方にあり!という記事なども。(gooニュース 加藤祐子)
最悪を想定しつつ「落ち着いて」と
のっけから言い訳ですが、本当なら今日は久々に地震以外で英語メディアを賑わせた日本関連のニュースをご紹介するのがいいと思うのです。2位を目指すのではダメだと言われた日本のスーパーコンピューターが7年ぶりに世界一になったという、久々のおめでたいニュースなので。ただしスパコン世界一について「めでたい」「すごい」以上の感想を書く知識が私になく、これ以上の掘り下げができません。なので、また原発の話を書きます(原発について詳しい知識があるわけでもないですが)。
先週のコラムで、 (当時から分かっていたこととは言え)原発事故発生当時のアメリカ政府が、日本政府の説明よりはるかに深刻に事態をとらえていたことに触れました。それゆえの「原発80km圏退避勧告」だったわけです。それに続いて今週は、イギリス政府も実は「チェルノブイリ以上」という最悪事態を想定して自国民の安全対 策を策定していたという記事を見ました。
英紙『ガーディアン』の20日付記事によると、同紙は情報公開法にもとづき独自に情報開示を請求。公開されたのは、イギリス政府の「危機に関する科学的助言部会(SAGE)」が事故直後にまとめた「最悪のシナリオ」の内容でした。SAGEは、福島第一原発にあると推測される燃料棒や使用済み燃料の量などをもとに計算。稼働中の3つの原子炉と6つの使用済み燃料プールから放射能が大量放出される最悪の事態になったら、チェルノブイリ事故の倍近い放射性物質が放出されるかもしれないし、その一部が東京に到達したらどうなるか、その場合でもチェルノブイリよりも被害は少ないだろうなどと英国政府が想定していたことなどが、明らかにされています。
(福島第一の事故も「レベル7」と判断された時に、「でもチェルノブイリとは違う」とイギリスなど複数の専門家が話していたのは、こちらのコラムで当時まとめました)
3月の当時、イギリス大使館が何を発表し、自国民にどう説明するかは私もネットや友人を通じて注視していたので、この記事を読んで「やっぱりなあ」という思いがこみあげてきました。イギリス大使館は他の複数の外国大使館のように大使館機能を関西に移したりせず、「最悪の事態にならなければ東京は大丈夫」、「最悪の事態なる可能性はきわめて低い」という説明を繰り返していました。そのため「イギリスは、大丈夫だと言ってる」という印象がずいぶんと日本人の間で(Twitterなどを通じて)安心材料として広まったものです。
ただしその一方で英外務省は3月16日の時点で、 「これは命令ではない」、「30km圏の外で健康に影響が出るという科学的知見はない」「東京で深刻な健康被害が起きると考えているなら、ただちに脱出するようもっと強い調子で言っている」と念入りに断りを入れつつも、「福島原発で推移中の事態に加え、物資や交通、通信や電力などインフラの混乱も鑑みて、いま東京や東京の北にいる英国民は、退避を検討するべき」と勧告しています。「念のため」60km圏内への渡航自粛を呼びかけ、「いざという時のため」として自国民には(都内でも)ヨウ素剤を配布していました。
要するに、典型的にイギリス政府的な対応だったわけです。あっちも抑えるがこっちも抑え、最悪を想定しつつも今は最悪事態ではないと落ち着かせ、そして各自が自分で判断するよう促すという。「バランス」を重視するのがイギリスのイギリスたる所以ですし、ジョージ・オーウェルの『1984』を生んだのもイギリス。第二次世界大戦中の標語が「Keep calm and carry on (落ち着いていつも通りに行動して)」だった国です。
さらに『ガーディアン』記事には、日本人として気になるくだりが。いわく公開を請求したが認められなかった文書が相当数あり、公開しない理由は「もし公開すれば国際関係に悪影響をもたらす」からだと政府関係者に言われたと。
えー と……(苦笑)。「国際関係」って、どことどこの国際関係でしょうね。先週書いたように、事故当初の日米関係は危機的状況だったという関係者の証言が出てきているのですが。日本政府による情報提供が不十分で、対応が後手後手に回っているとオバマ政権は危機感を抱いていたので、あの手この手で日本政府に圧力をかけていたと。日米関係がそうなっていた同じころ、日英関係はどうなっていたのでしょう……。
(続きはこちら)