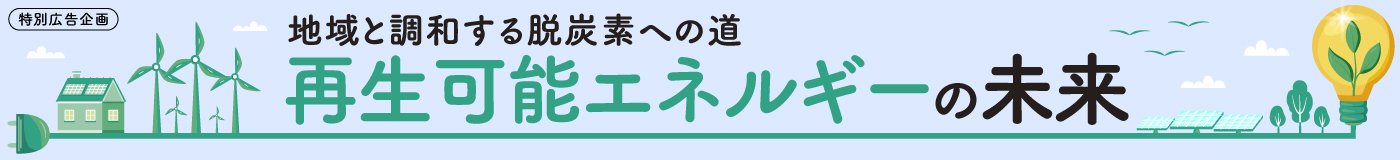世界的な脱炭素の潮流の中、日本でも再生可能エネルギー(再エネ)の導入が進められている。欧州諸国に比べると遅れが目立つが、東日本大震災を機に固定価格買い取り制度(FIT)が導入され、太陽光発電を中心に再エネ比率は拡大してきた。現在、日本の電力に占める再エネの割合は約2割。政府は2040年までにこれを4~5割に引き上げる方針だ(※)。
「経済産業省が石炭火力の休廃止を進める中で、再エネの役割はこれまで以上に大きくなっています」と語るのは、環境社会学や社会的合意形成を専門に研究する名古屋大学の本巣芽美特任准教授だ。
第7次エネルギー基本計画より、今後日本では「太陽光と洋上風力の拡大が見込まれる」と本巣特任准教授は話す。
一方で、再エネ拡大には地域との関係性が大きく関わってくる。太陽光発電は森林伐採や景観への影響、洋上風力は漁業との調整、陸上風力は騒音やバードストライクなど、地域から懸念の声が上がることも少なくない。
本巣特任准教授が行った陸上風力発電に関する住民調査では、法令の基準を満たしていても、「風車の音が気になる」という声が寄せられた。「課題は数値の正しさではなく、感じ方の違いをどう受け止め、向き合うかです」。
成功事例もある。ある洋上風力発電プロジェクトでは、事業者が漁業者と対話を重ね、漁業への影響調査や電力の地産地消、地域還元の基金創設など、地域がメリットを実感できる仕組みを構築した。「ただし、お金で気持ちを買うことはできません。信頼がなければ、むしろ逆効果になることもあります」と本巣特任准教授はくぎを刺す。
こうした背景にあるのが、「再エネの社会的受容(Social Acceptance)」という考え方だ。「これは新しい技術や政策を社会が受け入れる過程を示す概念で、再エネでは三つの層に分けられます」と本巣特任准教授。
一つは「社会・政治的受容」(国民や政策決定者による支持)、二つ目は「市場的受容」(投資家や企業にとっての妥当性)、そして三つ目は「地域的受容」(地域住民や自治体による受け入れ)。このうち「地域的受容」では、手続き的公正、配分的正義、そして信頼の3要素がそろって初めて、地域との共生が実現できるという。
制度面での動きも進んでいる。
例えば宮城県では、一定規模の森林開発を伴う再エネ事業について、地域との協調が確認された場合には課税しない「再生可能エネルギー地域共生促進税」を導入した。「抑制ではなく促進を目指す設計は、地域との共創を志向する点で注目しています」と本巣特任准教授は話す。
また、地域と再エネの在り方を議論する場に、SDGs教育を受けた若い世代の参加を促すことも提案する。短期的な利害よりも持続可能性に目を向ける若者たちの視点が、未来志向の対話を進める原動力になると期待されるからだ。
再エネは単なるインフラ整備ではなく、地域と共に築く「共創のプロジェクト」なのである。
※出所:自然エネルギー財団「電源構成国際比較」/経済産業省「第6回 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会」資料/経済産業省「エネルギー基本計画」関連資料