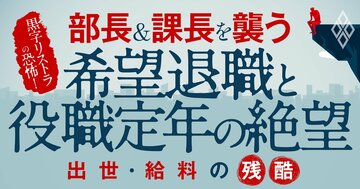脳腫瘍は診断と治療技術の進歩にもかかわらず予後が厳しいがんの一つだ。外科的手術が有効なのは他の臓器がんと同じだが、問題は「脳」という場所にある。「特に神経細胞と神経繊維のあいだを埋める“グリア細胞”から発生する腫瘍(グリオーマ)は周囲の正常組織との境界が曖昧で、全部摘出するのが難しい」(脳神経外科医)のだ。これが他の臓器がんなら、いわゆる「安全域」をとって周囲の正常組織を切り取り、再発防止に努めることができる。しかし脳の場合、腫瘍の位置によっては言語機能などを損なう恐れがある。このため、正常組織をできる限り傷つけないように、腫瘍の全摘出を諦めることもある。当然だが、再発率は高い。
いかに、正確かつ安全にすべての腫瘍を取り除くか、という難題に光が差し込んだのは1990年頃から。腫瘍を目立たせるために、がん細胞だけに集まりやすい光感受性物質──特定の波長の光に反応し蛍光色を発する──を投与し、手術中に位置を確認しながら腫瘍を摘出する「光線力学的診断法(PDD)」が開発されたのだ。執刀医は術中に正常組織と腫瘍との境界を確認しながら、腫瘍を正確に摘出できる。
日本では、これに使われる光感受性物質「5-ALA」が薬事法未承認のため、先進的な病院の臨床研究にとどまっているが、海外では臨床応用が進んでいる。