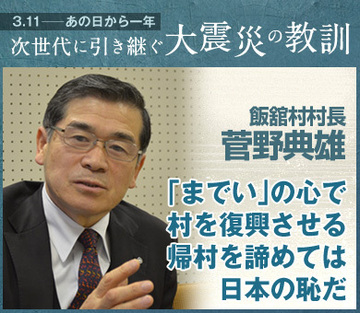あの日から大きな変化がない
「津波街道」のいま
 仙台から青森までの海岸線を走る国道45号線は、数々の津波被災した街を通る「津波街道」だ(2011年11月24日、宮古市田老)
仙台から青森までの海岸線を走る国道45号線は、数々の津波被災した街を通る「津波街道」だ(2011年11月24日、宮古市田老)Photo by Yoriko Kato
三陸の海岸線を走る国道45号線を行くと、数々の津波の被災地が現れる。仙台、多賀城、塩釜、東松島、石巻、気仙沼、陸前高田、大船渡、釜石、大槌、山田町、宮古、野田村、八戸。国道から少し入れば、閖上、七ヶ浜、牡鹿、女川、南三陸などもある。仙台から青森にかけてのこの45号線を、いつしか私は、ひそかに「津波街道」と呼び始めたくらいだ。
それぞれの町や集落に行くたびに、津波に破壊された景色の中の変化を探してしまう。どこも、すぐに気づくような大きな変化などは、ない。見つかるのは、「あの建物が解体された」「信号が点灯した」「道路が通れるようになった」「バス停が復活している」といった、点のような小さな変化だ。
 石巻南浜町。住宅地だった街に、がれきの山脈が連なる。震災廃棄物の量は、同市の一般廃棄物の106年分といわれ、この光景は、震災から1年経った今も全く変わらない(2011年9月11日、石巻市南浜町・門脇町)
石巻南浜町。住宅地だった街に、がれきの山脈が連なる。震災廃棄物の量は、同市の一般廃棄物の106年分といわれ、この光景は、震災から1年経った今も全く変わらない(2011年9月11日、石巻市南浜町・門脇町)Photo by Yoriko Kato
こうしてヨソ者としての目線を向けながら感じているのは、東日本大震災から1年経った被災地は、日々の衣食住が足りて表面的には落ち着いている、という印象だ。人々はいま、仮設住宅を拠点に、暮らしに適応しようと奮闘している。
津波災害現場の復旧・復興の進み度合いは、場所によってまだら模様であるとも思う。釜石や気仙沼には、解体できない建物が、いまだに街の中に連なる。がれきの仮置き場が満杯で、壊したくても壊せないのだそうだ。
被災地の人々がいつも目にせざるを得ない範囲に、進展の見られない光景がたくさんある。がれきの山脈が延々と連なっていたり、生活道路が、砂利で応急的に盛り土しただけのままだったりする景色を、「もう何とも思わなくなってしまった」という人がいる一方で、「見るのも辛い」という人もいる。こういった物理的な処理の遅れが、被災者の心の中に、復興の立ち遅れたイメージを初期段階から定着させてしまう。