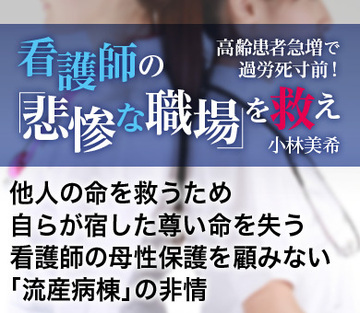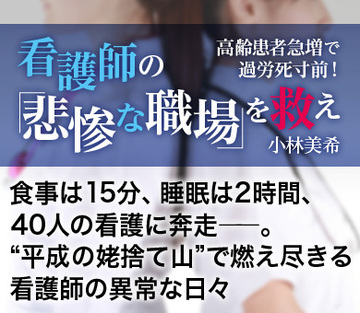過酷な夜勤にはもう耐えられない――。
病院から姿を消した看護師の日常生活
「あまりに過酷な夜勤に耐えられなくなった」
都内の有名民間病院で働く看護師の大木智子さん(仮名・29歳)は、夜勤の多さに心身のバランスを崩し、こう言い残して病院から姿を消した。
高齢患者で溢れる病院で、看護師たちは恒常的に多くの夜勤をこなしている。企業戦士のなかにも「徹夜は当たり前」という人はいるだろうが、看護の現場における夜勤のきつさは、おそらくその比ではなかろう。過酷な「夜勤の無限ループ」のなかで、体を壊す看護師が続出しており、病院を辞める者も少なくない。それがさらなる人手不足と夜勤の増加を招くという悪循環を生み出している。
その1人である智子さんは、勤務先の病院から去らざるを得なくなるまで、いったいどんな日常生活を送っていたのだろうか。
智子さんの看護師としてのスタートは、内科と外科の患者が混在する病棟への配属だった。当初の月給は額面で17万円。業務に慣れない新人は最初の半年は夜勤に入ることができず、しばらく基本給のみの収入が続いた。
病院の寮に住んでいたからこそ、やっていけた。勤務帯は3交代制で、日勤(8時30分~17時30分)、準夜勤(16時30分~1時)、深夜勤(0時~翌8時30分)のシフトの組み合わせ。入職して半年後、夜勤に入るようになった。
夜勤では、看護師たった2人で40人を看る。寝たきりの患者や外科の重症患者がベッドから起き上がって転倒すれば骨折してしまい、頭を強く打てば死亡事故につながりかねないため、気が抜けない。
転倒予防のため、患者の足もとには「待った君」「転倒虫」などと呼ばれるセンサー付きのマットレスが敷かれ、患者の体重がかかると大きなブザーが鳴る。
夜中はあちこちでブザーが鳴るため、その度に看護師は走って駆けつける。その間に、オムツ交換、点滴のチェックなど患者のケアをしていくため、仮眠はほとんどとれない。救急搬送で入院患者が来れば、1人はその準備や手続きに回り、夜勤は事実上1人ということもある。
そうしたなかでナースコールが鳴り、患者に呼び止められても「ちょっと待ってね」と言ったきり、なかなかベッドサイドに行くことができない。