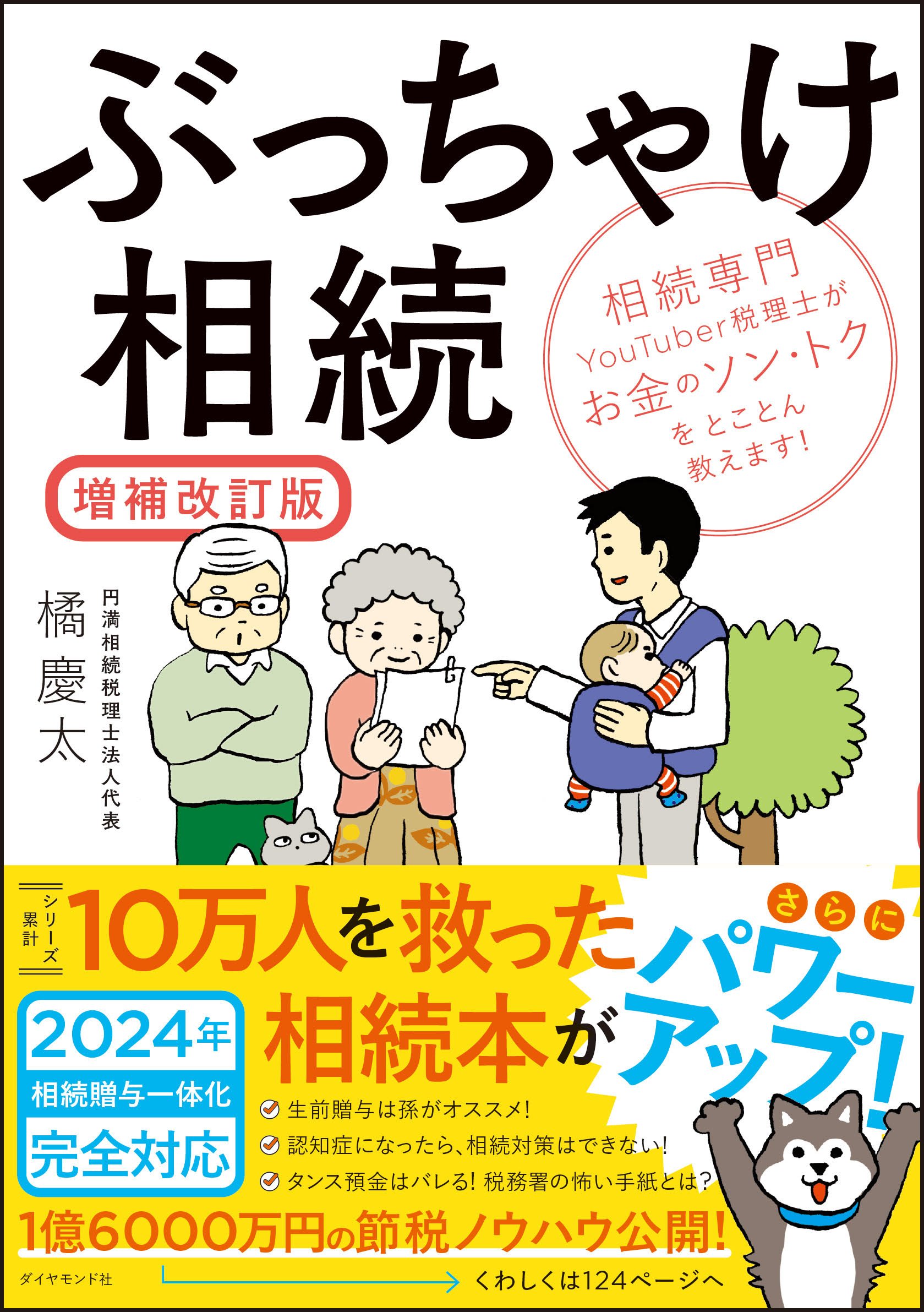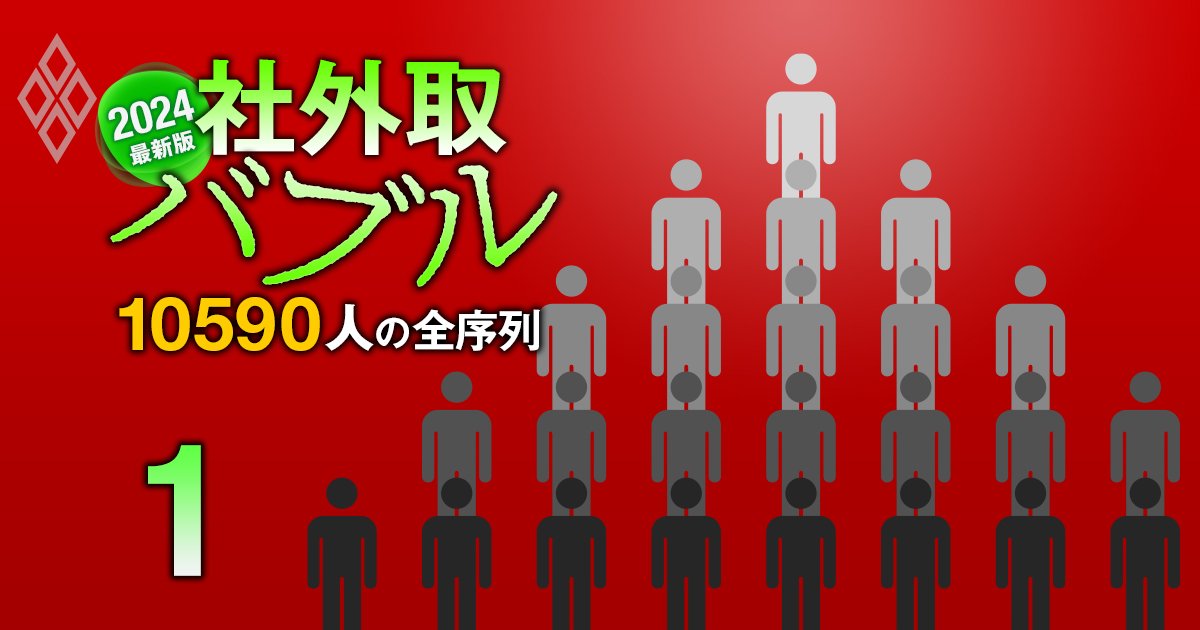人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
相続税を1円でも減らすには?
贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。
暦年課税制度とは、普段からよく聞く、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。2024年からは、持ち戻し期間が7年になります。
※持ち戻しについては、前回記事『「110万円を超える贈与」が税務署にバレる理由【生前贈与の超基本】』を参照
相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。
暦年課税制度と相続時精算課税制度、どちらを使うべき?
先に結論をお伝えすると、2024年1月1日以降は、多くの人が相続時精算課税制度を選択したほうが有利といえます。整理すると次のようになります。
相続時精算課税制度が有利になる人
・元々相続税のかからない人や、相続税はかかるが少額である人(現行税制において年間110万円までの贈与が最適解である人)
・7年以内に亡くなってしまうことを心配する人
暦年課税が有利になる人
・相続税が多額にかかる人(現行税制において年間110万円を超える贈与が最適解である人)のうち、7年超、亡くならない自信のある人
現行税制において、年間110万円での贈与が最適である人とは、その人が所有する財産額と、相続人の人数で決まります。
例えば、相続人が配偶者無し、子ども2人の場合には、相続税の対象となる財産がおおよそ7000万円(小規模宅地特例などを使った後の金額)を超える場合には、110万円を超える贈与をして、贈与税を先に払ったほうが有利になります。
ただ、このあたりの見極めは、遺産の分け方や正確な土地評価額が決まっていないと結論を導き出せないため、相続税に強い税理士に相談の上、最終的に判断しましょう。
また、7年後も絶対に生きている自信のある人は、そう多くはないと思います。確実に年間110万円までを非課税にできる相続時精算課税制度を選択したほうが賢明と言えるでしょう。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)