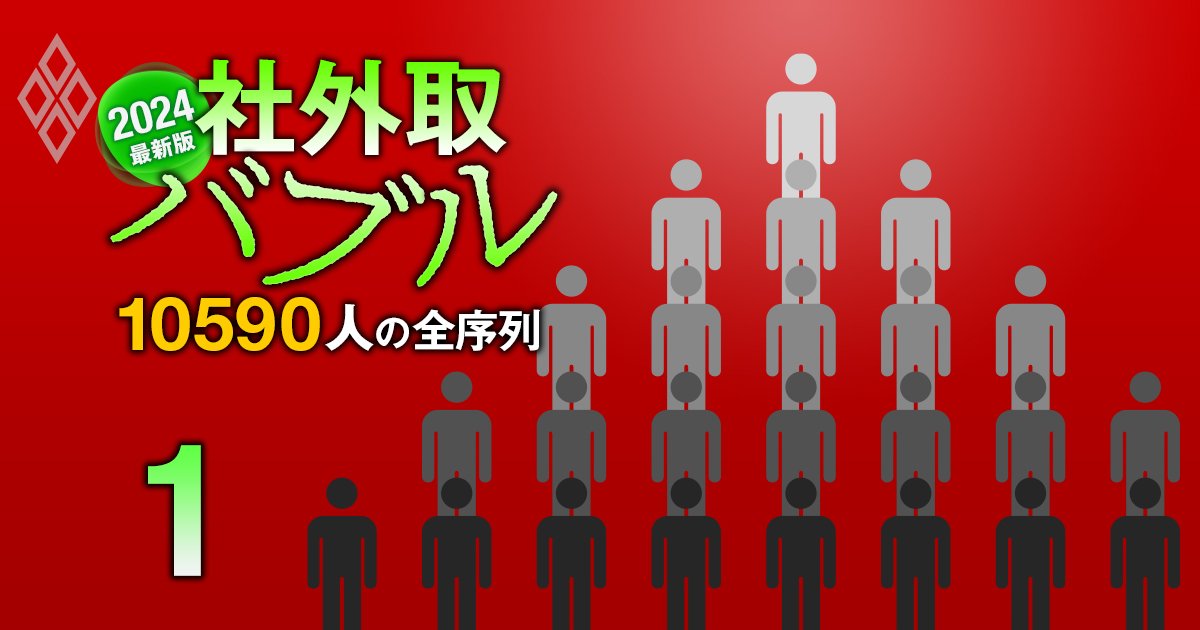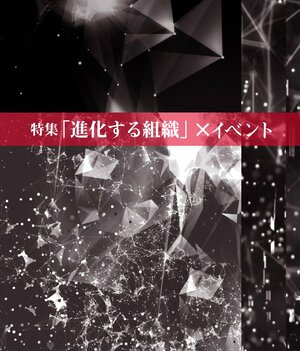相互の信頼関係を高めて
組織内の意思統一を図るには
2つ目に「組織における意思統一のあり方」を取り上げましょう。
『失敗の本質』では、指揮系統の中での意思伝達における日本軍の失敗を指摘しています。上で述べたようにミッドウェー海戦やレイテ沖海戦では、上層部と現場指揮官の間で目的に関する理解が一致していなかったことが、戦略的失敗につながったと示されています。インパール作戦でも、現地のインド進攻を目的とする部隊と、ビルマ防衛を主目的とする上級司令部との間で理解の不一致があったにも関わらず、その不同意が上層部から明確に伝えられずに作戦が失敗しています。
一方米国は、ニミッツ長官と部下の現場指揮官・スプルーアンス少将が、ハワイで住居をともにして価値や情報、作戦構想の共有に努めていたといいます。スプルーアンス少将も参謀と、空母「エンタープライズ」の甲板上で散歩をしながら長時間にわたって議論を重ね、相互の信頼関係を高めていました。そして作戦計画についての検討を進めると同時に、価値観の統一を図ったといいます。
戦後日本の企業組織を見ると、昭和の高度経済成長期には社員を家族のように親密に扱う会社も多く、社員旅行や運動会などを通じて価値観の共有を図っていました。今でもそういう企業もありますが、現代の日本ではワークライフバランスの重視やハラスメント教育など、昭和時代の問題点を見直そうという動きが強くなっています。昭和の悪しき習慣を一掃したのはよいのですが、組織内でのオープンなコミュニケーションも同時に取りづらくなり、意思疎通や価値観の統一が図れなくなるケースも増えているように思います。
もちろん、必要以上のウエットさはむしろ敬遠されますし、部下のプライベートに踏み込みすぎるのも良いことではありません。ただ、それなら新しい時代に合わせたチームビルディングや1on1ミーティングなどの手法を試すなど、上司と部下との間で意思統一を図る方法があるのではないでしょうか。