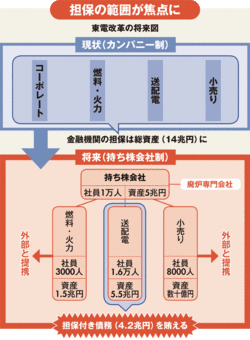東京電力の再建計画がようやく動きだした。これまでの「生かさず殺さず」のスキームを見直し、国の責任も明確化される。代わりに東電は“解体”を迫られるが、道のりは険しい。
猛暑の後のつかの間の秋から、一気に肌寒さが増した11月上旬、経済産業省の官僚が首相官邸や議員会館、内閣府など関係各所に精力的に足を運ぶ姿があった。
目的は、東京電力の再建策である「総合特別事業計画」の見直しに向けた根回しだ。
東電は、昨年春に実質国有化されたものの、福島第1原子力発電所の廃炉や賠償、除染の費用がいずれも兆円単位に上ることから、再建スキームが立ち行かなくなっていた。その見直しに向けた作業が水面下で進んでいたのだ。
事態が一気に表面化したのが、10月末に自民党の復興加速化本部が公表した第3次提言だ。除染については復興の一部として国費投入を求める一方、対応が後手になっている汚染水対策や廃炉部門を分社化するよう要求。あらゆる費用を東電が負担する「東電任せ」からの転換を図る狙いがあった。
これを受けて東電も、分社化に向けた検討に入った。ただし、「廃炉機構などの設立による完全な切り離しではなく単純な分社化が議論されている」(東電関係者)とみられ、汚染水対策や廃炉で経産大臣の関与を強める方向で調整を進めている。
11月11日、自民党の提言が安倍晋三首相らに手渡され、除染などへの国費投入の議論が動き始めた。安易な国民負担の増加には、与党内でも反発が予想されるが、経産省は次の手を用意している。
東電のさらなる“解体”プランである。東電改革という意味では、再建策の要になるとみられているものだ。
「一番の焦点が、火力発電の扱いだ」と経産省関係者は明かす。
東電では今春から、カンパニー制に移行し、同時に持ち株会社制を検討している。持ち株会社の下に「燃料・火力」「送配電」「小売り」の三つの事業会社がぶら下がる形を取り、政府内で進む「発送電分離」を先取りする狙いだ。
ここでキーとなるのが、「燃料・火力」の大胆な“切り出し”だ。
東電の業績圧迫の一番の構造的要因は原発停止による火力発電の燃料費増で、原発再稼働以外での収支改善策は、安価な燃料調達と老朽発電所の更新しかない。