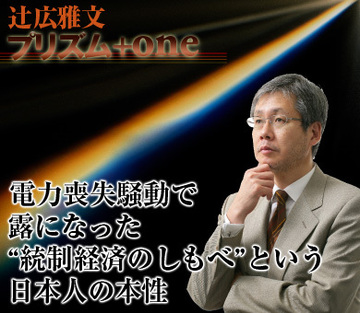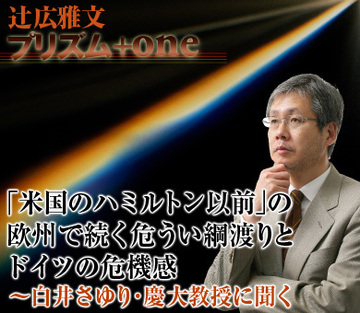TBSドラマ「官僚たちの夏」の舞台は1950年代から60年代の高度成長期のとば口、主人公たちは国内製造業の育成強化を必死で図る通産官僚たちであり、敵対するのは同じ省内の国際派グループである。
当時の日本は敗戦から立ち直り、豊かな欧米社会のキャッチアップを夢見て、国中が熱気をはらんでいた。このドラマは低成長に沈滞、閉塞する今の日本人にとって、50代以上であれば懐かしい記憶を手繰り寄せるセンチメンタルジャーニーであろうし、若者にすれば新鮮なる歴史上のサクセスストーリーであろう。
だが、このドラマを制作したプロデューサーの意図はそれだけではあるまい。政党も指導者たちも誰一人として信頼できる将来ビジョンを提示できないままに、長い経済的低迷を抜け出せない日本人に、確信を持って強い国家作りを主導する者たちへの憧憬、出現願望が高まっている、と踏んだのではないだろうか。
主人公の通産官僚たちは自動車産業やテレビ産業を育成し、繊維産業を保護するために、成長能力ある企業を選択し、それ以外の企業には業態転換をなかば命令し、海外からの競争製品輸入を止めてしまう。その取捨選択、育成方針に呼応して、産業、個々の企業に資金をいくら融資するかを決めるのは銀行ではなく、大蔵省である。通産省と大蔵省次第で当時、国の将来は変わった。
そこには確かに、エリートたちの志があり、無私があり、懸命があり、少なからず私たちの胸を打つ。しかしながら、それは言うまでもなく、発展途上国型の官主導による開発主義経済、国家管理である。当時、政府のあらゆる仕組みが開発主義経済に呼応かつ構成していた。
程度の違いはあれ、当時1970年代初めくらいまでは、先進諸国も同様であった。ありていに言えば、戦争時の統制経済の仕組みを改変し、国家管理による経済産業運営が行われていた。昨年来の世界的金融危機で抜本的見直しが必要ではないかと指摘されたブレトンウッズ体制とは、その国家管理システムを世界に拡大したものだったといっていい。
だが、とっくに通産省や大蔵省、つまり国家が担っていた管理機能の大半は取って代わられた。何によって取って代わられたか。市場(マーケット)によってである。今、先進各国の政府は、いかに市場の調整機能をうまく作動させるかを日々、腐心する。