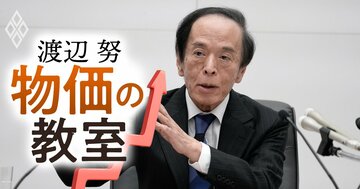2025年5月下旬の日本の超長期金利
(30年物の国債利回り)
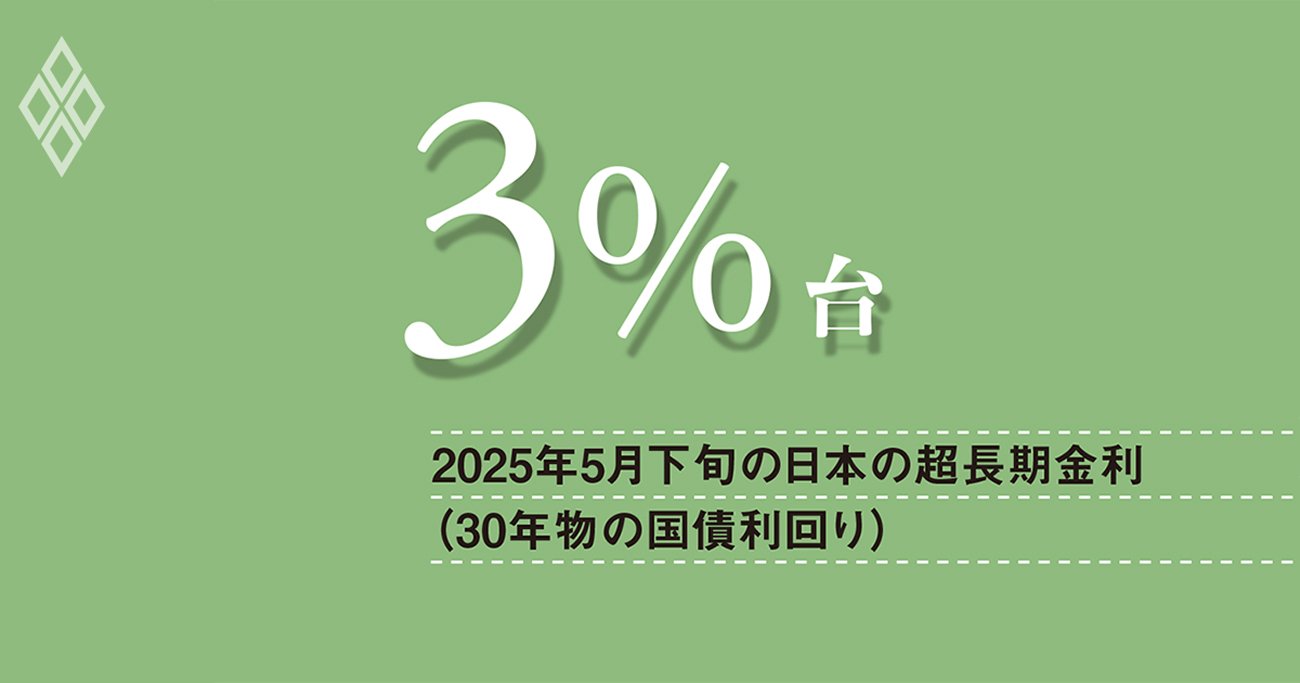
今年5月下旬、日本の30年物の国債利回りが3%台に到達し、1999年の入札開始以来、最高水準を記録した。背景には、インフレと生命保険会社など伝統的な買い手の需要後退に加え、日本銀行の国債買い入れ減額ペースも影響している。
日銀は6月の金融政策決定会合で、従来の毎四半期4000億円の減額ペースを、2026年4月以降は毎四半期2000億円のペースに変更すると表明。また、金利急騰時には機動的に買い増す方針を示し、市場に予見性と安心感を与えた。併せて財務省も、20~40年債の発行額を計3.2兆円減らす方針を示し、供給面から防波堤を築こうとしている。
一方で、副作用も顕在化しつつある。6月の中東での緊迫局面では、日米の金利差が依然大きいまま、円は一時1ドル=145円台まで売られた。従来の「有事の円高」は成立しにくくなっているということだ。円安は輸入物価の変動を通じて国内物価を押し上げ、長期金利のさらなる上昇圧力となる恐れもある。金利抑制と円安対応という二つの課題が、矛盾した形で政策面に露呈し始めている。
財政への影響も深刻だ。25年度の当初予算における国債費は28.2兆円と過去最大に膨らみ、財務省の試算では長期金利が25年度の2%から28年度に2.5%まで上昇するだけで、利払い費は10.5兆円から16.1兆円に増える。さらに長期金利が1%ポイント上昇すれば追加で3.7兆円の利払いが必要になる。財務省は表向き長期債を抑制する一方、短期証券を増発して平均残存年限を縮めており、日本財政が金利上昇に脆弱な構造に向かうことを意味する。
こうした中、日銀と財務省は国債買い入れ減額ペースの変更と超長期債発行抑制によって時間を稼ぎ、政府は賃金と物価の好循環の実現によって経済成長と財政再建の両立を目指している。ただし、円安がエネルギー価格の上昇を通じて家計の実質所得を圧迫すれば、賃上げのメカニズムは頓挫しかねない。
超長期金利の急騰を恐れて金融政策の正常化に踏み切れず、かといって正常化を遅らせれば円安圧力が増す。このジレンマを乗り越えるには、生産性向上や実質賃金の引き上げで実体経済を底上げしながら、同時に財政再建を行うしかない。金融政策だけでは問題を解決できない現実や政治の動きを、市場は冷静に注視している。
(法政大学教授 小黒一正)