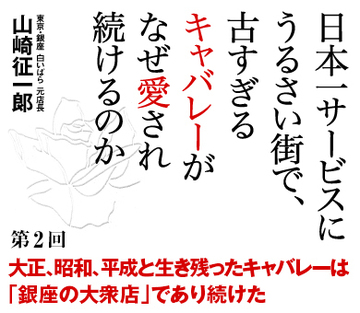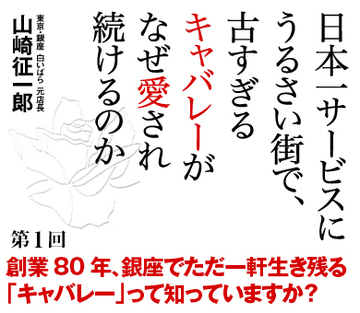創業80年、伝説の老舗キャバレー、東京・銀座「白いばら」に50年間勤務し、名店長といわれた著者が、お客様のための創意工夫をはじめて明かした『日本一サービスにうるさい街で、古すぎるキャバレーがなぜ愛され続けるのか』から、抜粋してお届しています。
白いばらが銀座にあるのは、広島から上京した初代社長・大住米太郎が、たまたま築地の明石町に住んでいたからです。一九三一年、白いばらの前身となる『広島屋』という名前の食堂を深川に開きます。ご飯が美味しく大評判だったと聞いています。
そして翌年、『麗苑』という名のカフェー(=ホステスのいる店)を出店します。銀座を選んだのは、築地に近かったことが主たる理由でした。
その後、営業形態はそのまま、一卓三円をモットーとしつつ、『ミス親類』『処女林』『第一銀座』と、店名を三度変えています。
そんな折、銀座五丁目の表通りにあった『タイガァ』というカフェーが閉店することになり、多くの女給さんが路頭に迷いそうになりました。
そこで、初代社長はその女性たちを全員雇い入れ、一九三五年、『ニュータイガー』という名前のクラブを開きます。お客さまには、作家や俳優、さらには二・二六事件の青年将校たちなどがいました。なかでも寅年の将校たちは、「タイガー=寅年」ということで足繁く通ってくれたそうです。
一九三六年の二・二六事件の前日にも来店し、指定席だったステージの見える席に座り、軍刀で植木をバサッと切り、そこにいたホステスたちに「あすの号外を楽しみにしておけ」と言い残したと聞いています。

戦時色が強まると、敵対国の言葉(=敵性語)はよろしくないという風潮が強まり、タイガーの店名を『南宝』に変えました。店内でも敵性語は禁止となり、マッチは「当て擦り」、サイダーは「噴出水」、マイクは「送話器」、サックスはなんと「金属製曲がり尺八」。ついには、クラブという営業形態自体もけしからんと、一九四四年にはタイプライターの修理工場になりました。平和な世の中になったら、再びクラブを再開しようと思っていた矢先、建物が空襲で消失してしまいます。一九四五年、三月。終戦の五ヵ月前のことでした。
そして一九五一年になって、キャバレーとしての営業が認められ、純粋・無垢をイメージする『白いばら』を店名に、再出発することになったのです。
昭和・平成と激しい時代の流れにさらされながら、二代目・大住政弘、三代目・一誠が店を継ぎ、守ってきました。
前述のように銀座に店を構えることになったのは、言わば偶然でした。でも、成功を収めることができたのは、その“偶然”によるところも大きいと思います。
戦後しばらくの間、大人の遊び場所といえば銀座・赤坂・六本木ぐらいしかありませんでした。なかでも銀座の近くには東京駅があって、地方から出張で上京したお客さまも、かなりの数、遊びに来てくださいました。
遠方から電車に揺られてくると、旅の疲れから、東京駅近くの宿に泊まることが多くなります。そこを拠点に、日中、取引先や政治家のところに出かけ、夜には疲れを癒しに「一杯飲みに行こう」ということになります。その時、土地勘も時間もないため、自然と宿泊先から近い銀座に向かうことになるのです。
敷居の高い銀座のお店の中でも、白いばらは安心して遊べるお店だったのでしょう。