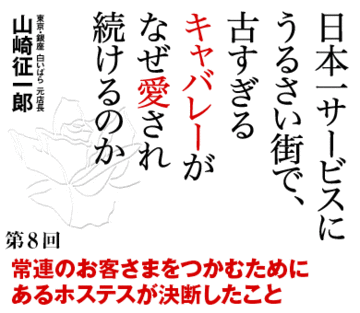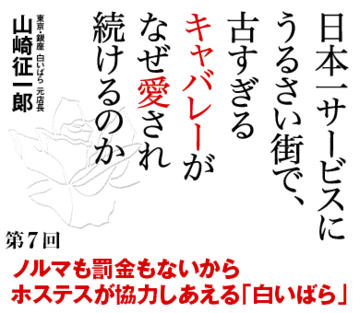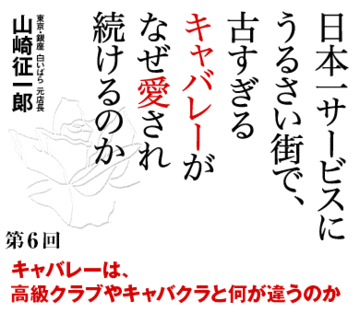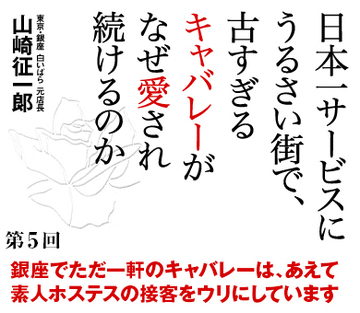創業80年、伝説の老舗キャバレー、東京・銀座「白いばら」に50年間勤務し、名店長といわれた著者が、お客様のための創意工夫をはじめて明かした『日本一サービスにうるさい街で、古すぎるキャバレーがなぜ愛され続けるのか』から、抜粋してお届けしています。
五〇年も一つのお店で働いてきましたから、いい時もあれば苦しい時もありました。一般の会社と同じで、ただ同じことを繰り返していればやっていけるほど甘い世界ではありません。かといって、時代に取り残されまいと、無闇矢鱈に新しいことを取り入れ、その店らしさを失ってしまっては、それはそれでお客さまが離れてしまいます。
私が白いばらで黒服として働き始めて最初にぶつかった問題は、お客さまとホステスの会話が弾まないことでした。素人ホステスの接客がウリといっても、初めから何の苦労もなくうまくいったわけではありませんでした。
一九六〇年代というと、鶴田浩二や高倉健が主役の任侠映画が最盛期の頃です。言葉数は少ないけれど、弱みを見せず、いざという時には啖呵の切れる芯の強い男がカッコよさの代表でした。
そんな時代ですから、銀座に飲みに来るお客さまも、強い男っぷりに拍車がかかっています。店が混んでいて、すぐにホステスをご案内できないと、「俺を待たせるのか!」と丸椅子を投げつけるお客さまもいました。

加えて、今と違って男性が女性慣れしていないため、ホステスとの会話が弾みません。その照れ隠しに、余計にぶっきら棒に振る舞うお客さまが多かったのです。
ホステス側にも問題がありました。高級クラブのホステスならお客さまの時計を見て、「これってパテック・フィリップですよね。すごいわぁ」と話のきっかけを作ったり、お客さまの自慢話をうまく転がしたりすることができますが、白いばらのホステスはそもそもプロフェッショナルではない兼業の女性ばかりですから、昔はなおのこと高級品なんて目にしたことがありません。ただの素人集団ですから、男性を手のひらに載せる腕なんてないんです。
しかも、当時のお客さまは、その店のナンバーワンを口説き落とすのが遊びの醍醐味でした。ところが、先にもお話ししたように、白いばらでは指名や売上げの順位付けを行っていません。だから、ナンバーワンがいないのです。
結果として、黙々と飲むお客さまとその隣でうつむくホステスという、まるでワケありカップルのような姿が店内のあちこちで見られるようになってしまったのです。私たちは頭を抱えました。素人相手ゆえに、肩ひじ張らなくて楽しめるのがウリなのに、その思惑が一八〇度ずれてしまっているのです。
そんな時、有楽町のあるキャバレーがホステスに名札を付けているという情報を、先代社長が仕入れてきました。たしかに名札を付ければ、自分をよく見せようとしすぎて話題作りに困っているお客さまの意識が、ホステスのほうに向くように思われました。そこで、白いばらでもさっそく真似してみることにしたのです。
余談になりますが、昔のホステスの源氏名は「武田さん」「船越さん」というように、みんな苗字でした。なぜなら、当時は携帯電話もメールもなく、ホステスが営業する場合はお客さまの会社に電話をかけて、取り次いでもらっていました。その時にさすがに「富士商事(=白いばらの社名)の〝幸子〟です」と、下の名前では言えなかったからです。
名札へのホステスの反発はすごいものでした。今の若い人にはピンと来ないかもしれませんが、自らを商品として売り出しているようで、恥ずかしかったんですね。名札を勝手に裏返して付けたり、バッグにしまったりして、抵抗するホステスが大勢いました。
私はそれを見つけるたびに、一人ひとりに名札を付ける意味を説明しました。あなたの名前を知らせるためじゃない。あなたに興味を持ってもらうようにするためだよ、そうしたら指名につながっていくよ、と。
最初は渋々付けていた名札でしたが、次第にみんなの表情がいきいきとしてきました。
名前で呼ばれることで、単なる〝ホステス〟としてではなく、〝私〟として扱われるようになり、誇りと責任感を持つようになったのです。
その空気はお客さまにも伝わって、指名の数が増えていきました。指名されたホステスは自信になり、さらにサービスの質がレベルアップしていくというように、名札一つで好循環が生まれたのです。
調子に乗った私たちは名前だけでなく、いろいろな情報を名札に載せることにしました。ホステスの出身地に始まり、血液型や誕生日、趣味なども載せて、その子のプロフィールがわかるようにしました。それに伴って名札もどんどん大きいものになっていきました。
いろいろやってみた結果、現在はマッチ箱くらいの大きさの紙に、管理ナンバーと源氏名、趣味と誕生日を載せています。空いているスペースに好きな食べ物やお酒を付け加えているホステスもいます。