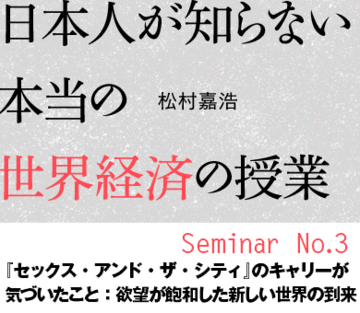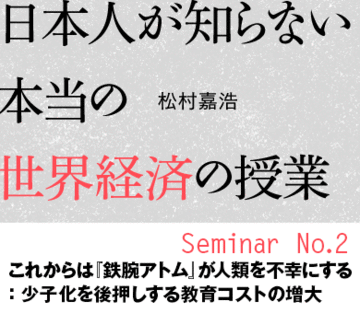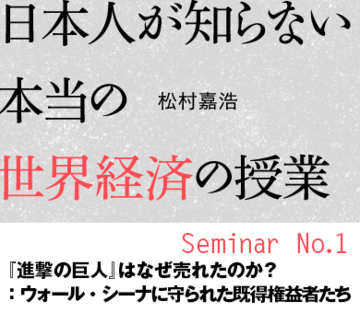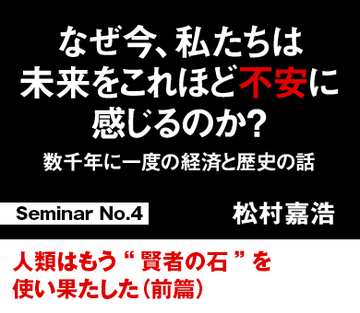各方面から絶賛されたストーリー仕立ての異色の経済書に、1冊分の続編が新たに加えられた『増補版 なぜ今、私たちは未来をこれほど不安に感じるのか?』が発売され、話題を呼んでいます。
この連載では、多数のマンガ作品やヒット曲、名著をヒントに、「マイナス金利」「イスラム国と世界中のテロ事件」「中国バブルの崩壊」「アート作品の高騰」「少子高齢化」「年金問題」「アベノミクスの失敗」の全てが繋がり理解できる同書の一部を「続編」部分を含めて公開していきます。
(太字は書籍でオリジナルの解説が加えられたキーワードですが、本記事では割愛しております。書籍版にてお楽しみください)
今回は世界史を見る目が大きく変わる、「世界システム論」という考え方を紹介します。

資本主義の歴史は「賢者の石」の奪い合い
「さて、新しい時代が来ているという話で、人口減少と欲望の飽和の話をしてきました。じつは、さらに別の角度からも新しい時代が来ているのです。今日はそのお話をしましょう」
「え~、まだあるんですかぁ」
もう、うんざりだというふうに絵玲奈は言った。
「ええ、これも人類が初めて経験する……」
「マジですか。また、そんな規模の話ですか! オドロキです。まさか自分がそんな時代に生まれちゃっただなんて……」
絵玲奈は深刻な顔をして言った。
「まあ、まずはお茶でも飲みましょうか。紅茶でいいですか? いいアールグレイを知人にもらったので」
教授室にはふさわしくないような高級そうなティー・カップに教授は紅茶をいれた。
「どうぞ」
「ありがとうございます」
絵玲奈は砂糖がないことに気づいた。
「あの~、砂糖ってありませんか」
「え、砂糖を入れるのですか?」
教授はとても驚いた様子で言った。
「え、そ、そ、そんな変なこと言いました? 紅茶に砂糖を入れちゃダメなんですか?」
絵玲奈は教授の勢いに驚いて、思わずどもってしまった。
「ダメです。それはとっても野蛮なことです。邪道です」
「はぁ? ぜんぜん意味がわかりません。教授」
絵玲奈は困惑して言った。
「砂糖は『鋼の錬金術師』に出てくる“賢者の石”みたいなものですから」
「“賢者の石”ですかぁ? ますます意味不明です」
「すみません。思わず言っちゃいました。今回お話ししたい《新しい時代》を説明する前に少しネタばれになっちゃいますが、せっかくなのでお話ししましょうか? “賢者の石”の意味を」
「はい、ぜひ、教えてください。教授」
「紅茶といえばイギリスですよね。イギリスってどんなイメージですか?」
「行ったことがないので、実際、イメージでしかないですけど。紳士の国で、ビートルズを生んだ国で、最初に産業革命を起こした先進国で、紅茶を飲んで優雅でかっこいいイメージです」
「まあ、そうでしょうね。日本は明治維新のときに幕府側をフランス、薩摩・長州側をイギリスというふうに、それぞれがサポートする形で内乱をしました。結果的に薩長が勝って、新政府はイギリスを手本に、日本を先進国である欧米列強に近づけようとするのです。日本人にとってイギリスは先生であり、イギリスに対する憧れを抱いてきたのです。なんといっても世界を支配した大英帝国ですからね」
「じゃあ、実際はどうなんですか?」
「そうですね。16世紀までのイギリスはヨーロッパの中でも辺境です。一言で言えば田舎だったと言っていいでしょう。政治的にもチューダー朝の基盤を固めたヘンリー8世は、政略結婚でスペインから王妃を迎えるような弱小国です。もっと昔はフランスのノルマンディ公の領地で、支配階級はフランス語をしゃべっていました」
「えっ! そうなんですか」
絵玲奈は驚いて言った。
「はい、なので英単語はフランス語の語源のものが多いですし、世界の言語の中で、最も外来語を含んでいるといわれています」
「ぜんぜん知りませんでした! イギリスって田舎だったんですね」
「そんな国だったんですが、18世紀に世界を牛耳るような国になっていくのです」
「どうやってですか?」
「それは、順を追ってゆっくりお話ししていきますが、その前に“賢者の石”のお話を片付けてしまいましょう。紅茶に砂糖を入れて飲むというのは、世界の覇権を握ったイギリス人が、いかに自分が金持ちかを誇示するためのステイタス・シンボルだったんです。世界の覇権を確立したイギリスが、世界の西の端のカリブ海で奴隷につくらせた砂糖と、東の端のインドでつくらせた紅茶を輸入してきて、合体させたわけです。
当時、高級だった砂糖とお茶を混ぜて、西から東まで世界システムを牛耳っているぞっていうのを見せつける成金趣味です。アジアの人からすればお茶に砂糖を入れるなんて想像すらできなかったでしょうし、覇権を争って敗れたフランス人から見れば田舎者がとんでもないことをして、と怒ってたんじゃないですかね」
「え~、びっくりです。イギリスのイメージが変わっちゃいそうです」
「マンガの『鋼の錬金術師』の世界観において、錬金術は無から有を生むことはできず、あくまでもともとあった物質の構成を変えるだけ、つまり“等価交換”しかできないという制約があります。しかしながら、“等価交換”の原則を無視してなんでも錬成できちゃう幻の錬金術の増幅器が“賢者の石”です。マンガの最後でその正体が明かされるのですが、それはなんと生きた人間を対価に錬成された魂が結晶した高密度のエネルギー体です。つまり人そのものというわけです。“砂糖”は、イギリス人が奴隷貿易でアフリカから連れてきた黒人奴隷を酷使してつくった黒人奴隷の“血と涙と汗の結晶”です。まるで“賢者の石”みたいじゃないですか?
それをわざと紅茶に混ぜて飲むっていうのは、そうすると美味しいからというわけでなく、支配を誇示するためなので、野蛮で品のない行為というわけです」
「すごく面白いです。ていうか、びっくりしました。そんな歴史があったなんて」
「本題に戻って《新しい時代》のお話をしましょう。我々がどういう時代にいるのかということを理解するには、我々が生きている世界がどのようにできてきたのかという過去を知らなければいけません。結論から先に言えば、資本主義の歴史は、じつは“賢者の石”の奪い合いでもあるのです。ところが、《新しい時代》に入ったというのは“賢者の石”を使い果たしてしまったということでもあるのです。私は歴史は専門ではないので、この事実を、アメリカの社会・歴史学者のイマニュエル・ウォーラーステインが提唱した近代世界システム論をベースに考えていきましょう」
「はい、お願いします」
「近代世界システム論は、教科書で採用されているようなこれまでの歴史に関する考え方の常識を覆す、非常に面白くかつ本質を突いた物の考え方です。先進国と後進国という言い方がありますよね。先進国は進んでいて、後進国は遅れているという考え方は、国の発展の歴史は同じレールの上を走っていて、いずれ後進国は先進国になるという考えです。こういうのを単線的発展段階論といいます。ところが近代世界システム論はこういう考え方をしません。もっと同一時代史的なとらえ方をするのです」
「同一時代史ってなんですか?」
「例えばイギリスが工業化されて先進国になったわけですが、後進国のインドがまだ充分に工業化されていないのは遅れているからではなく、イギリスが工業化されたためにその圧力を受けたインドは容易に工業化できなくなり、工業化とは逆の動き、“低開発化”に向かったという考え方なのです。同じ時間軸の中で別々の道を歩んで今に至っているというわけです」
「ということは、後進国は後進国になるようにプログラムされてきていて、別のルートを歩んでいるということですか?」
「そのとおりです。ですから、後進国は決して資本投下がなくて開発がされなかったり、怠慢でがんばらなかったりしたから遅れているわけではないのです。先進国つまりは工業化された国のための食料や原材料の生産地にさせられ、逆に猛烈に資本投下されて開発された結果、めちゃくちゃに社会や経済が歪んでしまったわけです。これを“低開発化”といいます」
「一言で言えば、後進国は先進国のために、こき使われるようにプログラムされちゃったということですか?」
「そうです。さっきの例えでわかりやすくいえば、先進国が発展するために“賢者の石”化されていったというわけです。ちなみに、あとでこの“低開発化”が非常に重要なキーワードになるので、しっかり覚えておいてくださいね。
近代世界システム論においては先進国になっていった地域を“中核”と呼び、“低開発化”された地域を“周辺”といいます。近代世界システム論の考えでは“中核”に従属する“周辺”といったように世界的な分業体制ができていて、世界が1つの経済圏に統合されたまとまったシステムとなっているので、すべての国はその構成要素にすぎないのです。ですから、歴史はそれぞれの国を単位として動いているわけではないというわけです。これが近代世界システム論の考え方の中心になります」
「へぇ~。学校で習った世界史とぜんぜん違いますね。非常に新鮮で面白いです」
「学校の教科書は、単線的発展段階論、つまり後進国は先進国に発展して追いつくという考えですからね。さて、我々は、現在この世界システムの中にいるわけですが、この世界システムがどういう経緯で始まったのかを見ていきましょう。そもそもの始まりは、貧しいヨーロッパの豊かなアジアに対する憧れなのです」
「えっ、ヨーロッパが貧しくて、アジアが豊かだったのですか? 今と逆なイメージですが本当ですか?」
「世界史の教科書は、最終的に世界の“中核”となった欧米を中心に歴史を見ていくことになってしまっているので、ヨーロッパが遅れているという感覚が乏しいですが、中世までのヨーロッパはアジアやイスラム圏から見ると、非常に貧しい世界でした。いわゆる暗黒の中世と呼ばれている時代です。古代のヨーロッパは、ギリシアやローマのように哲学や幾何学・天文学といった学問が発達しますが、中世になるとキリスト教が支配する時代になって科学の発展が止まるどころか後退します。例えば、古代には地球が太陽の周りを公転していることを理解していたのに、中世になると地球は平面で天が動いているというふうになってしまいました」
「あ、あれですね、ガリレオが『それでも地球は回っている』って言った……」
絵玲奈は、小学生のころに課題図書でガリレオの偉人伝を読まされていたので、ガリレオが理不尽な目にあわされて、可哀想だったことを印象的に憶えていた。
「そうですね、宗教裁判にかけられて、無理やり天動説を認めさせられて、つぶやいたといわれていますね。この時代のヨーロッパはキリスト教、カトリックがめちゃくちゃをやっていた時代です。民衆はラテン語で書かれた聖書が読めるわけもなく、教会で言われたことを信じて、贖宥状のようなおカネを払うと天国へいける切符を売りつけられたりしていました。当時、先進地域だったアジアの中国で発明された印刷技術が入ってきて、現地語で翻訳された聖書が広まることで、カトリックのインチキがばれて、カトリックに反抗するプロテスタントが出てきます」
「なんか、中世のヨーロッパって、教科書ではよくわからなかったですけど、ずいぶんダメなんですね」
「そうなんです。15世紀ごろにはヨーロッパの封建社会は崩壊の危機に立たされていたんです。その当時、世界には4つから5つの経済圏があって、現在、近代世界システムの“中核”にのし上がった西ヨーロッパはどの経済圏にも属さない“周辺”にすぎませんでした。シルクロードから入ってくるアジアの物品はすばらしいものですし、マルコ・ポーロの『東方見聞録』のように、アジアが豊かですばらしい、黄金の国があるらしいというような情報がヨーロッパに入ってきました。そのなかで、このままじゃどうしようもない、外に打って出るしかないというふうになっていくわけです。
このように、豊かなアジアに対する強い憧れが辺境のヨーロッパ人をアジアに駆り立てたのです。ところが、陸つづきでアジアに向かうことはできませんでした。東側にはイスラム教のオスマン帝国が勢力を大きく伸ばしていたからです。そういうわけで、ヨーロッパの西の端のスペイン・ポルトガルが最初に海に乗り出してアジアを目指すのです。これがもともと“周辺”だったヨーロッパが“中核”になっていく近代世界システムの始まりです。ここまではいいですか?」
「はい。それでどうなるんですか? 教授」
今まで聞いたことのない面白い話に、絵玲奈は前のめりになった。
「いわゆる大航海時代が始まります。ポルトガルが東を目指し、アフリカ大陸をぐるっと回ってアジアに向かう航路をつくり、出遅れたスペインが、地球が丸いなら西に向かえばアジアに行けるはずだという話でコロンブスがインドを目指して大西洋に乗り出し、結果的に新大陸を発見します。コロンブスは死ぬまでインドだと信じていたようですが。
ここから、スペインが新大陸、ポルトガルがアジアというふうにそれぞれが縄張りを分けて活動を始めるわけですが、その前にもう少し、この時代のヨーロッパ人がどんな人たちなのかを理解しておいたほうがいいと思うので説明します。そうでないとよくわからなくなると思うので」
「とりあえず、貧しかったということはわかりました」
「農業生産力は非常に低く、経済的にはダメだったのですが、中世のヨーロッパは軍事技術が他の世界に比べて非常に発展していくのが特徴なのです。その経緯を説明します。まず、ルネサンスの三大発明って何かわかりますか?」
「ごめんなさい……わかりません」
「大丈夫ですよ。さきほど出てきた印刷技術と、火薬と羅針盤です。ルネサンスの三大発明と偉そうに言っていますが、実際はもっと昔に中国で発明されたものがヨーロッパに持ち込まれ、それを改良しただけです。いずれにしても、さきほど言ったキリスト教の迷信の世界だった暗黒の中世から決別するルネサンスが始まって、これらの技術がヨーロッパの社会を変えていきます。
訓練しない人でも簡単に使える鉄砲のような武器がひろがり、馬を使った戦争のスペシャリストだった中世の領主・貴族の軍事力が低下してしまいます。そして、経済が低迷して領主と農民の間で取り分の紛争が多発するなかで農民の反乱を抑えられなくなっていくのです。中世の領主・貴族たちは、それまで自分たちが勝手にやりたいので中央の王をできるだけ無視してきたのですが、そうも言っていられなくなって国王に依存するようになっていきます。この結果、世界史の教科書に出てくるように、16世紀ごろに絶対王政が成立し、ゆるやかで不完全ながらも国民国家ができ始めるのです」
「国民国家ってどういう意味ですか?」
「現在の国は、国民国家です。日本人とかフランス人とかいったように、同じアイデンティティを持った人たちが集まってできている国ということです。ところが、中世のヨーロッパは国の概念があいまいでした。中世の人にどこの人かと問えば、国の名前ではなく荘園や教区の名前を答えたでしょう。いろいろな領主・貴族を国王が封建関係で1つの大雑把なまとまりにくくっていただけだからです。それが、不完全ながらも国王が国をまとめる中心となって、いわゆる主権者となっていくのです」
「なるほど、わかりました」
「で、話を続けると、そうなるとそれまであいまいだった領域、国境を明確にしなくてはいけませんよね」
「たしかにそうですね」
「でも、狭いヨーロッパ大陸に国家がひしめき合うことになれば、どうなると思います?」
「戦争……ですか?」
「そのとおりです。絶対王政の時代は、戦争が頻発します。高校の世界史の教科書でもこの時代の戦争は、20件近く載っているぐらいなのです。この結果、ヨーロッパは各国で武器の開発競争が起きて、もともと火薬を発明した中国よりも火薬の運用が発展していくのです。そして、16世紀にはアジアと比べて圧倒的な武力の差ができてしまいます」
「貧乏が理由で最初は農民との奪い合いに勝つために軍事力が発展し、そのうち国と国の戦争になっていったというわけですか?」
「そうです。そして、戦争に勝ち抜くにはおカネが重要です。戦争はものすごくおカネがかかるので。しかし、さきほども言ったようにヨーロッパの生産力は低いわけで、外に打って出るしかない、目指せ黄金の国となるわけです。そして、そこで3番目の発明品の登場となります」
「羅針盤ですね」
「そうです。それが外に打って出るための発明というわけです」
「ちなみに、なぜヨーロッパより、豊かなイスラムや中国といったところが“中核”となって世界システムをつくることにならなかったのですか?」
「ご指摘はもっともで、羅針盤を発明していた中国では、バスコ・ダ・ガマやコロンブスが世界に乗り出してくる70年ほど前、明の時代に鄭和という武将が7回の大航海をしています。その規模も2万8000人、62隻という大船団で、コロンブスのおよそ90人とは比較にならないものでした。しかしながら、それ以降、中国が海に出ていくことはありませんでした。中国はアジア域内で充分、豊かに暮らせていましたし、明清期の中国やオスマン朝のイスラム世界は政治的に統合された帝国でしたから、武力が中央に独占されていたのです。ヨーロッパのように国家同士があちこちでドンパチやるような状態ではなかったので、秩序が保たれてはるかに平和な社会だったと言えるでしょう。そのため、わざわざ、よくわからないリスクをとって遠くまで進出していく理由がなかったわけです。これが、イスラム世界や中国が世界システムを形成しなかった理由です。
逆に、誤解を恐れずに言えば、当時のヨーロッパは文化・文明が他の地域より遅れていて、自らの経済的な危機を、略奪によって解決するような野蛮な人たちでもあったのです。そういう人たちがヨーロッパ内の戦争で鍛え上げられた武力を持って外に出ていき、平和に暮らしていた他の経済圏を、自分たちを“中核”とする世界システムに暴力的に組み込んでいったプロセスが、16世紀以降の世界史の大きな流れです。歴史家のポール・ケネディの大作『大国の興亡』でも、この時代のヨーロッパが、つねに戦争を繰り返していて、ここで生まれた軍事的な革新が経済発展に結びついていったという指摘をしています」
「う~ん、教科書とぜんぜん違って目からうろこです」
「まあ、こんなにはっきりはなかなか言いづらいですからね。ヨーロッパからクレームがきちゃうかもしれないですから」
苦笑いしながら教授は言った。
「でも、とっても面白いです。歴史って暗記ばっかりでホントつまんないと思っていましたけど、背景や流れがわかると興味が湧きますね。なんで、学校はもっとわかりやすく教えてくれないんですかね」
絵玲奈は、もっと早くこういうことを知っていたら、面倒で大嫌いだった歴史をもう少し真面目に勉強できて受験で苦労しなくて済んだのにと思った。