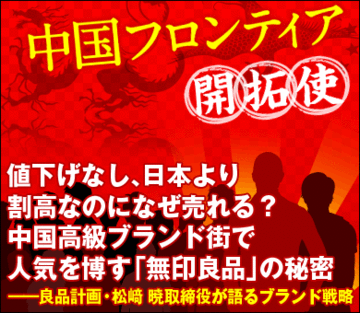Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
「無印良品」ブランドを展開する良品計画には、1991年に西友から出向して以来、24年を過ごし、2015年に退社した。
2001年1月に私が良品計画の社長に就任したときは、拡大一途から業績が急落するという最悪のタイミングだった。社長として最初の決算となった2001年2月期、良品計画は創業以来初となる減益を経験し、2001年8月の中間期には38億円の赤字、そして2002年2月期は当期利益がゼロになった。2000年2月には1万7350円だった株価は、私が就任した2001円1月には2750円にまで落ち込んでいた。時価総額は約4900億円から770億円へと“大暴落”である。企業価値はわずか1年で4100億円も下落してしまったのだ。
それでも、08年に会長に就くまでなんとか良品計画の再生に道を付け、「無印良品」のブランドを次の世代へとバトンタッチすることができた。
現在、良品計画は、直近の16年2月期の売上高が3072億円を記録して初めて3000億円の大台を超えた。国内では「無印良品」、海外では「MUJI」のブランドで展開するアイテムは衣服・雑貨、生活雑貨などで7131品目を数える。国内で414店舗、海外で344店舗を展開し、これを国内外合わせて約1万2000人の社員が支えている。
今月は、私が良品計画の事業再生にいかに取り組んできたかと、そのなかで学んだ“事業再生の肝”を記しておきたい。多くの企業が激変する環境に対応できず、持続的な成長の芽をつかめぬままでいる。私の経験がお役に立てれば幸甚だ。
「わけあって安い」は、「わけあって落日」になった
「無印良品」の最初のアイテムが西友から誕生したのは1980年のこと。高度成長が終わり、オイルショックが到来し、消費は成熟期に移行していた。そうしたなかで大手のスーパーストア各社が取り組んだのがプライベートブランド(PB)の投入で、お客さまのニーズにきめ細かく対応しようとした。最初の無印は、調味料、トイレットペーパー、洗剤、缶詰など40アイテムだった。
当初のPBは値段こそナショナルブランドに比べて3割ほど安いが、質が伴わず「安かろう、悪かろう」と各社ともひんしゅくを買っていた。そのなかで唯一健闘していたのが西友の「無印良品」だった。その理由は、明確な商品コンセプトにあった。
西友が属するセゾングループのオーナーは、詩人にして作家でもあった堤清二さんだ。そのカリスマ的な雰囲気から、提さんのまわりには日本を代表するクリエイターたちが集っていた。中でも日本の禅や茶道の価値観に影響を受けた者たちから、「無印良品」は発想され、商品開発が進んだ。
そのコンセプトは、「わけあって、安い」。デザインはシンプルで、素材を見直し、生産工程でのムダを省き、包装も簡素化する。そうすることで質は落とさず価格は下げる。
例えば、ティッシュペーパーは外箱をなくし、中身だけ。醤油やサラダオイルは共通のボトルにして廃棄ロスを減らす。
商品はシンプルで機能性をとことん追究し、かつ天然素材しか使わない。その発想の原点は「モノしか見えないモノをつくろう」だった。綿100%の白いシャツにはロゴさえ付いていなかった。シャツの機能だけで勝負すると考えたからだ。
89年には「無印良品」の事業を引き継いで良品計画が設立され、90年には西友から直営店を移管した。当時の売上高は245億円で、経常利益は1億円。91年には早くも海外出店を始めた。95年に株式を店頭公開し、後に東京証券取引所に上場する。
会社設立から10年後の2000年2月期には売上高が1000億円を超え、経常利益も130億円を達成するなど、まさに順風満帆の成長を続けていた。
しかしここがピークでもあった。冒頭にお話ししたように2001年2月期には売上高こそ微増だが、経常利益は116億円に減少し、直営既存店の売上高前年比は91%に落ち込んでいた。明らかに異変が起きていた。
そう、良品計画は、「わけあって落日」を迎え始めていたのである。