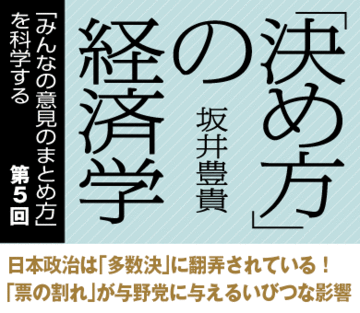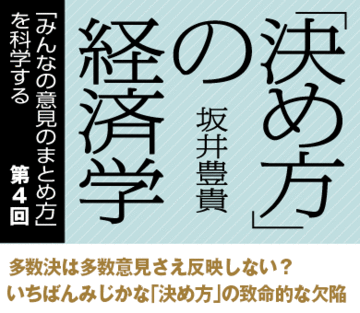私たちは普段「多数決」という決め方をよく使用する。『「決め方」の経済学』の著者である坂井豊貴氏によれば、多数決で正しい判断をするには、ある条件が必要だという。それは何か。
(新刊『「決め方」の経済学』)より、一部を特別に公開します)
罪の有無は
多数決で決められるのか

いま1人の被告が法廷で罪を問われている状況を考えてみよう。彼が罪を犯したのか否か、確たることは誰にもわからない。かりに犯行現場の目撃者がいたとしても、見間違いかもしれないし、嘘をついているかもしれないし、妄想に取り憑かれているかもしれない。
真実は神のみぞ知るとしても、この世の裁判で有罪か無罪かを決めるのは神様ではなく、人間だ。そしてここで考えるのは陪審員。陪審員の多数決で罪の有無を決定する。その決め方でどれほど正しい判断ができるのだろうか。
正しい判断とは何かというと、「被告が罪を犯していたときには有罪、そうでないときには無罪」と判断することだ。犯罪者を野放しにしないこと、冤罪を起こさないこと。
陪審員の人数が多いと
正しい判断をしやすくなる
これには陪審員の人数が影響する。
まずは陪審員が1人の場合を考えてみよう。このとき陪審の評決が正しいためには、当然ながら、その1人の判断が正しくあらねばならない。割合としては「1人のうち1人」なので100%だ。誰一人として間違えてはならない。
では陪審員が3人ならどうか。3人全員が正しくある必要はない。多数決の結果が正しくあるためには、2人が正しければ十分だからだ。言い方を変えると、間違える陪審員が1人、全体の約33%に留まるならば、多数決の結果は正しくなる。
この傾向は陪審員の数を増やすとさらに強まる。
陪審員が5人なら、そのうち3人が正しければ、多数決の結果は正しくなる。逆にいうと、陪審員のうち2人、全体の40%までは間違えてもいい。
陪審員が11人ならそのうち6人さえ正しければ多数決の結果は正しくなる。逆にいうと、陪審員のうち5人、全体の約45%までなら間違えてもいい。
さらに人数を増やして陪審員が101人ならば、そのうち約半数の51人が正しければ多数決の結果は正しくなる。50人までなら間違えても構わない。半数に近い陪審員が間違えたときでさえも、多数決の結果は正しくなるのだ。
こう考えてみると、陪審員の数が増えるほど、多数決の結果が正しくなりやすいとわかる。51%だろうが50.1%だろうがとにかく過半数の陪審員が正しければ、多数決の結果は正しくなれるからだ。
極端な話、陪審員の数を無限に増やしていくと、多数決の結果が正しい確率は100%に限りなく近づいてゆく。多数決のこうした性質を示す結果を陪審定理という。
「陪審定理」が成り立つには
ある条件が必要である
これまでの議論の運びでは、陪審定理が成り立つための前提条件を明記していなかった。でもその前提条件が満たされないと、陪審定理は成り立たない。それが満たされるか否かが、多数決による成功の可否を分かつといえる。
まず1人の陪審員が正しい判断ができる確率をpで表そう。そして 1>p>0.5 とする。まずこれを説明しよう。
1>p は、人間が100%の確率では犯行の有無を当てられないという意味だ。人知は神に及ばないということ。及んでくれても構わないけれど、そのときもはや人間に多数決は必要ないだろう。
p>0.5 は、人間が熟慮すれば「表裏が半々の確率で出るコイントス」よりはうまく判断できるという意味だ。完全な当てずっぽうよりは、熟慮のほうが正確であろうということ。その程度には人間を信頼するという人間観の表れだ。
確率 p は各人で共通とする。確率が各人でバラバラなケースを扱う研究も多くあるが、議論の骨子は p が共通のケースとほとんど変わらない。
陪審の評決が正しい確率、つまり多数決の結果が正しい確率はいくらになるのだろう。もしその確率が p より高いならば、多数決の判断は、1人の人間の判断より正しくなりやすいことになる。