昨年からの株価下落過程で、何回か底を確認との声が聞かれた。だが、現実には昨年8月の安値1万5262円を一番底とすれば、二番底が11月22日の1万4669円、三番底が1月22日の1万2572円、そして四番底が3月17日の1万1691円となる。これで最後となるか否か、過去の戻り相場の局面から考えてみたい。
相場トレンドを知る法としては、移動平均線を見るのが最も簡単で一般的だ。なかでも100日と200日にスポットを当ててみたい。
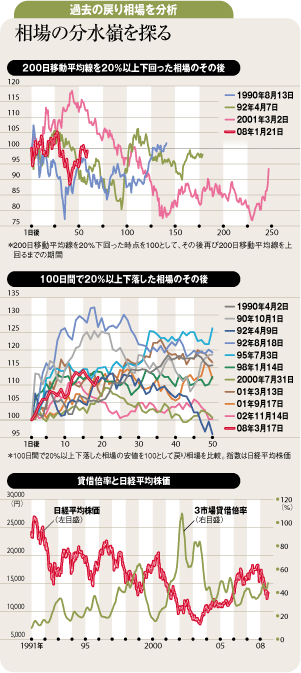 今回の下落相場でも注目された法則の一つに「200日移動平均線の20%下方乖離は大底接近のシグナル」がある。実際には最初に200日移動平均線から20%以上下方に乖離したのが1月21日。そこからさらに900円ほど下落してようやく反転した。
今回の下落相場でも注目された法則の一つに「200日移動平均線の20%下方乖離は大底接近のシグナル」がある。実際には最初に200日移動平均線から20%以上下方に乖離したのが1月21日。そこからさらに900円ほど下落してようやく反転した。
過去の「200日移動平均線の20%乖離」後の相場を見てもほぼ同様で、底打ちのシグナルとまではいえない。下がり続ける200日移動平均線からさらに大きくは下がりにくい傾向がある、と考えたほうがよさそうである。
サンプル数を増やし、100日間で20%以上下落した急落相場で、安値からの戻りを比較してみよう。実際に大底を示し、相場の転換点となったのは1992年8月安値と1995年7月安値だった。これらと比較すると、現在は95年型の動きに近いように見える。
しかし、どちらのチャートにも1998年や2003年といった本来の大底が登場しない。このことは貸借倍率でも裏づけられる。1998年、2003年は3市場の貸借倍率が50%を大きく超え、いわゆる空売りが急増した。
100日、200日のチャートを見てもわかるとおり、底かと思えばまた下落する展開が何度も続き、大底に近づいていく。売り方は勢いづいてポジションをふくらませる一方で、底だと見る買い方は「買っては投げ、買っては追証」を繰り返して疲弊する。こうして建玉が減少し、貸借倍率が急上昇していくのである。
今のところ、売り方の勢いはそこまで盛り上がっているわけではない。だが、底を打って反転する力にも欠ける。過去の相場で、上昇、もみ合い、反落の分水嶺は、いったん底をつけた後、3ヵ月を待たずに安値を下回るかどうかだった。決算発表や長期休暇などによって波乱が起きやすいゴールデンウイーク前後の相場は、まさにその分水嶺となりそうである。
(エクイティトレーダー 山独活継二)




