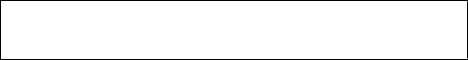「勝ちましたね」という政府関係者の口調には、安堵の色が滲んだ。
2月25日、肺ガン治療薬「イレッサ」の副作用被害をめぐる第一審判決が下された。患者と遺族は、国と輸入販売元のアストラゼネカを訴えていたが、国には著しく不合理な判断・行動はなかったとして、賠償請求が退けられたのである。
もう一方の当事者のアストラゼネカは、製造物責任法上の責任を問われ、原告9人に合計約6千万円の支払いを命じられた。イレッサの有用性は認められるが、警告方法に問題があったというのだ。
イレッサの副作用を巡っては、大阪と東京の両地裁で訴訟が起こされており、今回の大阪地裁が初めての判決だった。
第一審を待たない異例のタイミングで、1月に両地裁が国とアストラゼネカに和解を勧告。被害者を救済する責任を指摘していた。国とアストラゼネカは、和解を拒否したものの、勧告の内容から国も一定の責任を問われるものと予想されていた。そのため、この判決には、少なからず驚きもあった。対する原告弁護団は「残念」(水口真寿美・副団長)と落胆を見せた。
この判決を不服として、原告やアストラゼネカが控訴するのか――。また注目されるのは、3月23日に言い渡される東京地裁の判決だ。しかし、どのような判決が出るにしても、「裁判で提起された医薬品をめぐる課題について、改善を進める」(政府関係者)ことこそが重要な意味を持つであろう。
喫緊の課題は、抗ガン剤の副作用による被害者救済制度を作るための仕組みづくりだ。
被害者救済制度でいちばんの問題は、財源の確保である。現在、抗ガン剤を除いたクスリには救済制度がある。この枠組みが参考になるだろう。ただし、被害者救済制度が乱用されないためには、患者と医師が、薬がもたらすリスクとベネフィットがあることを理解して、納得した上でクスリを使用することが前提だ。
そのためには、副作用情報の開示と周知徹底が重要となってくる。だが、これまでの薬事行政においては、「副作用が重いか軽いかを分ける基準や、副作用が発生する確率を評価する基準が非常に曖昧。副作用情報をいかに伝えるか、といったことも含めて、理念や方法論を議論したことがない」(厚労省関係者)という状況だ。ゼロベースで、副作用情報の伝え方を考えていく必要がある。
求められる課題に国が対応する姿勢を見せてこそ、今回の裁判がいっそうの意味を持つ。国が「勝った」と責任をメーカーだけに押し付ければ、被害者は厚労省を憎んで今後も訴訟が続く。これでは、メーカーは日本を顧みなくなり、真に画期的な新薬が日本から消える。そんな事態は避けなければならない。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 柴田むつみ)