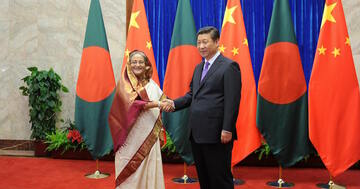「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が19日、衆院法務委員会で自民党・公明党・日本維新の党の賛成多数で可決した。民進党、共産党などの野党は「廃案」を訴えていたが、与党側は衆院法務委での審議時間が30時間を超えて、審議が熟したとして強行採決した。改正案は参院に送られ、今国会で成立する見通しである。
「テロ等準備罪」の国会審議に国民は白けきっている。多くの国民はテロ対策の必要性を認識しながらも、「テロ等準備罪」への不安も感じている。野党は与党と協議を行い、妥協を勝ち取りながら、国民の不安を除去している役割を担うべきだった(本連載2017.4.11付)。
だが、野党はひたすら廃案を求め、「カレーも作れない」「LINEもできない」などと重箱の隅を突き、揚げ足を取るだけに終始した。結果として、維新の党が求める「取り調べの可視化」を付帯事項に加えるだけで、処罰対象となる犯罪の数277は1つも削られることなく、与党案はほぼ無修正で衆院通過してしまった。維新の党を除く野党の怠慢は、万死に値するものである。
本来、国会で議論すべきは、国際社会の厳しい現実の下、もはや目を背けることができなくなっている「テロ対策」を強化することで、日本社会がどのように変わっていくか、多角的に検討することではないだろうか。実は、民進党はそのための格好の検討材料を国会に提出していた。テロ等準備罪の対案である。しかし、民進党自体がその意味を理解できず、国会内外での議論を起こせず、ただ対案を出しただけとなっているのは残念である。
英国のテロ対策は情報網・
監視体制を駆使し水際で防ぐ
民進党の対案は、「フランス」のテロ対策の思想に近い考え方である。これに対して、与党案は「英国」に近い。ともに民主主義の総本山を自認するといえる英仏は、民主主義とテロ対策のあり方について、全く異なる手法をとっている。
英国とフランスのテロ対策の端的な違いは、英国のロンドン市内やヒースロー空港には「自動小銃を持った警官」の姿がほとんど見られないが、フランスのパリ市内やシャルル・ド・ゴール空港には多数の警官や武装兵が立ち、警戒しているということだ。
筆者が英国に住んでいた時(2000~2007年)、ロンドン市内にもヒースロー空港にも自動小銃を持った警官はほとんど立っていなかった。2001年の「9.11」などテロが頻発し、世界中で警戒態勢が強化された時期で、例えば、成田空港に入るためには、見送りに来ただけの人でもパスポートを提示しなければならなかったが(それは現在でも変わらない)、ヒースロー空港では駐車場に車を停めてターミナルに入るときに、パスポート提示を求められたことは一度もなかった。
ロンドン市内も一見、警戒態勢は緩く、いつでも簡単にテロを起こせそうな感じだった。だが、テロが頻発するフランス、ベルギーなど欧州大陸に比べれば、発生件数は格段に少ない。英国ではテロはほとんど起きないと言い切っていいレベルである。
それでは、なぜ無防備で隙だらけのように見えながら、テロが起きないのか。端的にいえば、英国の警察・情報機関が、国内外に細かい網の目のような情報網を張り巡らせ、少しでも不穏な動きをする人物を発見すれば、即座に監視し、逮捕できる体制が確立されているからだ。
平均的なロンドン市民
1日に約300回監視カメラに写っている
英国は「監視社会」である。英国内には約420万台の監視テレビ(CCTV)が設置されていて、これは世界最大の台数である。ロンドン市民が普通に生活していて、1日に監視テレビに捉えられる平均回数は、約300回といわれている。
そして、この監視カメラが捕らえた情報に、携帯電話やPC、ラジオ、電子切符「オイスター」などから得られる様々なデジタル情報を組み合わせて、特定の人物の所在を高精度に追跡できるデータベースを構築しているという。
さらに、英国の警察は、犯罪人データベースに約400万人分のDNAサンプルを所持している。これは世界最大の件数を誇り、フランスの同様のデータベースの50倍である。警察は逮捕した人物からDNAサンプルを取るが、逮捕者が無罪として釈放されても、その人のサンプルはデータベースから消去されないという。いわば、「全市民を容疑者として扱っている」ようなものだと、英国の警察はメディアから批判されてきたくらいだ。
英国の情報網・監視体制は、52人の犠牲者を出した05年のロンドン同時爆破テロ以降、さらに強化されてきた。テロが発生したのは、情報機関と警察が相互不信に陥り、情報を共有できず、実行犯の動きを見逃してしまったという反省からだ。その後、情報機関と警察の間で綿密に情報交換が行われるようになっているという。
さらに、2015年には「対テロリズム及び安全保障法」が成立し、テロ防止のための脱過激化プログラムが強化された。地方自治体、刑務所、保護観察、福祉部門の職員、学校や大学の教員、NHS(国家医療制度)の医師、看護士は、過激化の兆候を見つけたら当局に報告することが義務付けられた。
英国は、過去4年間で13件の大規模テロを未然に防ぎ、常に500件を調査対象としているという。要注意リストには約3000人が掲載され、別の300人を監視下に置いている。毎月、テロリストの疑いありとして逮捕される人数は大変な数に及んでいる。要するに、英国のテロ対策とは、警察と情報機関が長年にわたって作り上げてきた情報網・監視体制をフルに使って、テロを水際で防ぐということである。
フランスのテロ対策は
軍隊・警察の武装強化が中心
一方、フランスのテロ対策は、「目に見える形での治安維持の強化」によってテロを抑止するというものだ。2015年1月に起きた風刺週刊誌シャルリー・エブド襲撃事件を契機にして、フランスでISによる大規模なテロ事件が頻繁に起きるようになっている。フランソワ・オランド大統領(当時)は、頻発するテロに対抗するため、既存の軍隊、警察組織に次ぐ新たな治安維持組織として「National Guard(国家警備隊)」を新設した。
既存の軍隊、警察もテロ対策を強化している。フランス内務省は、軍隊が使用する戦闘用の自動小銃を、憲兵隊と警察の犯罪担当班に装備させる、新しい武装計画を決定した。シャルリー・エブド襲撃の折に、重装備のテロリストと至近距離で対峙した警察官が、これに対処できる装備を持たなかったことで、テロリストを逃がしてしまった反省から決定された。2018年までには警察全体に訓練を施し、全国どこでも20分以内にこの武器を装備して駆けつけられるように配備を進める方針だ。このように、フランスでは、武装した憲兵や警察が、主要駅や街頭を警戒する光景が日常となっている。
フランスのテロ対策を困難にする
民主主義の厳格な運用
フランスは、ISのテロの最大の攻撃目標となっているといわれる。2015年以降、238人がテロで死亡している。大統領選の第1回投票前には、パリ中心部のシャンゼリゼ通りでISの戦士と見られる男と警官4人と銃撃戦になり、警官のうち1人が死亡、2人が重傷を負った。テロ犯は治安部隊に射殺され、市民や観光客に犠牲者は出なかったが、大統領選の主要候補は翌日に予定していた選挙集会などの開催を取りやめた。
フランスがISのテロの標的になってきたのは、フランス特有のテロ対策の難しさがあるからだ。ブルカ禁止法や、全身を覆う水着ブルキニ禁止論争がフランス国内のイスラム社会のフラストレーションを増幅させ、教育格差や就職差別によってムスリムの若者が社会からの疎外感を感じ、アイデンティティクライシスを起こしている。その結果、テロリスト組織に加わる若者が少なくない。フランスはテロリストにとって隙だらけなのだ。
だが、フランスでイスラム系移民の社会統合が進まず、テロ対策が困難なのは、実は「民主主義」を厳格に実行しようとするからだ。フランスは、「共和国であるフランスには移民はいない」という建前を取っている。アフリカから来た人も、中東からきた人も、フランス国籍を持つ限り、皆同じなのだということだ。
ところが、その建前があるために、移民の権利を保護したりする法律が制定されていない。結果、マイノリティである移民は単純労働以外の職に就けないなど社会から阻害され続けてきた。その不満の爆発が、テロの背景にある。
また、民主主義の厳格な運用は、監視カメラの設置など、警察・情報機関による情報収集、監視体制の構築の妨げになっている。「内心の自由」など、基本的人権の保護が徹底されているフランスでは、監視の強化によってテロを防ぐという考え方は理解を得にくいのだ。実際、フランス国内の監視テレビの数は、英国の3分の1以下だといわれている。
要するに、民主主義の厳格な実行を追求したために、警察や情報機関の活動が制限されて、結果として、パリ市内やドゴール空港に自動小銃を持った警官や憲兵が多数立つという、物騒な社会となってしまったということだ。
英国で権力の乱用を防ぐ
ジャーナリズムと政権交代ある政治
一方、英国であるが、政府は英国社会にマイノリティが存在することをはっきり認めている。そして、マイノリティを保護する制度が多数設けられている。その結果、英国ではマイノリティも社会に参加する機会が与えられ、医者と弁護士は多くがインド系であるように、移民は英国社会に根付いて名誉ある地位を占めるようになっている。
これはフランスからすれば、民主主義の「いい加減な運用」ということになるだろう。そして、いい加減さゆえに、国民の「内心の自由」や「情報公開」などの民主主義の重要な構成要素についても、柔軟な運用をしている。
前述の通り、英国は高度な「監視社会」が構築されている。そして、警察と情報機関は知り得たことの情報源を明かすことはないし、英国民は基本的にそれを特別に問題視していないように思える。
英国で「監視社会」が認められている理由は、この連載で指摘してきたように、権力に対して委縮することがない強力なジャーナリズムの存在、それを支える政権交代のある政治であろう。
英国は、日本の「テロ等準備罪」が想定するようなテロ対策を実施しているし、特定情報保護法に相当する「公務秘密法」がある。しかし、ジャーナリストなど一般国民を有罪とした事例は過去ない。英国では、政権が権力乱用を安易に行うことはできない。国民がそれを不当だとみなした場合、政権は容赦なく次の選挙で敗れ、政権の座を失ってしまうからである(2013.12.6付)。
「テロ等準備罪」の国会論戦の争点は
テロが頻発する世界での日本社会のあり方
日本で、英国のような「監視社会」の構築によるテロ対策が、国民から理解を得るのは難しい。過去の忌まわしい歴史があるからだ。1925年に成立した「治安維持法」は、共義主義の弾圧から始まったが、次第に拡大解釈され宗教団体や右翼活動、自由主義等、すべての政府批判が弾圧の対象となっていった。そして、言論弾圧による権力の暴走を止められず、敗戦への道を進んだ。日本の過去の過ちを繰り返してはならないという批判は、いまだに根強いものがある(2013.12.6付)。
しかし、現状のまま何もしないというのもあり得ないだろう。英国もフランスも、方向性は真逆だが、テロ対策を徹底的に行っていた。それでも、テロを防ぎ切ることはできなかった。東京五輪やラグビーW杯など、世界的なビッグイベントを開催する日本が、テロの標的にならないとは言い切れない。何らかの対策は必要だ。
だが、日本国民が、フランスのように「内心の自由」など人権・民主主義を守るために、街中に自動小銃を持った警官が多数配備されるような社会を受け入れるかといえば、それも難しいだろう。
それでは、日本人はどうすべきなのだろうか。街中には自動小銃を持った警官が立たず、非常に穏やかな雰囲気を保つが、その裏で網の目のような情報網でテロを防ぐ「監視社会」がいいだろうか。民主主義を厳格に守るが、そのためにテロを未然に防ぐための情報網を構築できず、街中に自動小銃を持った警官が多数立って、テロを抑止しようとする社会を選ぶのだろうか。本来、「テロ等準備罪」を巡る国会論戦は、テロが頻発する厳しい国際情勢の下でどのような社会を望むのかが、争点となるべきではないだろうか。
(立命館大学政策科学部教授 上久保誠人)