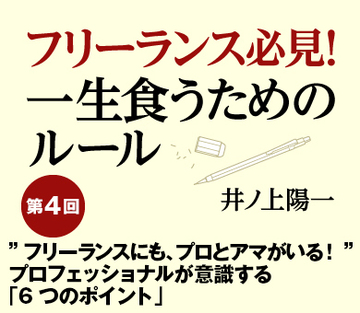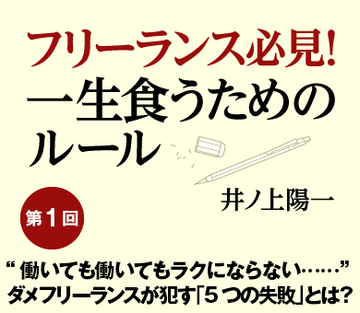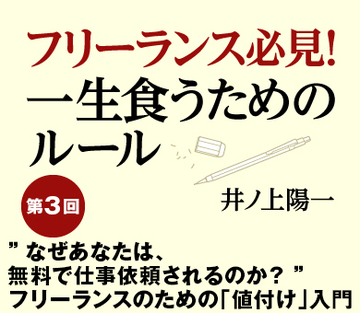「仕事相手が全員年下」「自己模倣のマンネリ地獄」「フリーの結婚&子育て問題」……Twitterで話題を呼んだ〈フリーランス、40歳の壁〉。本物しか生き残れない「40歳の壁」とは何か、フリーとして生き抜いてきた竹熊健太郎氏がその正体に迫ります。著書『フリーランス、40歳の壁』では自身の経験のみならず、田中圭一さん(『うつヌケ』)、都築響一さん、FROGMANさん(『秘密結社 鷹の爪』)ほか、壁を乗り越えたフリーの話から「壁」の乗り越え方を探っています。本連載では一生フリーを続けるためのサバイバル術、そのエッセンスを紹介していきます。
連載第1弾は、『フリーランス、40歳の壁』オンライン番外編!40歳過ぎにサラリーマンとしての地位を投げ捨てて、フリーへと転身したアニメ・特撮研究家である氷川竜介氏にその選択の意味を問います。フリーでやっていく条件は何か、サラリーマンを辞めることのメリット・デメリットなどを聞いていきます。一生、フリーを続けるためのサバイバル術がここに!
学生時代に元祖・アニメライターとなる
氷川竜介さんは、アニメ評論家であり研究家であり、編集者・フリーライターであります。ことテレビアニメに関しては、先ほどの肩書きに「日本を代表する」を冠してもいいかもしれません。1958年に兵庫県姫路市に生まれ、物心ついた頃に日本最初のテレビアニメ『鉄腕アトム』が始まりました。私と氷川さんは彼のほうが学年が3つ上ですが、ほぼ同世代と言っていいでしょう。高校在学中には『宇宙戦艦ヤマト』のスタジオを見学していたといいますから、筋金入りのマニアだと言えます。
氷川さんは、高校時代に故・竹内博氏(怪獣映画研究家)主宰の『怪獣倶楽部』の同人となり、アニメや特撮映画のファン活動、いわゆる「同人活動」を始めました。その後『ヤマト』でもファンジン(同人誌)を編集・執筆し、東京工業大学工学部電子工学科在学中には1977年に突然巻き起こった「ヤマトブーム」で、ファンの立場、マスコミの立場の両方からその中心にいることになります。ヤマトブームは、すぐにアニメブームに広がります。1978年から続々とアニメ専門誌が創刊されるのですが、氷川さんは、学生でありながらアニメに詳しいライターとして重宝されるようになりました。
 氷川竜介(ひかわ・りゅうすけ)
氷川竜介(ひかわ・りゅうすけ)1958年兵庫県生まれ。アニメと特撮についての執筆を中心に活動し、理系的な分析力で作品の魅力と本質を探る。文化庁メディア芸術祭アニメーション部門歴代審査委員。2018年4月より明治大学大学院特任教授に就任。学部、大学院ともにポップカルチャー研究として「特撮」を扱う講義を新規に推進中(おそらく大学では初)。2017年に「アニメ100年」関連の個人誌を出し、通史の書き下ろし単行本を準備中。また「アニメ特撮アーカイブATAC」(理事長:庵野秀明)の理事に就任し、制作関係資料の保全など公的活動にも従事中である。
「大学入学が1977年、卒業が1983年で6年間在籍しました。高校3年のときにアニメのファンサークルを始め、受験時期は活動に限界がありましたが、大学合格と同時に『月刊OUT』というサブカル雑誌創刊2号「宇宙戦艦ヤマト」特集に参加します。児童向け以外でアニメを扱った最初期の雑誌です。
アニメや特撮の専門誌が生まれる前でしたから、そうしたジャンルに詳しい専業のプロはいなくて、いわゆるマニアしかいなかった。だから、アマチュアに原稿を書かせるしかない時代だったんです。それで現地徴用兵的に起用された。学生アルバイトというより、SFの世界で言うセミプロ感覚に近いです。
『OUT』以外では『てれびくん』『テレビマガジン』『テレビランド』など児童雑誌の仕事が多かった。あとはキングレコードで『機動戦士ガンダム』のLPレコードを放送中から手伝い、ドラマ編という音声で物語をまとめる仕事や音楽集の構成もしています。」
『フリーランス、40歳の壁』で取材した同世代(1980年前後に大学生だった世代)の多くがこのパターンなのですが、在学中にミニコミや特定の趣味にのめり込み、そのまま「フリーランスの出版業界人」になってしまう人は多いのです。もちろん、こういう人はいつの時代にも存在すると思うのですが、記憶を堀り起こせば、1980年代はとりわけその傾向が強かったように思います。「趣味」が仕事になると、本気で信じられた時代だったのです。
しかし氷川さんは、ライター仕事に忙しくて大学を留年しながらも、すぐにプロライターにはなりませんでした。氷川竜介といえば、アニメブームとともに生まれてきたようなライターです。ジャンルの勃興期で、ライバルはほとんどいませんでした。学生ライターとして何誌にも原稿を書き、ほぼ最初から、その道の第一人者でした。大学を卒業する頃も、アニメブームは消え去るどころか衰えずに燃え盛っていました。こういう場合、そのままライターとして暮らしてもやっていけると考える人が多いと思います。少なくとも私はフリーの道以外、眼中にありませんでした。周囲にもそういう人が多かったですし、趣味と仕事の区別がつかないような、そういう時代だったのです。でも氷川さんは賢明にもアニメは趣味として続けつつ、サラリーマンとして就職する道を選んだのです。
彼は通信系のエンジニアとして、1983年に富士通に就職しました。技術系サラリーマンとしては優秀でした。87年には技術サポートとして、7ヵ月間、アメリカ・アリゾナ州フェニックスに長期出張もします。
帰国して、仕事のテスト用として1988年にニフティ・サーブというパソコン通信に入ります。パソコン通信とは、一般の電話回線を使ったネット通信サービスで、特定のプロバイダ、たとえばニフティならニフティの会員の間だけでチャットや掲示板が使えるというものです。その意味では全世界規模のインターネットとは違う、ローカルな通信サービスでしたが、最盛期の1996年には会員数が200万人を超える規模を誇りました。しかしインターネットの普及とともに、ローカルなパソコン通信はその使命を終えます。氷川さんは88年からニフティの「アニメフォーラム」に出入りするようになって、氷川さんの運命は再びアニメ界に引き寄せられることになりました。
「アニメフォーラムには大勢の参加者がいたけど、アマチュア中心なので交わされるアニメ知識が、失礼ですがヌルいと思ったんですよ(笑)。だから最初は冷ややかに見ていましたが、そのうちガマンできず書き込むようになり、「ロト」というハンドルネームを使いました。当時流行っていたゲーム『ドラゴンクエスト』の勇者の称号で、固有名詞のつもりですらなかったのです。これが僕の愛称として定着してしまい、インターネット時代の今でも使っています。」
氷川さんは30歳直前に参加されたそうですが、アニメファンとしてはすでに「長老」格でした。パソコン通信の世界では“ロトさん”と言えばアニメ好きなら一目置かれる存在になっていきます。なにしろ伝説の『宇宙戦艦ヤマト』の制作現場をこの目で見ている古参ファンなのです。アニメファンとして氷川さんの上に立つものがいるとすれば、それはアニメーターや監督など、現場の修羅をくぐった人間くらいでしょう。
90年代アニメ批評の勃興
GAINAXの創業社長だった岡田斗司夫氏と知り合ったのも、ニフティ・サーブがきっかけでした。1990年のことです。チャットで盛りあがり、フォーラム有志でGAINAXに招かれ、盛大なオフラインミーティングもやりました。そのあたりから、ネットを介して製作者とエンドユーザーがダイレクトに交流することが始まったと、氷川さんは回想します。
富士通に就職してからは、仕事として雑誌に文章を発表することは長くお休みしていました。ところが1990年代の初頭から『ウルトラマン研究序説』のような、アニメや漫画をアカデミックに研究するブームが起こり始めたのです。それまで子どもや特殊なマニアのものとされていたアニメや特撮、マンガのようなサブカルチャーが、いきなり衒学的な研究対象になり始めたのでした。これは「オタク」と呼ばれるようになった1950年代後半から1960年代生まれの人々が、30代になっていたことが影響していると思います。ファンの単なる感想や制作サイドの宣伝文ではない、批評として中身がある文章が求められ始めたと言えます。『新世紀エヴァンゲリオン』の放映が終了して劇場版が公開された1997年頃に、そうした「大人のためのアニメ批評」の需要はピークに達していたと言えます。
「エヴァが終わって、ファンが大騒ぎしている最中に『デラべっぴん』というグラビア雑誌で『エヴァ特集』が組まれたんです。岡田斗司夫さんのご紹介ですが、誌面構成と寄稿をしたのが僕の再デビューの大きなきっかけになります。『庵野秀明監督の映像は実相寺昭雄監督ゆずりだ』とか、なかなか他のアニメ雑誌では書かれていないようなことを、ぶつけてみました。」
当時、岡田斗司夫氏はGAINAXの社長を辞し、東京大学で「オタク学」を講義したり、『僕たちの洗脳社会』という本や『おたく学叢書』を立ち上げて、マスコミの注目を集めていました。そして『オタク学叢書』の一冊目として氷川さんの初著作である『20年目のザンボット3』があったのです。いわば、岡田氏が巻き起こしたオタクブームに巻き込まれる形で、氷川さんは業界に復帰したと言えます。
「その時点でのアニメを語る言説とは、ファンの他愛ないおしゃべり的なものか、または本格的な学者が自身の専門分野をバックに語る硬い言葉か、どちらかしかなかったという印象です。その中間の領域で、アニメを純粋にアニメとして語れる人があまりいなかった。その意味で僕は独特のポジションにいたように思えます。」
近年、経産省がアニメやマンガを積極的に扱ったクール・ジャパンが盛り上がっています。アニメは日本の有力な輸出文化として注目を集めているわけですが、氷川さんが本格的にアニメ評論を始めた契機は、マンガや映画とは違って、アニメはナチュラルな文化としては後世に残らないのではないか、せっかくの作品も消費されて終わってしまうのではないか、という危機意識があったからだと言います。
「時代が推移しても、作品を語るのは好き・嫌いの刹那的な言葉だけ。ならば、パッケージやコンテンツとしては残るかもしれませんが、作品が発表されたその時に受けた自分たちの「想い」のようなものは、きちんと言葉にしておかないと、観客全員の死とともに消えてしまうのではないかと思ったわけです。送り手と受け手の想いとつながることで作品が受容されたはずで、回路みたいな「系」が残らないと、アニメは文化にならないという確信もありました。」