企業は、どんどん若い勤労世代に賃金分配をしなくなっている。20歳代以下の勤労者に配分した雇用者報酬総額は、1999年に55兆円だったと推計されるが、2011年には37兆円にまで減ってしまっている(▲39%減、図表1参照)。
この間、雇用者報酬は、総額で▲9%ほど減額されているが、配分率自体も1999年の20.4%から、2011年の15.1%へと大幅低下している。
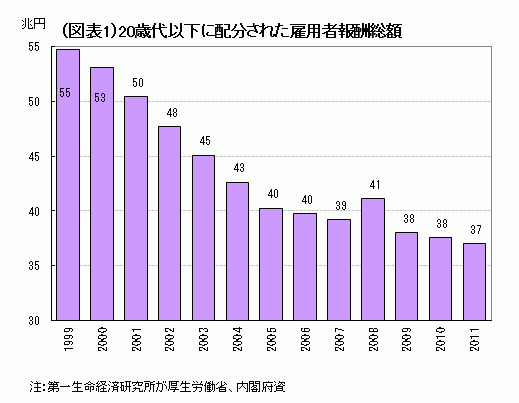
このデータ解説を聞いて、若者の人数が減っているので、20歳代以下に配分した報酬額が減っていても仕方がないと考える人は多いだろう。本当にそう考えてよいのだろうか?
筆者は、実はその点こそが大問題であると考える。なぜ、人数が少なくなっているのに、同額の人件費を分かち合わないのか。人数が少なくなった分だけ、1人当たりの分配金を引き上げることでは、何がいけないのか。
思い出してほしいのは、2006~2009年に団塊世代がリタイヤして、企業が支払う総人件費は大幅に軽減されたことだ。筆者の計算では、企業が2005年に支払っていた50歳代の人件費は65兆円だったのが、2010年に58兆円へと▲7兆円ほど軽くなった。だが、▲7兆円は他の年代の報酬に分配されることなく、単なる総人件費の削減で終わった。
なぜ、1人当たりの
人的投資を増やさないのか
筆者は、若者が格差に苦しんでいるから賃金を増やしてほしいなどと主張するつもりはない。パイが小さくなるのに世代間闘争をやっても社会的利益は乏しい。
重要なのは、公正・平等の視点ではなく、効率・成果に対する悪影響である。頭数が減ったから総額も減らそうという発想に、縮小均衡のメカニズムが潜んでいる。







